ブランディングとは?再認と再生、選ばれる企業になるためのブランド構築を徹底解説!
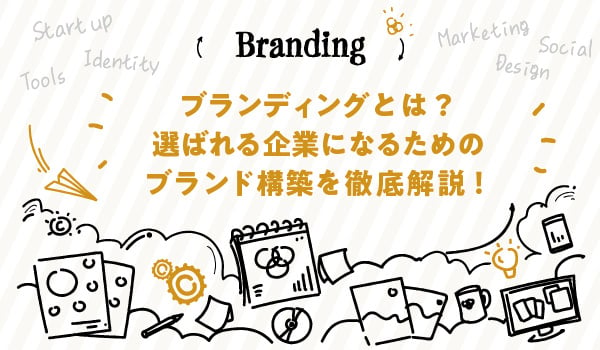
ブランディングとは、自社の商品やサービス、そして企業そのものを「唯一無二の存在」として市場に位置づけ、顧客の記憶と選択肢に残すための長期戦略です。単なる認知拡大ではなく、経営理念を基盤に、経営戦略 → マーケティング戦略 → コミュニケーション戦略までを一貫して顧客視点で設計し、「自社が思われたいイメージ」と「顧客が抱くイメージ」を重ねることを目的とします。ジャリアでは、マーケティングを「売れる仕組み」、ブランディングを「売れ続ける仕組み」と定義し、この一貫性をブランドの土台としています。
例えば、消費者が特定のカテゴリーの商品を検討する際に「このブランドなら間違いない」と自然に思い浮かべる状態や、看板やロゴを見ただけでポジティブな感情や信頼感が湧く状態は、ブランディングが成功している証拠です。これは、デザインや広告だけでなく、日々の顧客体験、社員の態度、社会への姿勢といったあらゆる接点が積み重なった結果生まれるものです。
現代は情報過多の時代。競合との違いが瞬時に比較され、顧客の選択肢も多様化しています。その中で選ばれ続けるためには、単発の施策や短期的なキャンペーンではなく、内側(インナー)と外側(アウター)をつなぎ、全社的に一貫したブランド体験を設計することが不可欠です。本ガイドでは、ジャリアが実務で培った経験と独自の設計思想をもとに、ブランド構築の全体像と具体的な実践方法を解説します。
|
目次 |
本記事と合わせてご覧いただくことで、ブランディングの全体像と各テーマの実践方法をより深く理解できます。
以下のリンクから、目的に応じた詳細解説ページへアクセスしてください。
- ▶ブランディングとマーケティングの違いや関係性を解説!
- ▶ブランドストーリーの作り方と企業ブランディングへの活かし方
- ▶インナーブランディングとは何か?社内から始めるブランディング戦略
- ▶ブランディングとロゴデザインの関係 ロゴの役割から制作ポイントまで解説!
- ▶ブランディング動画とは?動画を活用してブランド価値を高めよう!
- ▶ブランドブックとは?インナーブランディングに必須ツールの制作目的やポイントを解説
- ▶デジタルブランディングとは?重要性やメリット、具体的な施策を解説!
- ▶ブランディングとSEOの関係性と成果を出す施策設計
ブランディングとは何か?その本質と目的
ブランディングは、企業や商品・サービスを「他とは違う存在」として顧客に印象づけ、長期的に選ばれるための戦略です。現代の市場は情報が氾濫し、顧客は瞬時に選択を迫られます。この中で価格や機能だけで競争するのは限界があり、ブランドの存在意義や価値観が選択基準として重視されるようになっています。
ジャリアでは、単なる見た目や広告だけではなく、理念・価値提供・顧客体験を一貫して設計し、内外から支持されるブランドを構築することを重視しています。本節では、その本質と目的を整理します。
情報過多の時代におけるブランドの役割
ブランディングとは、自社の商品・サービス・企業そのものを他社と明確に差別化し、顧客の中に特定のイメージを根付かせるための戦略的活動です。単なるロゴや広告のことではなく、企業が持つ理念・価値観・提供価値を一貫して届けるための総合的な取り組みです。
現代は、SNSや検索エンジンを通じて情報が氾濫し、顧客は数秒単位でブランドを選別する時代です。この環境下では、一時的な広告効果だけでは顧客の記憶に残ることは困難です。重要なのは、企業が何者で、どのような価値を社会や顧客に提供する存在なのかを明確にし、それを全ての接点で一貫して発信・体現することです。
例えば、ある飲料メーカーが「健康的で持続可能なライフスタイルの提案」をブランドの核に据えている場合、商品設計、パッケージ、広告表現、店頭体験、さらには社員の接客態度まで、その価値観が反映されている必要があります。この一貫性こそが、顧客の信頼を醸成し、長期的なブランドロイヤルティへとつながります。

一貫した信頼と選ばれる力の基盤
ブランディングの目的は、顧客の中で「このブランドは自分に合っている」「信頼できる」と感じてもらい、選ばれ続ける存在になることです。価格や一時的なキャンペーンに依存しない選ばれ方を実現できれば、企業は安定した売上基盤を築くことができます。
ジャリアの考えでは、この「選ばれる力」を構築するには、経営理念から顧客接点までを一本の線でつなぐ必要があります。私たちは、ミッション・ビジョン・バリューを土台とし、経営戦略 → マーケティング戦略 → コミュニケーション戦略へと派生させる構造を重視しています。この全体をブランド戦略と位置づけ、すべての施策が同じ方向を向くように設計します。
結果として、顧客はどの接点でも同じブランド世界観を感じ取り、安心感と一貫性を認識します。これが長期的なファンの獲得と、競合優位性の確立につながるのです。
ブランディングとマーケティングの違い
ビジネスの現場では「ブランディング」と「マーケティング」という言葉が混同されがちです。しかし、この2つは目的もアプローチも異なります。マーケティングは、ターゲットのニーズを把握し、それに応える商品やサービスを市場に適切に届けるための施策全般を指します。一方、ブランディングは、企業や商品の存在意義・価値観・世界観を一貫して発信し、顧客の記憶や感情に根付かせるための戦略です。
ジャリアでは、マーケティングを「売れる仕組み」、ブランディングを「売れ続ける仕組み」と定義しています。両者の最大の違いは時間軸と視点です。マーケティングは顧客ニーズに応じた販売促進を短期的に設計するのに対し、ブランディングは経営理念をベースに、経営戦略からコミュニケーション戦略までを顧客視点で一貫設計し、企業のありたい姿と顧客が抱く印象を重ねていく長期戦略です。この一致が実現すれば、顧客は迷わず繰り返し選び続けます。
長期視点の「価値設計」と短期施策の違い
ブランディングは、顧客に信頼や愛着を持ってもらい、長期的に選ばれる存在になるための価値設計です。そのため、成果が見えるまでに時間がかかることが多いですが、一度確立されると価格競争に巻き込まれにくくなります。
一方、マーケティングは、比較的短期間で売上や集客を向上させることを目的とする施策が多く、広告キャンペーンや販促活動、SEO施策などが該当します。短期的な成果を出す一方で、ブランドとしての軸が定まっていなければ、施策ごとに方向性がブレるリスクがあります。
両者を融合した成果に繋がる設計論
ブランディングとマーケティングを効果的に融合させるには、まずブランドの基盤(理念・価値観・ターゲット像)を明確にすることが前提です。ジャリアでは、ブランドステートメントを核として、この基盤を全社で共有します。
その上で、マーケティング施策をブランドの方向性に沿って展開することで、短期的な成果と長期的なブランド価値向上を同時に実現します。例えば、新規顧客獲得のためのキャンペーン広告でも、ブランドのトーンや世界観を崩さずに設計すれば、単発の売上だけでなくブランド認知やロイヤルティにもつながります。
マーケティング=売れる仕組みであり、ブランディング=売れ続ける仕組みと考えています。

ブランディングの種類と全体設計への位置づけ
ブランディングには、対象やアプローチの違いによって複数の種類があります。特に企業活動においては、外部への発信を中心とした「アウターブランディング」と、社内に理念や価値観を浸透させる「インナーブランディング」が代表的です。さらに、この二つを有機的につなぎ、外部と内部の体験を一致させる「統合ブランディング」という考え方も欠かせません。
ジャリアでは、この3つを切り離して設計するのではなく、ブランド戦略全体の中で相互に補完し合う構造をつくることを重視しています。本節では、それぞれの特徴と役割、そして全体設計における位置づけを解説します。
アウターブランディング:外部発信の型
アウターブランディングは、顧客や市場といった社外のステークホルダーに向けて行うブランディング活動です。広告、広報、SNS運用、イベント、ホームページ、動画コンテンツなど、多様なチャネルを活用してブランドの価値や世界観を発信します。
目的は、ブランドの認知度を高め、特定のイメージを市場に定着させることです。しかし単なる情報発信に留まらず、発信内容やトーンがブランドの理念と一致しているか、顧客の体験にどう結びつくかが重要です。
インナーブランディング:社員共感の仕組み
インナーブランディングは、企業内部の従業員に対して理念やブランド価値を浸透させ、日常の行動や意思決定に反映させる取り組みです。ブランドは顧客接点だけでなく、社員が日々体現する行動やコミュニケーションによって強化されます。
ジャリアでは、ブランドステートメントをベースに、ワークショップや社内共有ツールを用いて、社員がブランドの「意味」と「価値」を自分ごと化できるプロセスを設計します。
インナーとアウターを繋ぐ統合設計の必要性
インナーとアウターを別々に進めると、外部に発信しているメッセージと内部で共有されている価値観がズレる危険があります。このズレは、顧客体験に不一致を生み、ブランド信頼度を損ないます。
統合設計では、ブランドステートメントを軸に社内外のすべての接点で一貫した価値提供を行います。これにより、顧客がどの接点に触れても同じブランド体験を得られ、ブランドイメージの強化と持続的な信頼構築が可能となります。

インナーブランディングとは?その定義と意味
インナーブランディングとは、企業の理念や価値観、ブランドの方向性を社内の全従業員に浸透させ、日々の行動や意思決定に反映させるための取り組みです。外部への発信を強化する前に、まず社内からブランドを理解・体現する文化を築くことが、持続的なブランド価値の源泉となります。特に近年は、SNSや口コミを通じて従業員の声や行動が直接的にブランド評価に影響する時代です。
そのため、単なる社内周知ではなく、社員が「自分ごと」としてブランドを語り、顧客接点で一貫したブランド体験を提供できる状態をつくることが不可欠です。本節では、インナーブランディングの定義とその重要性を解説します。
内側からの共感が選ばれるブランドをつくる
インナーブランディングの最大の目的は、社員一人ひとりがブランドの価値を理解し、自らの言葉や行動でそれを表現できるようにすることです。外部施策だけでは作れない信頼や共感は、内部から自然に醸成されます。
例えば、カスタマーサポート担当者が顧客対応で見せる姿勢や言葉遣いが、ブランドの価値観と一致していれば、その体験は顧客に強く印象づきます。これは広告では得られない深いブランド体験となり、顧客ロイヤルティの向上につながります。
社員アンバサダー育成の重要性
社員アンバサダーとは、ブランドの価値や理念を社内外に発信し、共感を広げる役割を持つ従業員のことです。彼らは顧客接点でのブランド体現だけでなく、SNSでの発信やイベント参加を通じてブランドの「顔」として機能します。
ジャリアでは、社員アンバサダーの育成をインナーブランディングの重要な柱と位置づけ、研修や評価制度にも組み込むことで、ブランド理念が日常的に息づく組織文化を育んでいます。
ブランドの柱(Brand Pillars)を定義する
ブランドを長期的に成長させるには、単発的なキャンペーンや表層的なデザイン変更だけでは不十分です。ブランドの存在意義や独自性を支える「柱」を明確に定義し、それを軸にすべての活動を展開する必要があります。この柱は、ブランドの方向性を示すコンパスであり、経営戦略から日常の顧客対応に至るまで、あらゆる意思決定の基準となります。
ジャリアでは、この柱を「Brand Pillars」と呼び、**Purpose(存在意義)/Positioning(独自性)/Personality(人格)/Perception(受け止め方)/Promotion(伝える力)**といった要素を整理し、ブランド全体の骨格として構築します。本節では、その定義と設計のポイントを解説します。
ブランドのPurpose(存在意義)は何か
Purposeは、そのブランドが「なぜ存在するのか」という根本的な問いに答える要素です。売上や市場シェアの拡大といったビジネス的目標を超えて、社会や顧客にどのような価値を提供するのかを明確にします。明確なPurposeは、社内外の共感を生み、ブランドへの支持を長期的に高めます。
Positioning(独自性)を強く設計する
Positioningは、競合との差別化を図るための立ち位置を示します。市場内で「どこにポジションを取るのか」を明確にし、顧客がそのブランドを選ぶ理由を一言で説明できる状態を目指します。ここでは、機能的価値だけでなく情緒的価値や社会的価値も含めて検討します。
Personality(人格)/Perception(受け止め方)の一致
ブランドにも人格があります。それは言葉遣い、デザイン、顧客との接し方などに表れます。この人格(Personality)が顧客の受け止め方(Perception)と一致していることが重要です。もし社内の想定と顧客の印象にズレがあれば、メッセージの修正や体験設計の見直しが必要です。
Promotion(伝える力)の戦略設計
Promotionは、ブランドの価値や存在意義をどのように伝えるかの戦略です。単なる情報発信ではなく、誰に、どのタイミングで、どのチャネルを通じて届けるかまで設計します。ブランドの柱に沿った一貫した発信は、認知だけでなく信頼の獲得にも直結します。

ブランドを“人らしく”語るストーリーフレーム
優れたブランドは、単なる情報や数値ではなく、感情に訴えるストーリーを持っています。現代の顧客は、機能や価格の比較だけで商品やサービスを選ぶのではなく、その背景にある「物語」に共感し、ブランドに惹かれます。
ストーリーは、企業の理念や歴史、顧客とのエピソードを通して紡がれ、ブランドを“人らしい存在”として感じさせる役割を果たします。ジャリアでは、このストーリー設計をブランド構築の中心に据え、創業背景や使命、提供する価値を体系的に語るフレームを活用しています。本節では、そのフレームと実践方法について解説します。
創業ストーリー/背景に共感の軸を置く
創業のきっかけや、事業が生まれた背景には、そのブランドの存在意義が凝縮されています。どのような課題を解決したいと考え、どのような信念で立ち上げたのかを語ることで、顧客はブランドの根幹に触れることができます。
たとえば、地域の課題解決を目指す企業であれば、その地域に対する想いや取り組みを語ることが、ブランド価値を高める重要な要素になります。創業ストーリーは、事実だけでなく情緒的な側面も含めて伝えることが効果的です。
実践事例を通じて理念を“体験”させる語り方
理念を単にスローガンとして掲げるのではなく、具体的な事例や顧客体験を交えて語ることで、ブランドはよりリアルに伝わります。顧客がブランドの価値を体感できるエピソードは、感情的なつながりを生み、長期的な関係構築につながります。
ジャリアでは、ブランドステートメントを核にしながら、理念と現場の事例をリンクさせる「ストーリー台本」を作成します。これにより、どの社員も一貫性のあるブランドストーリーを語れるようになります。
ジャリア式ブランディングの起点 ブランドステートメント作成
ジャリアのブランディングは、必ずブランドステートメントの策定から始まります。ここで重要なのは、経営理念を起点に経営戦略 → マーケティング戦略 → コミュニケーション戦略までを顧客視点で一貫させる設計です。ステートメントは企業の「こう思われたい」という姿を明文化し、顧客が抱く印象と重なるポイントを意識して作られます。こうした設計により、マーケティングで得た顧客接点を、ブランディングで長期的な信頼とロイヤルティに転換します。
ブランドステートメントを策定することで、企業がブレない軸を持ち、インナー・アウター双方のブランディングを高い精度で実行できる環境をつくります。本節では、その役割・構成要素・作成プロセス・活用例について解説します。

ブランドステートメントの役割と構成要素
ブランドステートメントは、企業の核となる価値観と約束を簡潔にまとめたもので、以下の要素で構成されます。
|
構成要素 |
内容 |
|---|---|
|
ミッション(Mission) |
企業が果たすべき使命や存在理由 |
|
ビジョン(Vision) |
将来的に実現したい姿 |
|
バリュー(Value) |
社内外で大切にする価値観 |
|
ポジショニング(Positioning) |
競合と比較した際の独自の立ち位置 |
|
ブランドパーソナリティ(Personality) |
ブランドの人格的特徴 |
|
ブランドプロミス(Promise) |
顧客に対して必ず守る約束 |
作成プロセスと社内外への共有方法
ジャリアでは、ブランドステートメントの作成を以下の流れで進めます。
- 現状分析:市場環境、競合、顧客の声をリサーチ
- 理念の言語化:経営層とワークショップを行い、理念・価値観を抽出
- 構造化:抽出した内容をMission / Vision / Valueに整理
- ステートメント化:読みやすく、感情に響く文章に落とし込む
- 共有・浸透:社内説明会、マニュアル、社外発信などで周知
ブランド施策全体の軸としての活用例
完成したブランドステートメントは、マーケティングや採用活動、商品開発、広報活動などあらゆる場面での判断基準になります。また、社内では行動規範として活用でき、外部では一貫性のあるブランド体験を生むためのガイドラインとして機能します。
ブランディングがもたらす具体的なメリット
ブランディングは、単なる企業イメージの向上にとどまらず、経営の安定性や市場競争力の強化にも直結します。明確なブランド戦略を持ち、一貫した体験を提供できる企業は、価格競争から抜け出し、独自の価値基準で選ばれる存在になれます。また、顧客や求職者からの信頼が高まり、リピーターや優秀な人材が自然と集まる好循環が生まれます。
ジャリアの経験でも、ブランド戦略を体系的に実行した企業ほど、短期的な売上だけでなく長期的なファンベースの構築に成功している事例があります。近年の調査でも、強いブランドを持つ企業は市場平均を20%以上上回る成長を示すとされ(BCG調査)、その効果は数字でも証明されています。
価格競争からの脱却と新市場開拓
ブランド価値が確立されることで、顧客は単なる価格比較ではなく、そのブランドの持つ世界観や信頼性、品質、アフターサポートなど総合的な価値で判断します。
実際、ブランド戦略を確立した企業は5年間で市場平均を20%以上上回る成長を遂げているという調査結果もあります(BCG, 2021)。こうした成長は、新市場開拓や高付加価値商品の展開を後押しし、企業が「唯一無二」として選ばれる状態を生み出します。
人材確保とエンゲージメント強化
魅力的なブランドは、顧客だけでなく求職者や社員にも強い影響力を持ちます。企業文化や価値観が明確で一貫しているブランドは、共感する人材を引き寄せ、採用コストを抑えながら優秀な人材確保につなげます。
また、ブランドに共感して入社した社員は、自発的にブランドを体現する行動を取りやすく、結果としてエンゲージメントや定着率の向上につながります。こうした社内ブランディングの効果は、ブランド戦略を持たない企業よりも社員満足度が高い傾向があることが複数の調査で示されています(junotype.com)。
ジャリアでも数年前のリブランディングの機会にブランドを再構築し、採用面にも活かした結果、採用でのマッチングの質が向上し期待する人材の獲得ができたという経緯があります。また入社後もブランドに基づいた行動や活動を行ってもらうため、ミスマッチが起こりにくく離職の防止にも繋がっています。
顧客体験に根差したブランド価値向上
ブランドとマーケティングを統合的に設計することで、企業は各顧客接点で一貫した体験を提供できます。これが顧客の信頼を醸成し、再購入や推奨行動(口コミ)へとつながります。
Forresterの調査では、ブランドとマーケティングを統合設計した企業はコンバージョン率が23%高いという結果も報告されています(Equinet Media)。また、Analytic Partnersの分析によると、ブランドマーケティングは短期成果だけでなくロイヤルティ醸成にも効果を発揮し、80%のケースでパフォーマンス施策を上回るROIを記録しています。

デジタル時代のブランディングの重要性
スマートフォンとSNSが生活の中心となった現代では、ブランドと顧客の出会いは、店舗や営業担当者を介さず、オンラインで完結するケースが急増しています。検索結果、SNSフィード、YouTube広告、メールニュースレターなど、デジタル上の接点がブランドの第一印象を決定づける時代です。こうした環境下では、オフラインだけでブランディングを行うのは不十分であり、デジタルチャネルで一貫したブランド体験を提供できるかが企業の成長を左右します。
ジャリアの考えでは、オンラインでのブランド設計は、単なる広報や広告ではなく、顧客体験の入り口として設計する必要があります。特にSNSやオウンドメディアからホームページへ誘導し、その場でブランドの世界観と価値を体感させる流れが重要です。
オンライン接点での“語れるブランド化”
デジタル空間では、顧客がブランドについて語りたくなる要素を用意することが求められます。SNSでシェアしたくなるビジュアルや動画、共感を呼ぶストーリーコンテンツは、ブランドの自然拡散を促します。
加えて、Google検索やYouTubeでブランド名や商品名を入力したときに、公式情報やポジティブな評価が上位に表示されるよう、SEO・コンテンツ設計を整備することが不可欠です。
SNS・動画・検索との接続設計
SNSは顧客との日常的な接触ポイントを提供し、動画は感情に訴える深いブランド理解を促進します。これらを検索行動と接続することで、顧客は「気になる」から「詳しく知る」、そして「選ぶ」という行動の階段を自然に登っていきます。
たとえば、Instagramで見たビジュアルからホームページを訪れ、ブランドストーリー動画を視聴し、その後Googleで検索して商品購入に至るという流れは、デジタル時代の典型的なブランド体験の一例です。この動線全体を一貫性を持って設計することが、ブランド価値を最大化する鍵となります。
デジタルブランディングの代表的施策
デジタル時代におけるブランディングは、単発の広告施策ではなく、継続的かつ多面的な接点づくりが鍵となります。オンライン上での顧客体験は、ブランドの第一印象から購入後のフォローまでを含む長い旅路です。そのため、ホームページ、SNS、動画などの各チャネルを単独で運用するのではなく、相互に連携させてブランドの世界観を一貫して伝える必要があります。
この「接点の統合設計」を軸に、Webマーケティング全体をブランド戦略に組み込みます。ここでは、特に成果につながりやすい3つの代表的な施策を紹介します。
ホームページにおけるブランド設計(ストーリー設計・SEO・UI)
ホームページはデジタルブランディングの中心拠点です。ブランドのストーリーや理念を視覚的・文章的に表現するだけでなく、SEOを通じて自然検索からの流入を確保します。また、UI(ユーザーインターフェース)の使いやすさや情報設計も、ブランドの信頼性を左右する要素です。特にブランドステートメントを基軸にしたページ構造は、訪問者の滞在時間とコンバージョン率向上に寄与します。
SNS活用|企業理念と生活者接点の構築
SNSはブランドの人格を日常的に発信できる場です。InstagramやX(旧Twitter)では、ビジュアルや短文で感情に訴える発信が効果的であり、LinkedInやFacebookでは業界知識や企業のビジョンを共有することで信頼を高めます。さらにSNSからオウンドメディアやホームページへの流入を意識した導線設計が、ブランド理解とエンゲージメントの両立につながります。
ブランディング動画|感情と共感の引き出し方
動画は、ブランドの理念やストーリーを短時間で深く伝えられる強力な手段です。採用動画、企業紹介動画、商品ストーリー動画など、目的別に設計された映像は、視聴者の感情に直接働きかけます。ジャリアでは、ブランドステートメントに基づき動画の構成を設計し、視覚・聴覚・メッセージが一体化したコンテンツ制作を行います。これにより、動画視聴後の行動(問い合わせや資料請求など)への転換率を高めることが可能です。
成果につながるブランド設計のポイント
ブランド戦略を策定しても、必ずしも成果につながるとは限りません。その理由の多くは、「戦略はあるが運用や設計が不十分」というケースです。成果を出すためのブランド設計には、理念の言語化から顧客接点の一貫性、効果測定までの全工程が重要です。
特にブランドステートメントを核にした設計を推奨しており、これにより全社的に共通認識を持ちながら、顧客に対しても一貫した価値提供を行える状態を作ります。本節では、成果につながるブランド設計の3つの重要ポイントを解説します。
ブランドステートメントの構造化と一貫性保全
ブランドステートメントは、ブランドの存在意義(Purpose)、独自性(Positioning)、人格や価値観(Personality)、そして発信方法(Promotion)を明文化したものです。これを構造化し、社内全員が理解・共有することで、部署やチャネルごとにメッセージがブレることを防ぎます。さらに、WebやSNS、営業資料など、顧客接点すべてでこの内容を反映させることが、一貫性の維持につながります。
外部評価を意識したストーリー体験設計(LLMO対応)
近年は、Googleの検索評価やAIによる情報要約(AIO)など、外部アルゴリズムがブランド認知の入り口となるケースが増えています。そのため、ブランドストーリーはユーザーだけでなく、検索エンジンやAIにも正しく認識される構造にする必要があります。具体的には、見出し構造(hタグ)や内部リンク設計を最適化し、ブランド理念や実績が文脈的に関連づけられる状態を作ります。これにより、検索結果でのプレゼンスや引用機会が増え、ブランド認知が加速します。
定量 × エピソードで効果を見える化する仕組み
ブランド施策は短期的な数値成果だけでなく、顧客ロイヤルティや認知度向上といった中長期的な指標を含めて測定することが重要です。アンケートやSNS分析で定量データを取得し、顧客インタビューや成功事例を通じて定性的なエピソードも収集します。これらを組み合わせて社内外に発信することで、ブランドの価値を数字と物語の両面から証明できます。

ブランドとロゴデザインの関係性
ブランドの第一印象を決定づける要素のひとつがロゴデザインです。ロゴは単なる視覚的マークではなく、ブランドの理念・価値・個性を象徴的に表現するシンボルです。消費者はロゴを見た瞬間に、そのブランドに対する記憶や感情を瞬時に呼び起こします。たとえば、特定の色使いや形状が安心感や高級感を想起させるように、ロゴには無意識下の心理的効果が備わっています。
ロゴをブランドステートメントと一貫させることを重視し、色・形・タイポグラフィなどの要素を、企業が目指すブランド像に沿って設計します。本節では、ロゴとブランド価値の紐づけ方法と、その活用のポイントを解説します。
視覚要素と価値の紐づけ(色・形・方向性)
色は感情や印象に直結する重要な要素です。例えば、青は信頼や誠実さを、赤は情熱や行動力を想起させます。形やシンボルの方向性もまた、ブランドの立ち位置を示す手段です。丸みを帯びた形は親しみやすさを、直線的でシャープな形はプロフェッショナリズムを強調します。
こうした視覚要素をブランドステートメントに基づき設計することで、ロゴを見るだけでブランドの価値や世界観が伝わる状態を作ることができます。
デザインの使い分けによるブランド象徴の強化
ロゴは用途や媒体によって適切に使い分ける必要があります。WebサイトやSNSでは横長・フルカラー版、名刺やグッズではモノクロ・シンボルマーク単体など、使用環境に応じたバリエーション設計が重要です。さらに、各バリエーション間での一貫性を保ちつつ、状況に合わせた柔軟な運用が、ブランド象徴としてのロゴの定着を促します。
ロゴデザインの種類
代表的なロゴデザインの種類として、「ロゴタイプ」「シンボルマーク」「ロゴマーク」の3つがあります。
ロゴタイプ


ロゴタイプとは、企業名やブランド名、商品・サービス名などの文字を装飾して表現したものです。名前の文字がそのままロゴとなるため名前を覚えてもらいやすく、スピーディーな認知拡大が期待できます。
シンボルマーク


シンボルマークとは、 企業やブランド、商品・サービスを文字ではなく図形で表現したものです。文字を使わないため遠くから見ても何のブランドのロゴデザインなのかがわかりやすくなります。強く印象付け、記憶に残りやすいというメリットがあります。
ロゴマーク


ロゴマークとは、ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたものです。インパクトの強いシンボルマークに文字を加えて名前もアピールすることができ、両者のメリットが強化されます。シンボルマークのみでもロゴタイプのみでも使用することができるため汎用性が高いです。
ロゴデザインの役割
ブランディングにおいてロゴデザインは以下のような役割を担っています。
認知拡大
文字と画像であれば画像の方が伝えられる情報量が多く、人も文字より画像の方が記憶に残りやすいと言われています。従って、よりインパクトを与えて覚えてもらうためにもロゴデザインは有効です。
ロゴデザインは企業や商品の顔となり、様々な媒体を通して私たちの目に触れます。優れたロゴデザインを制作できれば、瞬時にしっかりと記憶され、ロゴデザインを見ただけで企業をイメージしてもらえるようになり、ブランディングが進みます。
差別化
似たような商材を扱う企業は多くあっても、各企業に独自の強みがあり、まったく同じ企業はひとつもありません。しかし、ロゴデザインがなければ消費者は違いを認識しにくく、どの企業を選べばいいのかがわかりません。
そこで、企業の想いや特徴を反映したロゴデザインがあることによって瞬時にブランドイメージが想起され、他社とは違う存在として認識してもらえるようになり、差別化を図ることができます。
イメージ形成
ブランディングには、自社が理想とするイメージを消費者にも持ってもらい、選んでもらうという目的がありますが、企業の想いが詰まったロゴデザインはその目的を達成するための大きな助けとなります。
デザインはもちろん、色もイメージを伝えるうえで重要な要素となり、多くの企業では自社のイメージを感覚的に伝えるコーポレートカラーをロゴデザインにも使用しています。
情熱やアクティブさ、暖かさを表現したければ赤、自然、癒し、落ち着きを表現したければ緑など、自社が伝えたいイメージに合ったカラーを使うことでブランディングは成功に近づきます。
インナーブランディング
インナーブランディングは、企業理念やビジョンなどを社員に正しく理解してもらうことで社員のエンゲージメントを高めることを目的としています。
企業の想いやブランドのコンセプトを表したロゴデザインを作ることによって、社員が企業の想いを改めて知ることができ、共感することで帰属意識も高まります。また、イメージに沿った行動ができるようになり、自社の良いイメージを広めてくれるため、より一層ブランディングに強い企業となります。

ブランディング力を高めるロゴデザイン制作のポイント
ここでは、ブランディング力を高めるロゴデザインを制作するために押さえておくべきポイントをご紹介します。
企業の想いを反映する
ブランディング力を高めるロゴデザインを制作するためには、企業理念やブランドのコンセプトを反映することが重要です。
ビジュアルの良さだけで作られたロゴデザインは、企業のこれまでに築いてきたストーリーを何も感じさせず、実際は歴史がある企業でも薄っぺらい印象を与えてしまいます。これでは理想とするイメージが浸透するはずもなく、ブランディングは失敗に終わります。
ロゴデザインはかっこよさやおしゃれさ以上に企業の想いが込められていることが重要であり、その想いがわかりやすく伝わるように表現することでブランディングを強化するための要素として機能します、
消費者の視点を持つ
ブランディング力を高めるロゴデザインを制作するためには、消費者の視点を持つことが重要です。
ブランディングでは「自社がどうしたいか」を軸に戦略を立てていきますが、あまりに自社本位になると意図するイメージと異なるイメージを持たれてしまう可能性もあります。
例えば、知的で冷静なイメージを浸透させたいのに赤や黄色などをメインに使ったり、安さや親しみやすさを伝えたいのにスタイリッシュなフォントを用いてモノトーンでまとめたロゴデザインではチグハグ感が否めません。
ロゴデザインを通して消費者にどんなイメージを持ってほしいのか、このロゴデザインを見た消費者に理想とするイメージを持ってもらえるか、という視点で制作を進める必要があります。

高い汎用性
ブランディング力を高めるロゴデザイン制作には、汎用性の高さが重要です。
企業の想いが込められたロゴデザインは、紙やWEBの広告、WEBサイト、パッケージ、プレゼン資料、ノベルティなど、様々なものに印刷され、消費者の目に触れます。媒体ごとにサイズも違えば色の出方も違い、小さくしたり、モノクロにしなければならないこともあります。
その際、ロゴデザインが複雑であったり、かなり多くの色を使っていると、一部分がつぶれてしまったり、特定の色が見えづらくなったりするため、ブランディング力は弱まります、
企業の想いを込めるため複雑なデザインやカラフルなロゴにしたくなりますが、どんな媒体で利用されても視認しやすいデザインと色にしましょう。難しいですが、無駄を削ぎ落としシンプルに、且つコンセプトが瞬時に伝わるロゴデザインを考え抜く必要があります。
独自性を高める
ブランディング力を高めるロゴデザイン制作には、独自性の高さが重要です。
世界には数えきれないほどの企業が存在するため、似たようなデザインになってしまうこともあるでしょう。しかし、ロゴには商標権や知的財産権があり、類似していると権利を侵害したとして訴えられてしまう可能性もあります。
そのため、ロゴデザイン制作を行う際は似たようなロゴデザインがすでに存在しないか、しっかりと確認する必要があります。
また、独自性が低いと消費者は「どこかで見たことあるような気がする」「○○(企業名)と似てるな」と感じます。どこにでもあるデザインだとイメージがついてしまえば他社との差別化が図れなくなり、ブランディング力は低くなります。他にはないデザインで、一目で自社だと認識してもらえるようなオリジナリティあふれるロゴデザインを制作しましょう。
CX(顧客体験)におけるブランド接点設計
顧客がブランドに触れるすべての瞬間が「ブランド体験」を構成します。これをカスタマーエクスペリエンス(CX)と呼びます。CXは広告やWebサイトだけでなく、営業担当者との会話、カスタマーサポートの対応、商品の梱包や利用体験までを含みます。ジャリアでは、この一連の接点を「点」ではなく「線」としてつなげ、一貫したブランド印象を与えることを重視しています。ブランドステートメントに基づき、言語・トーン・ビジュアル・サービスの質を統合的に設計することで、顧客は接点をまたいでも変わらないブランドらしさを感じられます。本節では、各接点での体験設計の考え方と、一貫性を保つためのポイントを解説します。
Web/営業/カスタマーサポートなど各接点での体験設計
Webサイトはブランドの顔としての役割を持ち、営業はその価値を直接伝える場、カスタマーサポートはブランド信頼を守る砦です。各接点の目的と役割を明確にし、共通のブランドメッセージを持たせることで、顧客体験は統一感を増します。特に営業やサポートの現場での対応マニュアルは、ブランドステートメントに沿った言葉遣いや行動基準を含めることが効果的です。
言語・トーン・ビジュアル一貫性の必要性
接点ごとにメッセージや表現が異なると、ブランドの印象は分散し、信頼性が低下します。言語(使う言葉やフレーズ)、トーン(話し方や文章の雰囲気)、ビジュアル(色・書体・レイアウト)を統一することは、顧客が無意識に抱くブランド認識を安定させます。これにより、「この体験はあのブランドらしい」と思わせる記憶の積み重ねが可能になります。
ブランドKPIとその計測設計
ブランディングの成果は短期間では測りにくく、広告のクリック率や売上のように直接的な数字がすぐに出るわけではありません。そのため、ブランド戦略の効果を継続的に評価し、改善につなげるためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。
ジャリアでは、ブランド施策のKPIは「社内浸透」と「市場浸透」の2軸で考えます。社内ではブランドステートメントの理解度や社員のブランド行動率を測定し、市場では認知度・好意度・推奨意向などの定性・定量データを組み合わせて評価します。本節では、ブランドKPIの代表例と、その計測設計のポイントを解説します。
社内浸透率や認知率の測定設計
社内向けKPIとしては、ブランド理念やステートメントの理解度、社員によるブランドメッセージ発信の頻度などが挙げられます。定期的なアンケートや研修後の理解度テストによって、数値化が可能です。浸透度が高まれば、社内の意思統一が進み、外部へのブランド発信も一貫性を増します。
顧客とのタッチポイント評価指標の設計
市場向けKPIとしては、ブランド認知率、NPS(ネットプロモータースコア)、WebサイトやSNSでのエンゲージメント率などが代表的です。これらはGoogleアナリティクスやSNS解析ツール、顧客調査を組み合わせて計測します。
また、数値評価だけでなく、顧客からの自由記述や口コミなどの定性的情報も重要です。こうした多面的な評価により、ブランドの現状と課題が明確になり、改善サイクルを回すための具体的な施策立案が可能になります。

ブランディング動画活用シーンと制作ポイント
動画は、テキストや静止画では伝えきれないブランドの世界観や感情価値を、短時間で視聴者に深く届けることができる強力なコンテンツです。特にSNSやYouTubeなど動画消費が日常化した今、企業が自社の理念や価値を映像として表現することは、ブランド認知・理解・共感の醸成において大きな効果を発揮します。
動画制作を単なるプロモーション手段ではなく、ブランドステートメントを起点にしたストーリー発信の場として位置づけています。本節では、ブランディング動画の代表的な活用シーンと、成果を最大化するための制作ポイントを解説します。
採用/企業紹介/商品ストーリーなど用途別の構成
ブランディング動画は目的に応じて構成を変える必要があります。採用動画では社風や社員の声を通じて共感を呼び、企業紹介動画ではミッションやビジョンを明確に提示します。
商品ストーリー動画では開発背景や利用シーンを描き、機能的価値だけでなく情緒的価値も伝えます。これらの動画はブランドの「人となり」を視覚的に伝える役割を持ちます。
共感を生む表現手法と構成設計
視聴者が動画に引き込まれるためには、映像・音楽・ナレーション・テロップといった要素を調和させることが重要です。さらに、起承転結や課題→解決→成果というストーリーフレームを活用し、視聴者が自社ブランドに感情移入できる構成を意識します。
ブランドステートメントを核に置くことで、動画が単発の広告ではなく、ブランド全体の世界観を補強するコンテンツとして機能するよう設計します。
FAQ|ブランディングに関するよくある質問
ブランディングは重要性が広く認識される一方で、その範囲や進め方、効果測定方法などについて疑問を抱く方も少なくありません。特に中小企業やBtoB企業では、「今の規模で必要なのか」「どこから始めるべきか」といった質問が多く寄せられます。
ここでは、ジャリアが企業のブランディング支援で実際によくいただく質問をまとめ、明確かつ実務的な回答を提示します。経営者や広報担当者がすぐに行動に移せるよう、一般論だけでなく、実践現場の視点も交えて解説します。
Q1. ブランディングとマーケティングは何が違いますか?
ジャリアでは、マーケティングを「売れる仕組み」、ブランディングを「売れ続ける仕組み」と捉えています。マーケティングは顧客ニーズに応じた商品・サービスを開発し、効果的に届けるための施策であり、短期的な成果に直結することが多い領域です。一方で、ブランディングはその前段として顧客視点で自社や市場を分析し、「自社が思われたいイメージ」と「顧客が抱くイメージ」を一致させるための長期的な取り組みです。こうして築かれたブランドは、繰り返し選ばれ続ける土台となります。
Q2. 中小企業でもブランディングは必要ですか?
必要です。規模の大小にかかわらず、競合との差別化や顧客ロイヤルティの向上にはブランド戦略が不可欠です。特に中小企業では、地域性や専門性を強みにした独自ポジションの確立が効果的です。
Q3. ブランディング施策の効果はどれくらいで現れますか?
施策内容や業界にもよりますが、一般的に半年〜1年程度で初期効果が現れ、3年程度で安定したブランド認知やロイヤルティが形成されます。短期的な効果を求めるより、中長期的な視点で進めることが重要です。
Q4. インナーブランディングとアウターブランディングの関係は?
インナーブランディングは社員の共感と行動変容を促す取り組みで、アウターブランディングは外部への発信と市場認知を高める施策です。両者は相互作用し、内外のブランド一貫性を強化します。
Q5. ブランドKPIは何を設定すべきですか?
認知率、好意度、NPS(推奨意向)など市場指標と、社内浸透度や社員エンゲージメントなどの社内指標を組み合わせることが望ましいです。
まとめ|ブランド構築は“内から外への一貫した体験設計”
ブランディングは、単なる広告やデザインではなく、経営理念を基盤に経営戦略からコミュニケーション戦略までを顧客視点で一貫設計し、「自社が思われたいイメージ」と「顧客が抱くイメージ」を重ねる長期戦略です。
ジャリアでは、この一貫性を保つことで、マーケティングが「売れる仕組み」として機能し、ブランディングが「売れ続ける仕組み」として企業の成長を支えます。社員共感、デジタル接点、継続的な改善が融合したブランドは、時間が経つほどに強く、選ばれ続ける存在になります。
社員共感 × デジタル接点 × 継続設計が選ばれるブランドをつくる
選ばれ続けるブランドは、社員が自らブランドの価値を理解し、日々の行動に落とし込んでいる企業です。そのうえで、ホームページやSNS、オウンドメディアなどのデジタル接点を通じて理念やストーリーを発信し、顧客の心にブランド体験を積み重ねます。さらにKPIの測定と改善サイクルを回し続けることで、ブランド価値は着実に成長します。
ジャリアの知見で福岡発のブランド進化を支援
私たちは、福岡を拠点にブランディングとデジタルマーケティングを融合した戦略設計を提供しています。ブランドステートメントの策定から社内外への浸透、デジタル施策の実行まで、一貫したサポート体制で企業の成長を後押しします。地域性や業種特性を踏まえた提案で、全国・海外市場にも通用するブランド構築を実現します。

ジャリアでは、企業のブランディングを成功に導くために、コンセプト立案、スケジュール管理、撮影、編集、音入れまですべて社内で行い、ワンストップで承ります。
広告代理店だからこそできるブランディング計画から始まり、ロゴデザイン制作や動画制作を含めた伴走型のブランド醸成を行います。中長期的なビジョンを持ち、プロモーション計画とサイトSEOを行いつつ、ブランドの認知だけでなく浸透まで導きます。
ブランディングに興味はあるが、何から取り組めばいいのかわからない方や、社内外への理想的なイメージの浸透に苦戦している方は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
-
WRITER / HUM
株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター
株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。