【新卒・中途別】ターゲットに響く採用メッセージの作り方
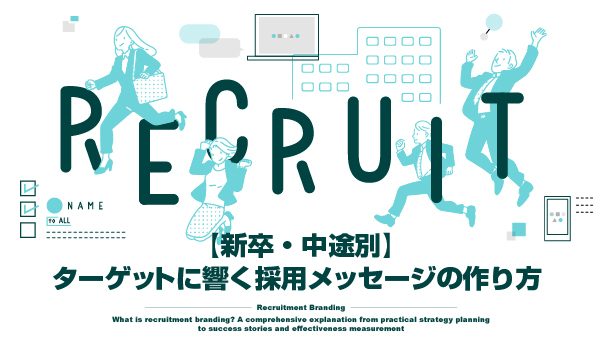
近年、採用市場における競争はますます激化しています。求人サイトやSNSを通じてあらゆる情報が瞬時に比較できる時代において、求職者は「条件」ではなく「共感」で企業を選ぶようになりました。
かつては「安定した企業」「有名なブランド」で応募が集まっていた時代もありました。しかし今の若手世代は、それだけでは動きません。彼らが見ているのは、“自分らしく働ける場所かどうか” という「感情的価値」です。
つまり、どれだけ素晴らしい福利厚生や給与制度を整えても、「この会社で働く意味が伝わらない」というだけで候補者は離れていきます。
採用メッセージとは、企業が求職者に語りかける“最初のストーリー”です。単なるキャッチコピーではなく、企業の想い・文化・ビジョンを言葉として翻訳する行為であり、採用ブランディングの“心臓部”といえます。
特に新卒・中途といったターゲットの違いによって、響く言葉のトーンや訴求軸はまったく異なります。新卒には「未来への共感」、中途には「今ここで働く理由」。同じ会社でも、伝えるべきメッセージの“設計図”が変わるのです。
しかし実際には、採用メッセージを明確に設計できている企業は多くありません。多くの採用サイトでは「挑戦できる環境」「成長できる仲間」といった抽象的な言葉が並び、どの企業の言葉も似通ってしまっています。
“どこかで見たような表現”では、もはや誰の心にも届きません。必要なのは、ターゲットの心理に基づいた「言葉の戦略」です。
本記事では、新卒・中途それぞれの心理特性をふまえ、
・響く採用メッセージを作るための設計ステップ
・媒体ごとの効果的な表現方法
・実際の成功事例と共通点
を体系的に解説していきます。「伝えたいこと」ではなく、「伝わること」をデザインする。それが、これからの時代における採用メッセージ設計の第一歩です。
|
目次
まとめ|一貫性がブランドをつくる |
採用メッセージが担う役割とは
採用活動における「メッセージ」は、単なるキャッチコピーやスローガンではありません。それは、企業と求職者をつなぐ“共感の接点”であり、言葉を通じて企業の存在意義を伝える最も重要な要素です。
情報ではなく「感情」で選ばれる時代
インターネットの普及により、企業情報はどこからでも得られるようになりました。採用サイト、口コミサイト、SNS、YouTubeなどの媒体にどの企業も「情報発信」はできる時代です。
だからこそ、求職者が最終的に企業を選ぶ基準は、“情報量の多さ”ではなく "心が動くかどうか”にあります。
採用メッセージは、その「心を動かす言葉」を設計するものです。たとえば、「挑戦できる環境」という言葉はどの企業にもありますが、“なぜ挑戦できるのか”“どんな人がそれを支えているのか”まで言語化できている企業は多くありません。言葉が具体的で、感情の背景が伝わるほど、共感が生まれます。
また、採用メッセージは“外部への発信”だけでなく、“社内の意識統一”にも作用します。
経営陣・人事・社員が「自分たちは何のために人を採るのか」という軸を共有することで、採用活動全体の一貫性が高まり、ブランドとしての信頼が生まれるのです。
採用メッセージがもたらす3つの効果
採用メッセージを明確に設計し、言語化できている企業は、次の3つの成果を得やすくなります。
① 共感を生む(心理的接点)
求職者が「この会社の考え方は自分に合う」と感じる瞬間を生み出す。これにより応募へのハードルが下がり、応募母集団の“質”が向上します。
② 信頼を築く(認知の一貫性)
採用サイト・動画・SNS・説明会など、あらゆる媒体でメッセージが統一されていると、企業に対して“誠実さ”や“透明性”を感じてもらいやすくなります。一貫したメッセージは、求職者に安心感を与える最も強い要素です。
③ 行動を促す(応募・定着への導線)
採用メッセージは、求職者を「共感」から「行動」へと導くスイッチです。「自分もここで働いてみたい」と感じさせる“ストーリー”がある企業ほど、応募率・内定承諾率・定着率が高い傾向があります。
採用メッセージは、“伝える”ためのものではなく、“人を動かす”ためのもの。その言葉に込める思想の深さが、採用活動全体の成果を左右します。

ターゲットごとの心理特性を理解する
採用メッセージを設計するうえで最も重要なのが、「誰に向けて語るのか」を明確にすることです。
同じ企業であっても、新卒と中途では“感じる魅力のポイント”がまったく異なります。つまり、メッセージの「正解」はひとつではなく、ターゲットの心理構造に合わせて言葉を設計する必要があります。
新卒採用における「共感型メッセージ」
新卒採用では、求職者がまだ社会経験を持たないため、企業理解の基準は「価値観」や「共感」にあります。給与や待遇よりも、「自分に合うかどうか」「社会の役に立てるか」「人として成長できるか」といった“感情的納得”が重視されます。
そのため、採用メッセージで伝えるべきは、「この会社でどんな未来が描けるか」という未来志向のストーリーです。
たとえば、
- 「挑戦できる環境があります」ではなく「失敗を許容し、挑戦を支える文化があります」
- 「社会貢献できる仕事です」ではなく「あなたの仕事が誰かの“ありがとう”を生む瞬間があります」
というように、感情と具体性を掛け合わせることで、言葉にリアリティが宿ります。Z世代の新卒層は「企業の本音」を見抜く力が強いため、抽象的な表現よりも“人の姿”を通じた語りが響きます。
社員のリアルな体験談や、働く姿を描く動画・ストーリー投稿などが効果的です。
また、新卒にとって採用メッセージは「会社選び」だけでなく、「社会人になる第一歩の羅針盤」にもなります。そのため、言葉のトーンはポジティブかつ希望を感じさせるものであることが重要です。
中途採用における「即戦力訴求」
一方、中途採用では、求職者の関心は「転職後の再現性」と「自己実現」にあります。
すでに社会経験を持つ分、企業の理念よりも「自分のスキルが活かせるか」「裁量を持って働けるか」といった現実的な期待値で企業を見ています。
中途向けメッセージで重要なのは、「どんな課題に挑み、どんな成果を出せる環境か」を明確に示すこと。
たとえば、
- 「新しいことに挑戦できる職場」ではなく「事業フェーズが変化する今、あなたの経験が必要です」
- 「風通しの良い組織」ではなく「役職に関係なく、意見が事業に反映される文化があります」
といったように、“自分が貢献できる具体的な場面”をイメージさせる言葉が効果的です。
さらに、中途層における離職理由の多くは「ギャップ」です。「思っていた仕事と違った」「文化が合わなかった」というミスマッチを防ぐためにも、採用メッセージでは“飾らないリアル”を伝えることが信頼につながります。
理念やカルチャーを美化するのではなく、「現状の課題」や「これからの挑戦」も含めてオープンに伝えることで、「ここなら本音で働けそう」という安心感を醸成できます。
新卒と中途の“動機構造の違い”とは?
|
観点 |
新卒採用 |
中途採用 |
|
重視する要素 |
共感・成長・社会貢献 |
即戦力・裁量・再現性 |
|
メッセージの軸 |
「どんな未来を描けるか」 |
「どんな課題を解決できるか」 |
|
言葉のトーン |
希望・ストーリー性・情緒的 |
論理・具体・成果志向 |
|
伝える手段 |
動画・ストーリー・SNS |
事例・社員インタビュー・数字・実績 |
両者に共通するのは、「企業の理念や文化を“自分ごと化”できるかどうか」。新卒は“未来への期待”、中途は“現実への納得”で動きます。この心理の違いを踏まえ、メッセージの言葉遣い・トーン・構成を調整することが、ターゲットに刺さる採用コミュニケーションの第一歩です。

メッセージ設計のステップ
採用メッセージを「思いつき」ではなく「戦略」として設計するためには、明確なプロセスを踏むことが欠かせません。ここでは、採用メッセージを構築するための4つのステップを紹介します。
① ペルソナの深掘り
まず最初に行うべきは、“誰に向けて言葉を届けるのか”を明確にすることです。ここでいう「ペルソナ」とは、単なる年齢や経歴などの属性情報ではなく、求職者の価値観・行動・心理状態を含めた人物像を指します。
ペルソナ設計の際は、次のような問いを深掘りしていくと効果的です。
- どんな働き方を理想としているか?
- どんな企業に魅力を感じるか?
- 何を不安に感じているか?
- どんな言葉に心が動くか?
たとえば、新卒の場合は「社会人としての成長」や「自分らしさを活かせる環境」を重視しがち。中途の場合は「成果に対する評価」「柔軟な働き方」「経営者との距離感」といったリアルな要素が関心軸になります。
このように、ペルソナを“数値”ではなく“物語”として描くことがポイントです。「25歳の大学卒業予定者」ではなく、「社会に出て自分の力を試したいけれど、何が向いているかまだ迷っている学生」。このレベルまで解像度を上げることで、自然と響く言葉のトーンが見えてきます。
② EVP(従業員価値提案)の言語化
EVP(Employee Value Proposition)とは、「あなたの会社で働く価値」を明確に言語化したメッセージです。つまり、「なぜあなたの会社で働くべきなのか?」をひとことで伝える“ブランドの核”です。
EVPを設計する際は、以下の3つの視点をバランス良く整理することが重要です。
- 企業が伝えたい価値(理念・ビジョン・カルチャー)
- 社員が感じている価値(やりがい・働きやすさ・仲間との関係)
- 求職者が求める価値(成長・挑戦・安定・貢献など)
この3つの重なる部分が、あなたの企業にしかない“働く理由”になります。たとえば「失敗を許容し、挑戦を称賛する文化」や「社員の声から制度が生まれる組織」など、単なる理念ではなく、日常の行動や文化に根ざした言葉で表現することが鍵です。
また、EVPは「企業スローガン」と混同されがちですが、目的は異なります。スローガンが“外向けの旗印”であるのに対し、EVPは“内外に一貫して通じる働く理由”。採用サイトや動画、SNSなど、すべての発信の基盤となるメッセージです。
③ トーン&マナーの統一
どんなに素晴らしいメッセージを作っても、媒体ごとにトーンがバラバラではブランドは伝わりません。採用ブランディングでは、「何を言うか」と同じくらい「どう言うか」が重要です。
たとえば、次のような点を整理しておくと、全媒体で統一感が保たれます。
- 言葉のテンション(フォーマル/カジュアル)
- 表現の文体(“〜します”/“〜です”など)
- デザイントーン(色・フォント・写真の明るさ)
- 感情の方向性(情熱的/誠実/温かい/挑戦的)
これらをガイドライン化することで、複数の担当者や外部パートナーが関わる場合でも「同じ温度」で発信が可能になります。
特にZ世代は“トーンのズレ”に敏感です。SNSではカジュアルなのに、採用サイトでは堅苦しいというような不一致は信頼を損ねる要因になります。どのチャネルでも「一貫した人格を感じる発信」であることが、採用メッセージの完成度を高めます。
④ 社内を巻き込む共通認識
採用メッセージは、人事部だけが作るものではありません。現場社員や経営層を巻き込み、「自分たちの言葉で語る」文化を育てることが重要です。
たとえば、以下のようなアプローチが効果的です。
- メッセージ設計段階で社員インタビューを実施
- 経営層に理念や今後の方向性をヒアリング
- 社内ワークショップで「自社の魅力」や「働く価値」を言語化
このプロセスを経ることで、単なる“コピーライティング”ではなく、“組織全体が共感できるメッセージ”が完成します。
また、社内が採用メッセージを共有・共感している企業ほど、発信にブレが生じません。社員が自らSNSで発信したり、説明会で一貫した言葉を使ったりと、「言葉が社内に浸透している状態」こそが、採用ブランディングの理想形です。

メッセージを伝えるチャネル別表現例
採用メッセージは、どれだけ優れた内容であっても「伝わり方」で印象が大きく変わります。採用サイト・動画・SNS・求人媒体など、それぞれのチャネルが持つ特性を理解し、表現方法を最適化することが重要です。ここでは、媒体別にメッセージをどう届けるべきかを解説します。
採用サイトでの表現
採用サイトは、企業と求職者の“最初の出会い”を作る場所です。ここで重要なのは、単なる情報掲載ではなく、「この会社で働く自分」をリアルに想像させる構成です。
効果的な採用サイト設計のポイントは次のとおりです。
- ファーストビューで企業の世界観を一目で伝える
- メインコピーで「理念 × 人 × 文化」を簡潔に言語化する
- 社員インタビューで“リアルな声”を可視化する
- 会社のミッション・カルチャーをストーリー形式で紹介する
- ビジュアルには“人の表情”を中心に据える
特に、メインコピーの設計は採用メッセージの核になります。「何をする会社か」ではなく、「なぜこの仕事をしているのか」という“存在理由”を示す一文を中心に据えると、印象に残るサイトになります。
また、採用サイトはSEOやSNS流入の基盤でもあるため、単なるデザイン性ではなく「読みやすさ」「導線の明確さ」も忘れてはいけません。
採用動画での表現
採用動画は、言葉では伝わらない「空気」「温度」「人の魅力」を伝える最も強力なチャネルです。Z世代を中心に、動画は採用活動の主要な情報源となっています。
構成の基本は以下の3ステップが効果的です。
- 冒頭:共感を引き出す導入
- 中盤:リアルな働く姿
- 結末:未来を感じさせるメッセージ
また、1〜2分の短尺動画を複数本制作し、SNSや説明会など複数の場面で再利用できる形にしておくと費用対効果も高まります。
ポイントは「演出しすぎないこと」。リアルな会話・オフショット・日常の風景など、編集されすぎていない“人間味のある映像”が、最も共感を呼びます。
SNSでの表現(短文訴求・ビジュアルメッセージ)
SNSは「企業の日常や温度感」を伝える場所です。採用サイトが“公式の顔”なら、SNSは“素の顔”。求職者は、投稿の中から企業の人格を感じ取っています。
プラットフォーム別の特徴を踏まえ、最適化することが重要です。
|
プラットフォーム |
特徴 |
向いている発信内容 |
|
|
視覚的世界観の統一が鍵 |
社員紹介、カルチャー投稿、リール動画 |
|
TikTok |
スピード感とリアルさ |
社員の1日密着、職場の雰囲気紹介 |
|
X(旧Twitter) |
拡散力と時事性 |
募集告知、採用イベント情報、経営者の想い |
SNSでは“語りすぎない余白”が大切です。「共感を押しつける」のではなく、「自然と知りたくなる」トーンで発信することが、ファンを生む秘訣です。
また、投稿のトーンは一貫して“対話的”であることが理想です。コメントへの返信や社員同士のやり取りが見えることで、外部の人にも“あたたかい企業文化”が伝わります。
求人媒体での表現(数値・実績・文化訴求のバランス)
求人媒体は、求職者が最も“比較”する場所です。ここでは、情緒的なメッセージだけでなく、定量的な情報とのバランスが求められます。
たとえば、
- 「離職率○%」や「平均勤続年数○年」など、数字で信頼を示す
- 「チーム構成」や「キャリアパス」を図解で説明する
- 「この職種のやりがい・難しさ」を両面で表現する
というように、応募前に“ギャップを減らす情報”を盛り込むことで、定着率の高い採用につながります。
また、求人媒体でのメッセージは「他社比較」に晒されるため、「理念 × 文化 × 成果」の3軸で差別化することが有効です。「何をしている会社か」よりも「なぜその事業をやっているのか」を語れる企業ほど、印象に残ります。

まとめ|一貫性がブランドをつくる
採用メッセージは、単なる言葉づくりではなく、企業の価値そのものを“見える化”する経営活動です。どれほど優れた制度や待遇があっても、「何を大切にし、なぜその環境をつくっているのか」が伝わらなければ、共感は生まれません。
本記事を通して見えてきたのは、採用メッセージの設計において最も大切なのは「一貫性」であるということです。まず、メッセージは常に“誰に語りかけるのか”を意識することが出発点になります。新卒には未来への共感を、中途には今ここで働く理由を届けましょう。相手の価値観に寄り添った言葉ほど、真に心に響きます。
そして、軸となるのがEVP(従業員価値提案)です。自社で働く意味をひとことで言語化し、それをすべての発信チャネルで同じトーンで伝えること。企業の理念や文化を貫くメッセージが定まれば、どんな媒体でもブレないブランドとして印象づけられます。
さらに重要なのは、言葉と行動を一致させることです。採用サイトやSNSで語る内容が、社員の日常や社内文化と乖離していては、信頼は得られません。発信と実態が重なる企業こそ、言葉に説得力が生まれ、外部からも“本物のブランド”として認識されます。
採用メッセージの本質は、“言葉で採用する”ことではなく、“言葉で信頼を築く”ことにあります。その信頼は、応募者だけでなく、社員や顧客、そして社会全体に波及していきます。採用ブランディングとは、マーケティングではなく「信頼づくり」です。
一貫した言葉の力で、人と組織を結び、共感によって選ばれるブランドへ。それこそが、これからの時代に求められる採用メッセージ設計の到達点です。
▶︎関連記事
【完全版】採用ブランディングとは?実践戦略の立案から成功事例・効果測定まで徹底解説

| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。