ChatGPT×AIツール連携で実現する業務自動化|Zapier・Make・Google Workspace活用術
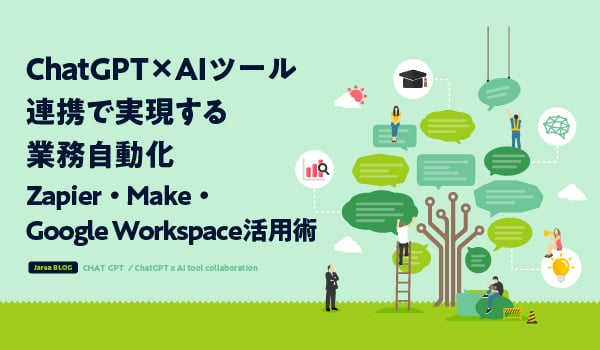
ChatGPTの活用が進む中で、「単体で使うのは限界がある」「実業務にどう組み込むべきか」という声も多く聞かれるようになってきました。実は、ChatGPTの真価が発揮されるのは他のAIツールやノーコードツールとの連携によって業務フローに“溶け込んだとき”です。
ZapierやMakeといった自動化ツール、Google Workspaceとの統合によって、ChatGPTは単なるテキスト生成AIから“業務を一気通貫で支える頭脳”へと進化します。本記事では、ビジネスの現場で今すぐ応用できる連携活用術とその設定例を解説します。
ChatGPT単体ではできないことと、その限界
ChatGPTは優れた文章生成・要約・翻訳などのスキルを持つ一方で、「情報の保存」「実行」「外部サービスとの連携」など、タスク実行能力に限界があります。たとえば、「Slackに送って」「Googleスプレッドシートに書き込んで」と指示しても、それを“実行”する力は持っていません。
この限界を乗り越えるのが、ZapierやMakeのような連携ツールの存在です。こうした外部ツールとつなぐことで、ChatGPTは実務のワークフローに深く入り込み、より実践的な業務自動化を実現できます。
なぜ連携が必要なのか? 業務現場では
「考えるだけではなく動かす」ことが求められます。ChatGPTはアイデアを出すのが得意ですが、アクションを伴う一連の処理には限界があります。たとえば「日報を集めて要約し、毎朝8時にSlackへ送信」という流れを実現するには、他のツールとの連携が不可欠です。連携によってChatGPTは、静的なツールから“動的な業務エージェント”へと進化します。
連携により実現できる具体的なシーン
Googleフォームから集めた顧客アンケートを要約し、営業チームへメール送信 ・SNSの投稿内容をChatGPTが生成し、Buffer経由で自動スケジュール投稿 ・顧客からの問い合わせ内容を自動で分類・要約し、Notionに整理保存 これらはすべて、ChatGPTと連携ツールの組み合わせで実現可能な業務自動化例です。
ChatGPTとZapierの連携でできること
Zapierは「あるトリガーが発生したら、このアクションを起こす」というルールを簡単に作成できるノーコード自動化ツールです。ChatGPTと連携させることで、情報生成と実行のギャップを埋めることが可能になります。
ZapierでのChatGPT連携例
Zapierは、ノーコードで複数のWebアプリケーションを連携できる自動化ツールです。ChatGPTと連携することで、例えば以下のような自動処理が可能になります:
-
フォーム送信内容をChatGPTで要約し、Slackに通知
-
新しいGoogleカレンダー予定をもとに自動でメール文面を作成し、Gmail下書きに保存
-
Trelloのカード作成時に内容をChatGPTで要約して説明欄に反映
Zapierの豊富な対応アプリとの連携によって、「問い合わせ対応の半自動化」や「顧客アンケート結果の自動要約」など、実務に直結したさまざまな業務改善が実現できます。
導入時のポイントと注意点
Zapierは操作が比較的シンプルですが、ChatGPTとの連携には以下の点に注意が必要です:
-
OpenAIアカウントからAPIキーを取得し、Zapier側に連携設定する必要がある
-
ChatGPT APIの入力文字数制限やトークン管理を理解しておくこと
-
テスト実行時と本番で挙動が異なるケースがあるため、しっかりとシミュレーションを行うこと
また、Zapierの無料プランでは一部の連携機能に制限があるため、ChatGPTとの本格連携には有料プランの検討も視野に入れておくとよいでしょう。
ZapierでのChatGPT実装ステップと設定ポイント
ZapierとChatGPTを連携させるには、以下の手順を踏みます:
-
Zapierアカウントを作成し、Zap(自動処理フロー)を新規作成。
-
トリガーアプリを選択(例:Googleフォーム、Notionなど)し、連携イベントを設定。
-
Action(アクション)として「Webhooks by Zapier」を選択し、「Custom Request」でChatGPT APIを呼び出す設定を行います。
-
OpenAI APIのエンドポイントとヘッダー、リクエストボディを構成。ここで「model」「messages」「temperature」などのパラメータを指定します。
-
API応答の取得と整形を行い、次のアクション(Slack通知、メール送信など)に渡します。
Zapier上でChatGPTを直接操作するには、Webhookの利用が必要になりますが、テンプレートやAIプラグインを使えばより簡易に構築することも可能です。プロンプト設計と入力内容のマッピング次第で、非常に柔軟な業務フローが構築できます。
Zapierテンプレートを活用したChatGPT連携の簡易構築
Zapierには、ChatGPTやOpenAIとの連携に特化したテンプレート(Zap)が多数公開されており、初心者でも数クリックで連携フローを構築できます。たとえば「Googleフォームに回答があったら要約を生成してGmailで送信」といったZapは、あらかじめ設定済みのステップが用意されており、カスタマイズも容易です。
このテンプレート活用により、エンジニアでなくても自社業務に合わせたChatGPTワークフローの設計が可能になり、導入障壁を大幅に下げることができます。まずはテンプレートベースで始め、徐々にWebhookやスクリプトを取り入れて応用範囲を広げるのが効果的なアプローチです。
ChatGPT×Make(Integromat)で複雑な自動化も可能に
Make(旧Integromat)はZapierに比べて、より柔軟で複雑な分岐やデータ処理ができる連携ツールです。特に大量のデータ処理やルーティングを要する業務では、Makeとの連携が力を発揮します。
Make活用例:業務効率化の実践
Make(旧Integromat)は、複雑なワークフローや多段階の処理が必要な業務に対して強力な自動化ソリューションを提供します。たとえば、フォーム送信→スプレッドシートへの記録→ChatGPTによる要約→Slack通知、という一連の流れをワンクリックで実現可能です。フィルタ機能や条件分岐(if/else)を用いて、送信内容に応じて処理ルートを分けるといった柔軟な設計も可能です。
セミナー申し込みデータをMakeで受け取り、自動で参加者リストを生成し、ChatGPTが個別フォローメールを作成→Gmailドラフト保存→営業担当に通知、といった一連の業務自動化を実装。結果として、運用負荷の大幅削減と対応速度の向上を同時に行うこともできます。
ChatGPT×Makeの導入ハードルと対策
Makeは直感的なUIを備えているものの、多段階の自動処理やWebhookなどを活用する場合には、ある程度の技術的理解が必要です。特にChatGPT APIの活用時には、JSON形式でのデータ構造やAPIキーの取得、HTTPモジュールの扱いに関する基本知識が求められます。
導入ハードルを下げるためには、まずシンプルなユースケース(例:Googleフォーム→メール送信)から始め、慣れてきた段階でChatGPTとの連携を加える方法が有効です。また、Makeにはテンプレートも豊富に用意されており、「OpenAI」「Google Workspace」「Slack」「Notion」など主要サービスとの接続済みレシピから着手することで、構築の負担を軽減できます。
Make(Integromat)でのChatGPT連携の基本ステップ
ChatGPTとMakeを連携する際の基本的なフローは以下の通りです:
-
OpenAIのAPIキー取得:OpenAIのアカウント設定からAPIキーを取得し、MakeのHTTPモジュールに登録します。
-
シナリオの作成:Makeのシナリオエディタ上で、新しいフローを作成。トリガー(例:フォーム受信)を設定します。
-
HTTPモジュールの設定:OpenAIのエンドポイント(例:https://api.openai.com/v1/chat/completions)を指定し、必要なヘッダー(Authorization、Content-Type)とボディ(モデル、メッセージなど)を設定します。
-
出力データの整形:ChatGPTからの応答をテキスト化し、後続処理(メール化・記録・通知など)に受け渡します。
-
テストと有効化:実際のデータを用いてシナリオをテストし、問題がなければ本番環境で運用開始。
これにより、たとえば「毎朝指定のスプレッドシートの内容を要約してSlack通知」といった自動化も数十分で構築可能です。ノーコードでありながら、エンジニアレベルの処理が構築できるのがMakeの魅力です。
Google WorkspaceとChatGPTの組み合わせ活用
Googleドキュメントやスプレッドシート、Gmailなど、日常業務で使うGoogle WorkspaceとChatGPTを組み合わせることで、業務効率化の幅が一段と広がります。
Googleスプレッドシートでの活用例
ChatGPTとGoogleスプレッドシートの組み合わせは、特にマーケティングや営業部門において、レポート作成やデータ整理の効率化に大きく貢献します。たとえば、Google Apps Scriptを使ってChatGPT APIと連携すれば、シート内のキーワードやメモを元に自動で説明文を生成したり、商品情報からセールスコピーを作ったりすることが可能です。また、CSVデータをインポートした後にChatGPTで内容を要約・分類・トレンド分析するといった使い方も有効です。
さらに、定期的なレポート作成業務においては、スプレッドシートで収集・整理されたデータをChatGPTに渡して要約を生成し、メールやドキュメントとして出力するところまでを自動化することもできます。マーケティングKPIの定点観測や週次のレポート提出などにおいて、人的コストを削減しつつ質を担保する運用が実現できます。
Gmail×ChatGPTでの文面作成効率化
ChatGPTとGoogleスプレッドシートの組み合わせは、特にマーケティングや営業部門において、レポート作成やデータ整理の効率化に大きく貢献します。たとえば、Google Apps Scriptを使ってChatGPT APIと連携すれば、シート内のキーワードやメモを元に自動で説明文を生成したり、商品情報からセールスコピーを作ったりすることが可能です。また、CSVデータをインポートした後にChatGPTで内容を要約・分類・トレンド分析するといった使い方も有効です。
さらに、定期的なレポート作成業務においては、スプレッドシートで収集・整理されたデータをChatGPTに渡して要約を生成し、メールやドキュメントとして出力するところまでを自動化することもできます。マーケティングKPIの定点観測や週次のレポート提出などにおいて、人的コストを削減しつつ質を担保する運用が実現できます。
Googleドキュメントとの連携で自動レポート作成
GmailとChatGPTの連携では、営業メールや問い合わせ対応メールの自動化に高い効果を発揮します。ZapierやMakeを使えば、新規メール受信や特定の件名に応じてChatGPTが自動で返信文の草案を生成し、それをGmail下書きとして保存することができます。これにより、定型文やテンプレートに依存しない、柔軟でパーソナライズされた返信対応がスピーディに行えます。
また、Googleカレンダーと組み合わせることで、日程調整メールを自動生成したり、ミーティング後のフォローアップメールをChatGPTが生成する、といった活用も現実的です。Gmail APIとChatGPT APIを統合することで、煩雑なやり取りの自動化と、ヒューマンタッチの両立を実現できるのが強みです。
例えばジャリアの社内では、SNSキャンペーンに関する問い合わせ対応の初動をChatGPT×Gmailで自動化しており、担当者は生成されたドラフトを確認・修正するだけで運用できる体制を整えています。これにより返信スピードと対応品質の両立が可能となり、少人数のチームでも業務負担の軽減につながっています。
Googleカレンダー×ChatGPTでリマインドと日程調整を自動化
Googleカレンダーとの連携では、予定の登録内容やゲスト情報をトリガーとしてChatGPTがメールやメッセージ文面を自動生成できます。たとえば、予定作成時に「前日リマインドメール」を作成し、SlackやGmailで送信する、あるいは会議後に「サンキューメールと議事要約」を自動で用意するといった活用が可能です。
さらに、会議のテーマや参加者によって文面のトーンを変えたり、参加できなかったメンバー向けに要点をChatGPTが要約して送付するなどの応用も効きます。これにより、社内外のコミュニケーション効率を高めながら、対応漏れのリスクも最小化できます。
まとめ|ChatGPTは連携によって“動けるAI”になる
ChatGPTは、連携によって初めて“現場で動けるAI”になります。ZapierやMakeといったツールを使うことで、ChatGPTは知的支援ツールから“実務を支える自動化パートナー”へと進化します。ツール間連携による業務自動化は、人的工数の削減だけでなく、情報の見える化・整理・再利用の質をも向上させるものです。
まずは「1業務1連携」から始めよう
連携を始める際には、いきなり全業務を自動化しようとせず、まずは「1業務1連携」を目指すのが現実的です。たとえば「日報作成」「SNS投稿」「メール返信案作成」など、負担が大きいルーチンワークから手をつけると効果を実感しやすくなります。
業務にフィットした“つながり方”を設計する
重要なのは、ChatGPTに何をさせたいか、そしてどのデータとどう結びつけたいかという“設計力”です。業務プロセス全体を見直しながら、最適なつながり方を考えることで、AIとツールのシナジーが生まれます。
●ChatGPTとは?メリットや活用事例、今後の影響について解説

| WRITER / HUM 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |