福岡で採用に強い企業になるためのブランディング活用の実践法
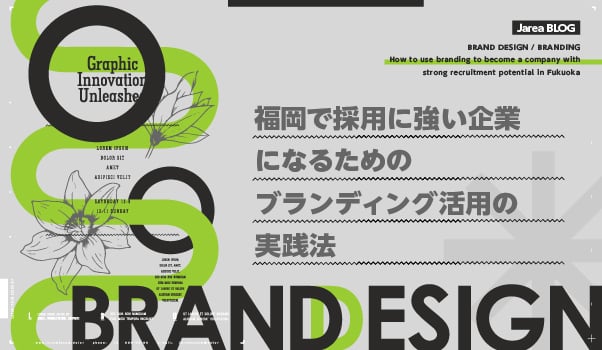
少子高齢化が進み、企業の採用活動はますます困難を極めています。とくに福岡のような地域密着型の企業が多い都市においては、“働く場所としての魅力”をいかに明確に打ち出すかが採用成功の鍵を握ります。その手段の一つとして近年注目されているのが「採用ブランディング」です。
採用ブランディングとは、単に求人情報を発信するだけでなく、「どんな理念を持ち、どんな人材を求め、どんな未来を描いているのか」という企業の価値を、戦略的に社内外へ伝える取り組みです。そしてこの価値を“可視化”するのが、デザインの力なのです。
本記事では、福岡の企業が“選ばれる会社”になるために必要な採用ブランディングと、その伝達力を高めるためのデザイン戦略について、実践的な視点で解説していきます。
採用を取り巻く環境は、かつてとは大きく様変わりしました。求人を出せば応募が殺到する時代は終わり、今では企業が“選ばれる側”となる時代。特に福岡のように、地域に根差した企業が多く、若年層の流出が課題となる地域では、他県や都市部との競争も視野に入れた採用ブランディングの視点が欠かせません。
求職者が企業を選ぶ際、給与や勤務条件といったスペック面だけでなく、「この会社の価値観に共感できるか」「この環境で自分が成長できるか」といった“感情的な納得”が重要視される傾向にあります。そのため、自社の魅力や想いをきちんと伝える設計がなされていなければ、選ばれることは難しいのです。
この章では、採用が“売り手市場”となった背景と、そこにおける企業ブランディングの必要性について詳しく紐解いていきます。

採用が“売り手市場”となった時代背景
現在の採用市場は、慢性的な人材不足と学生・求職者の価値観の多様化によって、大きな変革期を迎えています。厚生労働省の調査によると、有効求人倍率は年々高い水準を維持しており、特に地方都市では人材の取り合いが常態化しています。
さらに、Z世代を中心とした若年層は、安定性よりも「働きがい」や「社会的意義」を重視する傾向が強く、単なる条件提示だけでは響かないケースが増えています。そのため、企業は“何をしているか”以上に、“どんな想いで取り組んでいるか”を発信しなければ、候補者の共感を得ることができません。
このような背景から、「企業としての存在理由」や「求める人物像」を明確にし、求職者に自社の魅力を伝える手段としてのブランディングが重視されるようになったのです。
企業の魅力は“設計して伝える”時代へ
採用活動においては、「いい人材が来てくれるといいな」という待ちの姿勢ではなく、戦略的に“設計する”姿勢が求められます。これまでのように、求人媒体に情報を出すだけでは、十分な成果は得られません。
採用ブランディングでは、企業の理念や文化、働き方、求める人物像などを明文化し、それらを求職者目線で再構成して伝えることが必要です。つまり、ただ企業側の主張を一方的に押し出すのではなく、「この会社なら自分も共に成長できそうだ」と思ってもらえるような“語り口”が重要となります。
この考え方は、Webサイトやパンフレット、SNS、説明会資料など、あらゆる採用ツールに反映されるべきものです。一貫した言葉選び、ビジュアル設計、ストーリー構成によって、企業の魅力ははじめて“伝わる”ものへと昇華されていくのです。
採用ブランディングとデザインの相乗効果
採用ブランディングを構成する重要な要素のひとつが「デザイン」です。理念や文化などの“目に見えない価値”を、視覚的に表現することが、求職者にとっての“共感の入口”になります。
たとえば、採用ページのファーストビューにおいて、企業理念を視覚的に象徴するような写真やコピーが設置されていれば、ユーザーは直感的に企業の世界観を理解し、読み進めようという意欲を抱きやすくなります。これは単なる装飾ではなく、ブランドの“翻訳”に近い行為です。
この章では、採用ブランディングにおけるデザインの重要性を、より具体的な観点から見ていきます。

理念や文化を視覚化するという戦略
企業の理念や文化は、言葉にすればするほど抽象的になりがちです。だからこそ、それらを“デザインで視覚化”することには大きな意味があります。たとえば、「挑戦」「柔軟性」「信頼」などの価値観は、カラーやレイアウト、写真、アイコンなどのデザイン要素によって、直感的に伝えることが可能です。
ここで重要なのは、見た目を整えることが目的ではないという点です。視覚的な要素が、企業の価値や雰囲気を的確に伝える“ツール”として機能しているかどうかが問われます。言い換えれば、企業文化を抽象から具体へと翻訳する装置こそが、ブランドデザインなのです。
“働くイメージ”をデザインで伝える
求職者にとって、企業選びの重要な基準となるのが「そこで働く自分を想像できるかどうか」です。この“働くイメージ”を形成するのに効果的なのが、写真や動画といった視覚コンテンツです。
たとえば、オフィス風景や社員インタビュー、仕事の流れを紹介するビジュアルは、職場の雰囲気や価値観をストレートに伝えてくれます。こうした表現を丁寧に設計することで、求職者は安心感や親近感を得られ、「この会社に応募してみたい」と思う確率が高まるのです。
また、Webサイトの色使いやフォント選びなども、“温かみ”“革新性”“誠実さ”といったブランドイメージを形成する大切な要素です。これらをトータルで設計することで、単なる情報発信ではなく、“感情に響く採用体験”を届けることができるようになります。
福岡の求職者に響くコミュニケーション設計
福岡は大都市でありながらも、地域コミュニティとのつながりが強く、求職者の企業選びにも独自の傾向があります。とくに若年層を中心に、「地元で働きたい」「地域と関わりながらキャリアを築きたい」というニーズが高まっている一方で、企業の側がその魅力をうまく言語化・視覚化できていないケースも少なくありません。
採用ブランディングにおいては、この“地域性”をいかに戦略に落とし込むかが成否を分けるポイントになります。この章では、福岡という地域の特性を活かしたメッセージ設計と、求職者との接点づくりについて解説していきます。

地域性を活かしたメッセージづくり
福岡で採用活動を展開するにあたり、地域性を無視したメッセージは響きにくい傾向があります。たとえば、地域貢献性の高い事業内容や、地元のお客様との関係性を強調することで、「ここで働くことが地域に根ざすことになる」というポジティブなイメージを持たせることができます。
また、言葉選びにおいても、都市部特有の硬質なトーンより、親しみやすく温かみのある表現が好まれる傾向にあります。ローカルメディアや地域イベントとの連携を通じて、企業の“顔が見える”ような情報発信を行うことで、求職者との距離感を縮めることが可能です。
このような地域に根差したブランディングは、単に採用に有利というだけでなく、長期的な従業員定着率の向上にもつながります。自分が暮らす地域に貢献できるという実感は、働くモチベーションの源泉となるからです。
就職希望者の心理と情報接点を理解する
求職者は、求人票や募集要項だけで企業を判断しているわけではありません。SNS、口コミサイト、企業の採用サイト、YouTube、説明会資料など、さまざまな情報に触れながら「この会社は信頼できるか」「自分に合っていそうか」と評価しています。
そのため、採用ブランディングでは、こうした多様な“情報接点”を意識した設計が必要です。たとえば、採用サイトに掲載する社員インタビューは、職種別・キャリアステージ別に設計することで、より幅広い共感を得ることができます。また、SNSでは日々の職場風景やイベントの様子をラフに発信することで、“飾らない会社”としての魅力を伝えることも可能です。
重要なのは、どのチャネルでも“同じトーンと価値観”が伝わること。メッセージに一貫性がないと、求職者は違和感を覚え、結果的に応募意欲が低下するリスクがあります。コミュニケーション設計は、ただ拡散するのではなく、意図をもって“信頼を積み上げる導線”として捉えることが求められます。
採用におけるトーン&マナーの重要性
採用におけるトーン&マナーは、企業の人格を形づくる非常に重要な要素です。トーンは“話し方や雰囲気”を、マナーは“ふるまいや対応の一貫性”を示し、これらが整っているかどうかで、求職者が抱く企業イメージは大きく変わってきます。
求職者は企業のWebサイトや求人票だけでなく、メールの文面、面接時の雰囲気、SNSでの発信など、あらゆる場面で“この会社は信頼できるか”を判断しています。だからこそ、トーン&マナーの設計には細心の注意が必要なのです。
このセクションでは、採用におけるトーン&マナーの設計とその実践ポイントについて、具体例を交えて解説していきます。

採用ブランディングにおける“語り口”の統一
採用ブランディングでは、求職者が企業に触れるあらゆるタッチポイントで“語り口”が統一されていることが重要です。Webサイトでの語調とSNS投稿、説明会での話し方にギャップがあると、受け手は戸惑いを覚え、「本当の姿が見えない企業」として不信感を抱いてしまう可能性があります。
たとえば、「まじめで誠実な社風」を打ち出している企業が、SNSで軽薄な表現を多用していれば、その一貫性のなさがブランド毀損につながることも。逆に、“らしい語り口”を全チャネルで統一できれば、企業としての個性が伝わりやすく、記憶にも残りやすくなります。
トーン設計では、「フレンドリーだけど丁寧に」「誠実でありながらもカジュアルに」など、複数の要素を組み合わせながら、自社ならではの“バランス感”を明文化していくことがポイントです。こうした方針が定まっていれば、担当者が変わっても一貫した採用コミュニケーションが維持できます。
応募〜選考過程における“体験品質”の統一
採用ブランディングは、情報発信だけで完結するものではありません。実際に求職者が応募し、選考を受けるプロセスそのものが“ブランド体験”として捉えられるべきです。
たとえば、エントリーフォームのデザインが雑だったり、面接の案内メールがぶっきらぼうだったりすると、それだけで企業に対する印象は大きく下がってしまいます。逆に、どの接点でも丁寧かつ親しみやすい対応がなされていれば、「ここで働きたい」という気持ちが自然と醸成されます。
つまり、トーン&マナーは採用コミュニケーション全体において“接客品質”を担う存在なのです。採用担当者だけでなく、現場で関わる社員や経営層までもが一貫した態度で対応することで、求職者にとっての信頼は確固たるものになります。
トーン&マナーの統一は、単なる“印象操作”ではなく、“企業文化そのものの体現”といえるでしょう。
まとめ|“共感される会社”は採用でも選ばれる
これからの採用市場において、企業が選ばれる存在であり続けるためには、単に給与や待遇だけではなく、「どんな価値観を持ち、どんな姿勢で人と向き合っているのか」をいかに誠実に伝えられるかが問われています。
採用ブランディングは、その“企業らしさ”を設計し、言語とデザインの両面から共感されるメッセージとして届けるプロセスです。そして、そのプロセスにおいて一貫したトーン&マナーを保つことが、求職者の心に届くブランド体験を生み出します。
とくに福岡という土地で働きたいと願う人々にとって、地域とのつながりや企業の文化は大きな決め手になります。企業が自らの理念を大切にし、それを丁寧に“見える化”しながら伝えていくことは、未来の仲間を惹きつける最大の戦略です。
“共感される会社”は、採用でも選ばれ、組織の未来を支える人材との出会いを生み出します。ブランドとしての強さと温度を併せ持った採用戦略の構築が、これからの企業にとって欠かせない時代となっています。
ブランドデザインの基礎となる戦略部分から構築のお手伝いさせていただきます。

| WRITER / ANNO 株式会社ジャリア福岡本社 第3営業部 ブランディングデザインチーム 株式会社ジャリア福岡本社 第3営業部 ブランディングデザインチームは、ジャリアの中でもブランド構築などブランディングに特化したチームです。企業のブランドはもちろん、採用関連も含め、ブランディングを軸に動画やWebサイト設計、パンフレットなど様々なツールの制作、広告代理店だからできる設計するだけで終わらない伴走しながらブランド再生と再認を作り上げるためにクライアントのブランドアイデンティティとブランドイメージの一致を目指し、日々活動しています。 |