SNS採用ブランディング|InstagramとTikTokの最新活用術
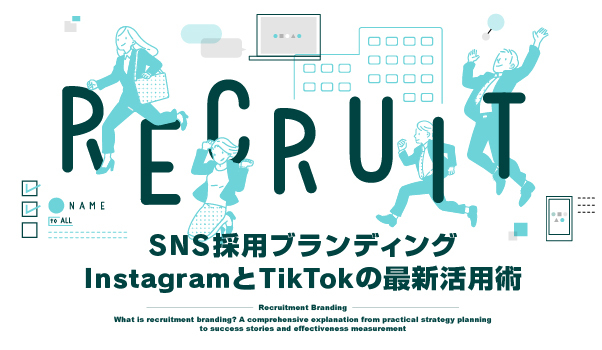
採用活動の主戦場は、いま「検索」から「SNS」へと移りつつあります。求職者が企業を知るきっかけの多くが、求人サイトや採用ページではなく、InstagramやTikTokなどのSNS上の発信に変化しています。
特にZ世代や若手層は、企業の「言葉」よりも「空気感」や「人の雰囲気」を重視する傾向にあります。彼らにとって、SNSで発信される写真や動画は単なる広報ではなく、企業文化を感じ取る“第一印象の場”です。つまり、SNSは「応募前の採用説明会」とも言える存在になっています。
一方で、企業側では次のような課題も多く見られます。
「SNSを始めたけれど、フォロワーが増えない」
「リール動画を投稿しても応募に結びつかない」
「発信の方向性が定まらず、担当者の感覚に頼っている」
SNS採用ブランディングの本質は、“バズる”ことではなく、“らしさを伝え続ける”ことです。求職者が“共感”を感じる発信を積み重ねることで、自然とファンが増え、応募やリファラルにつながる「循環」が生まれます。
InstagramやTikTokは、それぞれ異なるアルゴリズムと文化を持つプラットフォームです。その違いを理解し、目的に応じて「どんな発信を、どんなトーンで行うか」を設計することで、SNSは採用ブランディングの最強の武器となります。
本記事では、SNS採用の現状から最新の活用トレンド、そして成果を上げている企業の共通点までを体系的に解説します。
- SNS採用ブランディングの現状と課題
- Instagramで“世界観を伝える”ための運用戦略
- TikTokでZ世代の共感を生む構成とトレンド活用
- SNS運用で成果を出す企業の実践事例
“採用広報”から“採用ブランド発信”へ。SNSを「企業の人格を伝えるメディア」としてどう活かすか。その最新戦略を、ここで明確にしていきましょう。
|
目次
|
SNS採用ブランディングの現状
SNSは、いまや採用活動における“第二の採用サイト”といっても過言ではありません。InstagramやTikTokを中心に、求職者が企業のリアルを知る主要な接点として機能しています。特に若手世代では、求人媒体よりもSNSから情報を得て応募を検討する割合が年々増加しています。
その背景には、情報取得のスタイル変化があります。かつては企業が一方的に発信する「情報主導型」の採用広報が中心でしたが、現在は“体験主導型”へとシフトしています。求職者は、「どんな会社か」ではなく、「どんな人が働き、どんな雰囲気があるのか」をSNS上で観察し、共感できる企業にのみ関心を示します。
実際に、就活ナビサイトや人材調査機関のデータでも、「Instagramで企業アカウントをチェックしている学生」は7割を超え、「TikTokで採用関連動画を見たことがある」と答える学生も半数近くにのぼります。つまり、SNS上の“印象”が応募率やブランドイメージを左右する時代になったのです。
一方で、企業のSNS活用には課題も多く存在します。特に中小・ベンチャー企業では、発信担当者が兼務で運用しており、発信の一貫性や継続性が課題となるケースが目立ちます。また、「何を投稿すべきか」「誰に向けた発信なのか」が曖昧なまま運用されている企業も少なくありません。
SNS採用ブランディングの本質は、“情報を届ける”ことではなく、“共感を育てる”ことにあります。つまり、採用におけるSNS運用とは、「フォロワーを増やす活動」ではなく、「企業文化を好きになってもらう活動」です。
フォロワー数ではなく、投稿1つひとつへの反応こそが、ブランド共感度を示す指標になります。
今、SNSは「広報」でも「宣伝」でもなく、“採用ブランドの体現ツール”へと進化しています。企業がどんな姿勢で働き方を見せるか、どんなトーンで社員を紹介するか。その一つひとつの発信が、「この会社らしさ」を形づくり、応募意欲へとつながっていくのです。

Instagram活用のポイント
Instagramは、採用ブランディングにおいて最も“世界観”を伝えやすいプラットフォームです。ビジュアルの統一感やトーンの設計次第で、企業の印象は大きく変わります。単なる写真投稿アプリではなく、「企業の人格を視覚的に表現するメディア」として活用することが、成果を出すための鍵です。
ビジュアル統一とトーン設計
Instagramで採用ブランドを構築する上で最も重要なのは、“投稿を一覧で見たときの印象”です。ユーザーは1投稿だけでなく、プロフィールページの全体トーンを一瞬で判断します。だからこそ、統一感のある世界観設計が信頼と共感の第一歩になります。
たとえば、次のような軸を決めておくと、運用の方向性がぶれません。
- カラー:コーポレートカラーまたはテーマカラーを基調にする
- フォント:投稿画像の文字は常に同一フォントで統一
- 構図:人物中心か、オフィス風景中心かを明確にする
- トーン:「明るく親しみやすい」「落ち着いた上品さ」などの印象を一貫させる
このトーン設計は、採用だけでなく企業ブランディング全体に波及します。投稿が社員の個性とリンクしているほど、求職者は「ここで働く自分」を想像しやすくなります。
また、キャプション(投稿文)は、説明よりも“共感”を重視しましょう。「〇〇さんの一日は…」と事実を伝えるよりも、「挑戦の毎日が、チームの活気をつくる。」といった情緒的なトーンが、ブランドの温度を伝えます。
Instagramは“写真の美しさ”ではなく、“世界観の整合性”で信頼される時代。視覚的な一貫性こそ、採用ブランディングにおける最大の武器です。
リール投稿とストーリーズ戦略
Instagramでの採用ブランディングを加速させるのが、リール投稿とストーリーズ運用です。特にリールは、アルゴリズム上“発見タブ”で新規ユーザーにリーチしやすく、企業認知を拡大する最強の手段といえます。
リールのポイントは、「短く・軽く・リアルに」。
たとえば、
- 社員の1日を30秒でまとめたVlog風動画
- 新入社員のリアクションを切り取ったオフショット
- チームの掛け声や朝礼シーンなど“音で感じる文化”
といった動画が高いエンゲージメントを生みやすい傾向にあります。過剰な編集よりも、“人の素”が伝わる映像が共感を呼びます。
一方で、ストーリーズは「関係を深めるツール」としての活用が有効です。一過性の発信ではなく、日常の延長として活用することで「親近感」や「リアルさ」を生みます。
社内イベント・誕生日・小さなチームの瞬間などを“等身大”で共有することで、フォロワーが「身近に感じる」関係が生まれます。
また、ストーリーズのハイライト機能を活用して「社員紹介」「採用FAQ」「カルチャー紹介」などのカテゴリーを固定表示すれば、採用サイトのミニ版としても機能します。このように、リールで“広げ”、ストーリーズで“育てる”。この2つの役割を意識した運用が、Instagram採用ブランディング成功の基本戦略です。

TikTok活用のポイント
TikTokは、Z世代の採用ブランディングにおいて最も影響力のあるプラットフォームです。短尺動画という形式を通じて、企業の“人となり”や“温度感”をリアルに伝えることができます。特に、エンタメ性とリアリティを兼ね備えた発信は、従来の採用広報では届かなかった層に強く響きます。
Z世代の共感を生む構成とは
TikTokで成功する採用ブランディングの鍵は、「リアル×ストーリー性×テンポ感」。Z世代は、企業が作り込んだ映像よりも、“本音で話す人”や“素の瞬間”に心を動かされます。だからこそ、動画の目的は「企業をよく見せること」ではなく、「人を感じてもらうこと」です。
たとえば、次のような構成が効果的です。
- 冒頭3秒で興味を引く
冒頭に“問い”や“驚き”を置く。「この会社、入社初日に社長が出迎え!?」など、思わず続きを見たくなるフックを設計します。 - 中盤でストーリーを展開
日常風景や会話の中に「会社の雰囲気」や「人間関係の温かさ」を自然に織り込みます。演出よりもリアルを重視することで、信頼を獲得できます。 - 最後に“感情の余韻”を残す
「ここで働けてよかった」と笑う社員の表情や、「挑戦を支えるチーム文化」を示す一言で締めくくると、視聴後の印象が深まります。
特にZ世代は「企業の理念」よりも「日常の空気感」を重視します。そのため、採用広報用のきれいな動画よりも、スマホで撮影した自然な映像のほうがエンゲージメントを得やすい傾向にあります。TikTokは“完璧さ”よりも“共感のリアリティ”を評価するプラットフォームです。
また、社員本人が登場する動画は非常に効果的です。「人事担当の1日」「営業チームの出社ルーティン」「入社1年目のリアル」など、“働く人の視点”から企業を見せることで、視聴者は「自分ごと」として感じ取ることができます。
ハッシュタグとアルゴリズムの理解
TikTokを採用ブランディングに活かすには、アルゴリズムの理解が欠かせません。TikTokの強みは“フォロワー以外への拡散力”にあり、投稿の質が良ければ無名企業でも数万〜数十万回の再生を狙えます。
そのために重要なのがハッシュタグ設計と投稿タイミングです。
ハッシュタグは、「広く見てもらう」ためのトレンド系と、「深く届かせる」ためのテーマ系を組み合わせるのが基本です。
- トレンド系例:「#就活」「#社会人vlog」「#新人の日常」
- テーマ系例:「#〇〇会社の裏側」「#〇〇業界の仕事」「#働くってなんだろう」
また、TikTokのアルゴリズムは“最初の1時間の反応率”を重視するため、投稿後すぐにエンゲージメントを集めることが重要です。社内で「いいね」や「コメント」を促す仕組みを作ると、初動を高めやすくなります。
さらに、投稿頻度は“週1本よりも、短尺×高頻度”が理想です。1本あたり15〜20秒の動画を週3本投稿するほうが、アルゴリズム上の評価が上がりやすい傾向にあります。
TikTokでの成功は、「流行を追うこと」ではなく、「自社らしい文脈でトレンドを解釈すること」。流行りの音源や構成を取り入れつつも、企業の理念やカルチャーと結びつけることで、“一瞬のバズ”ではなく“持続的な好感”を生み出すことができます。
TikTokは、採用ブランディングにおける“共感を得る場所”です。リアルでユーモアのある日常を通じて、「この会社で働くの、ちょっと楽しそう」と思わせることができれば、採用への最短距離が見えてきます。

SNS運用の採用ブランディング成功事例
SNS採用ブランディングで成果を上げている企業には、共通した「設計思想」と「継続の仕組み」があります。単に投稿頻度やフォロワー数の多さではなく、“企業のらしさ”を一貫して伝え続けているかどうかが鍵です。ここでは、Instagram・TikTokを活用して成果を出している3つの成功パターンを紹介します。
① 世界観を統一した「Instagramブランディング型」
ある地方の製造業企業は、採用難が続く中でInstagramを中心としたブランディングを展開しました。特徴は「写真の美しさ」ではなく、“働く人の姿を丁寧に切り取る”投稿スタイル。毎週1回、社員の笑顔・チームミーティング・工場の風景などを同じ色味とトーンで発信しています。
投稿のトーンは「誠実・温かい・等身大」。キャプションには「この町でモノづくりを続ける理由」など、理念を短い物語として添えています。その結果、フォロワー数は半年で約5倍に増加し、「Instagramを見て応募しました」という学生が3割を超える成果を生みました。
この事例が示すのは、SNSは「派手さ」よりも「一貫性」で信頼をつくるということ。
“見た瞬間に伝わる世界観”が、ブランドの印象を決定づけます。
② 社員が主役の「TikTok共感型」
あるベンチャー企業では、人事部が中心となり、TikTokで「社員の日常」を発信。テーマは“企業を紹介しない採用動画”。社員の雑談風景やオフィスのランチタイム、仕事終わりの一言など、“本音と笑顔”を30秒にまとめています。
再生数は決して爆発的ではないものの、コメント欄には「雰囲気が好き」「ここで働きたい」といった声が多数。実際にエントリー数が前年比180%に増え、採用単価も半減しました。
この成功要因は、“完璧さ”を手放したことです。演出された広告ではなく、「人が見える」「空気が伝わる」映像が、Z世代に最も響くコンテンツになります。
③ ストーリーで文化を伝える「ハイブリッド型運用」
大手IT企業では、InstagramとTikTokの両方を組み合わせ、発信目的を明確に分けています。Instagramでは「企業の理念・価値観・世界観」を、TikTokでは「社員のリアル・日常・カルチャー」を発信。同じテーマでもトーンを変えることで、プラットフォームごとに違う感情体験を設計しています。
たとえば、Instagramでは「#挑戦する文化」をハッシュタグとして使い、社員インタビューを写真とテキストで紹介。一方TikTokでは、その社員の1日を15秒動画で公開し、視覚的に“挑戦の瞬間”を体感させています。
この一貫した発信設計により、採用ブランドの認知が急速に拡大し、SNS経由の応募比率が全体の40%を突破しました。
この事例のポイントは、「プラットフォームを分けても、世界観はひとつ」ということ。
InstagramとTikTokは別のメディアではなく、一つのブランドストーリーを伝える“異なる章”として活用するのが理想的です。
これらの成功企業に共通するのは、「SNSを担当者の感覚で運用しない」こと。ブランドトーン・発信テーマ・投稿リズムを“仕組み化”し、誰が発信しても同じ温度で「らしさ」が伝わる状態をつくっています。
SNS採用ブランディングの成果は、短期のバズではなく、長期の信頼形成によって生まれます。そしてその信頼が、応募・リファラル・内定承諾率の上昇という“数字の結果”へと確実につながっていくのです。

まとめ|SNSで「らしさ」を伝える時代
SNS採用ブランディングの本質は、“企業を見せること”ではなく、“企業のらしさを感じてもらうこと”です。InstagramやTikTokの登場によって、求職者は企業の一方的なメッセージではなく、リアルな日常や文化を自ら体験するように情報を得る時代になりました。
求職者はもう、「何をしている会社か」よりも、「どんな人たちが、どんな想いで働いているか」に関心を寄せています。そのため、SNS運用は広報の延長ではなく、“採用の最前線”として戦略的に設計する必要があります。
Instagramでは世界観とトーンを統一し、企業の人格を視覚的に表現する。TikTokではリアルな日常や人の温度感を通して共感を生み出す。それぞれのメディア特性を理解し、「見て終わり」ではなく「心に残る」体験設計を行うことが、SNS採用の成功条件です。
▶︎関連記事
【完全版】採用ブランディングとは?実践戦略の立案から成功事例・効果測定まで徹底解説

| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。