ブランディングとSEOの関係性と成果を出す施策設計

検索順位を上げたいならSEO、信頼と好感度を高めたいならブランディング――そう切り分けてきた時代は終わりました。2025年6月のGoogleコアアップデート以降、検索エンジンは「ユーザー体験の全体像」を重視するようになり、ブランドの信頼性やストーリーがSEO評価に直接影響する構造へと変化しています。
本記事では、SEOとブランディングの関係性を軸に、どのように両者を融合させて成果を出すか、そしてAIO・LLMO時代に対応する戦略設計について実践的に解説していきます。
|
目次 |
なぜ「ブランディング」と「SEO」は今、融合すべきなのか?
2025年6月のGoogleコアアップデート以降、検索エンジンの評価基準は「単なるキーワード一致」や「被リンク数の多さ」から大きく変化しています。特に注目されているのが、ユーザーの検索行動の背後にある“意図”や“信頼性のあるブランドかどうか”という視点です。この変化により、SEOとブランディングはもはや別々に取り組むものではなくなりました。
検索結果の上位に表示されるコンテンツは、ユーザーの課題解決に役立つだけでなく、「誰が発信しているのか」「どんな背景や価値観を持っているのか」までが問われています。つまり、SEOは“ブランド”の上に構築される戦略であるべきなのです。
検索行動は“ブランド体験”の入口になった
現代のユーザーは、何らかのニーズを自覚した瞬間に検索行動を起こします。つまり、検索とは“顕在化したニーズ”の証そのものであり、検索窓に入力された言葉は、ユーザーの今まさに解決したい課題を表しています。
この時、検索結果から遷移したホームページにおいて、ユーザーが初めて触れるのが企業の「ブランド体験」です。単に情報が並べられているだけのページでは、信頼も印象も得られません。問題意識に共鳴し、世界観や価値観を伝えるコンテンツ設計がなされていなければ、ユーザーは競合他社へと流れてしまいます。
私たち株式会社ジャリアが重視しているのは、この検索→遷移→体験という一連の流れを、“ブランド想起につなげる体験設計”として戦略的に捉えることです。検索結果で得た第一印象と、遷移先で出会うブランド体験に一貫性があれば、ユーザーの中に強固な「記憶」が形成され、再検索や指名検索へとつながります。これが、ただのSEO施策では到達できない“ブランドSEO”の本質です。
ブランドとSEOの融合は、単に順位を上げるためではなく、検索体験を通じてブランドの価値を正しく伝えることを目的とすべきフェーズに来ているのです。
Googleのアルゴリズムとブランド認知の相関性
Googleは常に、ユーザーにとって「信頼できる情報源」を優先して表示することを目的にアルゴリズムを進化させてきました。その中で注目すべきは、情報の“発信主体”が誰であるかという点に、以前よりも強いウェイトが置かれるようになっていることです。単なる情報量やキーワード出現率だけでなく、その情報がどれだけ信頼され、他者に言及され、ブランドとして認知されているかが、検索順位を左右する要素となってきています。
たとえば、企業名やサービス名がSNSや口コミ、他サイトの記事、YouTubeの概要欄などで頻繁に取り上げられていると、Googleはそれを「関連性の高い情報」として認識します。これは明確な被リンクが存在しなくても、コンテンツの“周辺文脈”から信頼性を判断していることの証左です。
また、ナレッジパネルやローカル検索に表示されるGoogleビジネスプロフィール情報にも、アルゴリズムは強く依存するようになりました。営業時間、レビュー評価、投稿頻度などが検索結果のランキング要因になるだけでなく、それらが「ユーザーとどれだけ一貫したブランド体験を提供しているか」も評価対象となっています。
私たちジャリアでは、これを「ブランドの外部評価と文脈整合性によるSEO強化」と捉え、企業がオンライン上でどう語られ、どのような印象を持たれているかを設計・運用の中核に置いています。ブランドとしての一貫性がある発信は、検索順位を安定化させ、競合と差別化されたポジションを築くうえで不可欠な戦略資産になるのです。
ブランディングはSEO評価の“非リンク”に匹敵する武器
従来のSEOでは、外部サイトからの被リンク(バックリンク)が検索順位に大きな影響を与えるとされてきました。確かに、今でも高品質な被リンクは評価されますが、2025年現在ではそれだけでは不十分です。検索エンジンは、直接的なリンク構造だけでなく、“どのように言及されているか”“どのようなコンテキストで話題になっているか”という、非リンク的な評価指標を重要視するようになっています。
たとえば、ある企業名がSNSで自然に言及されたり、YouTube動画内の会話で何度も登場したりすることは、Googleにとって「このブランドはユーザーから語られる価値がある存在である」と認識するきっかけになります。これは、リンクを伴わないにもかかわらず、SEO上の評価に直結する“非リンク型シグナル”です。
さらに、Google DiscoverやAIO(AI Overviews)における情報抽出は、被リンクの有無ではなく「情報源としてどれだけ信頼されているか」「他の情報とどれだけ一貫性を持っているか」を重視します。ここで強みとなるのが、ブランドそのものが持つ信頼性・専門性・実績です。
ブランディング施策をSEO文脈で捉える際、重要視しているのがこの“非リンク領域”の強化です。たとえば、自社のブランド名が第三者のブログや解説記事、SNSや口コミで一貫してポジティブに語られるように設計されたコンテンツは、たとえリンクが張られていなくても、ブランドの存在感と信頼性を裏付ける強力な要素になります。
つまり、ブランディングは単なる認知や好感度の向上にとどまらず、検索エンジンにおける評価の「見えないリンク構造」として機能し、SEO戦略を根底から支える存在なのです。
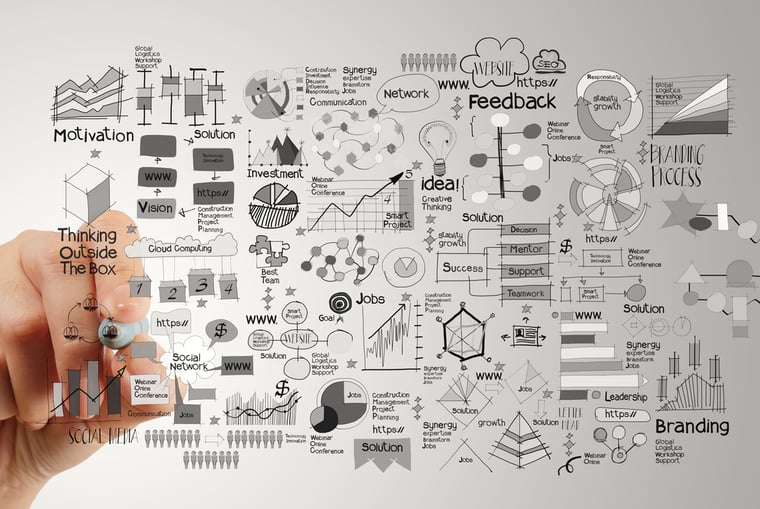
SEO観点から見たブランディングの役割と効果
従来のSEO戦略は「Googleに評価されるための最適化」に集中していましたが、現在はそれだけでは成果に直結しません。検索エンジンが重視するのは、「どれだけユーザーにとって信頼できる情報源か」「再訪や指名検索につながる存在か」という観点です。つまり、SEOにおいても“誰が発信しているか”が問われる時代になりました。
この変化に伴い、ブランディングの力がSEOの成果を左右する構造が明確になってきています。ブランド認知が高まることで指名検索が増え、CTR(クリック率)が向上し、さらに検索体験全体に好影響を及ぼす好循環が生まれます。このセクションでは、SEO視点からブランディングが果たす具体的な役割について掘り下げていきます。
指名検索の増加がもたらすSEO上の恩恵
指名検索とは、企業名や商品・サービス名を明示的に検索されることを指します。たとえば「ジャリア ブランディング」「○○株式会社 採用サイト」などが該当します。このような検索はユーザーの中に明確なブランド認識がある証であり、Googleはそれを“ブランドとしての信頼性”の一つと見なしています。
実際に、Search Consoleで指名検索のインプレッション数やCTRが高まっているページは、非指名ワードの評価にも良い影響を与える傾向があります。ユーザーが「選びたい」と思えるブランドを育てることは、SEOにおける最強の防御力であり、かつ攻めの施策とも言えるのです。

SERPで目立つ「ブランド表記」「サイトリンク」の効果
検索結果ページ(SERP)でユーザーの目を引く要素として、「ブランド名付きのタイトル」「パンくずリスト構造」「サイトリンク表示」などがあります。これらはGoogleが“明確にブランドとして認識している”ときに表示されやすく、クリック率を大幅に向上させる要因となります。
とくにサイトリンク(企業名で検索した際に表示される下層ページリンク)は、ユーザーにとっての信頼指標となるだけでなく、ブランド体験の構造設計を反映するものです。ブランディングを意識した情報設計・階層設計がなされているかどうかは、こうした表示結果にも如実に反映されるのです。
E-E-A-T評価とブランド認知の関係性
GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を評価指標として明示しており、ここに「ブランド認知」が強く影響します。つまり、「どこの誰が」「どのような背景で」情報を発信しているかがSEOでの可視性を左右します。
たとえば、専門的な知見を持つ企業が、自社の業界トピックを実名・実体として発信していれば、それは匿名のまとめ記事よりも高く評価されます。ブランディングがある企業は、E-E-A-Tの観点からも優位に立てるため、検索順位の安定性が増し、アルゴリズム変動の影響も受けにくくなるのです。
私たちジャリアでは、このE-E-A-Tとブランド認知を「SEO耐性の二本柱」として捉え、ブランド設計とコンテンツ設計を一体で進めることを推奨しています。
SEOに効く“ブランディング的なコンテンツ”とは
Googleのアルゴリズムが進化し、評価軸が「情報の正確性」や「更新頻度」から、「発信者の信頼性」や「文脈的な一貫性」へとシフトする中、今求められているのは“ブランドを伝えるコンテンツ”です。ただアクセスを集めるのではなく、ユーザーの記憶に残り、検索行動の先にあるブランド想起へとつなげるコンテンツが、SEOに強く影響するようになっています。
ここでは、私たちジャリアが実践する“ブランディングの視点から見たSEOコンテンツ”の設計ポイントをもとに、成果を出す具体的な構成と執筆手法を解説します。
「理念・ミッション・ストーリー」がある記事の強さ
SEOコンテンツというと、一般的には「How to系」「キーワード解説型」が主流です。しかし、Googleは「どの企業が」「なぜこの情報を発信しているのか」を重視するようになっています。つまり、企業の理念やビジョン、創業ストーリーといった“背景”が語られることで、記事は単なる情報ではなく“ブランドメッセージ”へと昇華します。
私たちジャリアがコンテンツを設計する際にも、単なるノウハウやトレンド解説ではなく、「なぜこのテーマに取り組んでいるのか」「どういった姿勢で社会と関わっているのか」といった視点を必ず盛り込むようにしています。こうした文脈があることで、Googleにとってもユーザーにとっても、情報が“意味あるもの”として届くのです。
ブランドと文脈整合性を両立する構成の作り方
Googleは今、ページ内のキーワードの整合性だけでなく、「その情報がサイト全体・ブランド全体の文脈と一致しているか」を評価するようになっています。ここで重要になるのが「トピッククラスター」や「内部リンク設計」です。
私たちは、ジャリアのオウンドメディアにおいても各ページの内容を単独で完結させず、全体のブランドテーマに沿った文脈の中で役割を持たせるように設計しています。例えば、ブランドデザインに関するページであれば、ロゴ制作、デジタルブランディング、SNS活用などの関連テーマと連携させて設計し、コンテンツの一貫性と専門性を高めています。
この文脈整合性があることで、検索エンジンは「専門的なサイトである」と判断し、上位表示の可能性が高まります。同時にユーザーにとっても「体系的に情報が整理されている」ことで信頼が生まれ、コンバージョンにもつながりやすくなります。
見出し設計と導線に“ブランド体験”を織り込む方法
ブランディング視点のSEOコンテンツにおいては、見出し設計とページ内導線の作り方にも工夫が必要です。単に「キーワードを入れる」のではなく、「この見出しがユーザーにどんな価値を伝えるのか」「どのような順序で読み進めればブランドが伝わるか」を意識して構成する必要があります。
ジャリアでは、h2・h3といった階層見出しに「ブランドが大切にしている考え方」や「体験に近い事例的要素」を組み込むことで、ユーザーが読み進めながら“ブランドと価値観を自然に理解していく”設計を重視しています。
たとえば、あるサービス紹介記事でも「導入事例」「制作背景」「実際の反響」などを見出しに盛り込むことで、「この企業は現場目線で発信している」と伝えることができます。このように、見出しと導線を通じてブランド体験を内包することで、読み手の感情に寄り添い、SEOとブランディングを両立する強い記事が生まれます。
ブランディングの観点で見直すSEO施策の設計
従来のSEO施策は、テクニカルな対応やキーワード選定が中心でした。しかし、Googleが“検索意図に寄り添う”ことを強く求めるようになった今、そこに「ブランドとしてのあり方」や「価値提供の一貫性」を反映させなければ、持続的に評価されるサイト運用は難しくなっています。
SEO施策そのものをブランディングの延長として再設計することで、指名検索の増加、再訪率の向上、サイト滞在時間の伸長といった、より本質的な成果が得られます。ここでは、SEOの実装フェーズに“ブランドの視点”を統合する具体的な方法を解説します。
検索クエリの“ブランド化”を意識したキーワード選定
単に月間検索ボリュームが多いキーワードを狙うのではなく、自社が届けたいメッセージや提供する価値を反映したクエリを中心に設計することが重要です。これは、ユーザーの検索行動をブランド体験の一部とみなすという、私たちジャリアの基本的な考え方にも直結しています。
例えば「福岡 ホームページ制作」だけでなく、「福岡 ブランド体験 設計」や「企業ブランディング 戦略」といった“文脈を含むクエリ”を主軸に据えることで、よりブランドと親和性の高いユーザーを呼び込むことが可能になります。
ナレッジパネルやGoogleビジネスプロフィールとの連携
Google検索におけるブランドの可視化という点で、ナレッジパネルやビジネスプロフィールとの連携は極めて重要です。ここに一貫した情報とビジュアル、企業としての姿勢が表現されていれば、それだけで検索結果における信頼性とブランド認知が大きく高まります。
私たちは、会社概要・代表者情報・実績などの基本情報をGoogleに正しく認識させる構造設計と、オウンドメディア・外部記事・SNSと連動した情報発信により、ブランドとしての「信頼の外部構造」を強化する取り組みを推奨しています。
メタ情報・構造化データに込める「ブランドメッセージ」
タイトルタグやディスクリプション、構造化データは、検索結果上でユーザーに最初に触れられる“ブランドの顔”とも言える部分です。ここにこそ、ブランドの考え方や姿勢を自然に織り込むべきです。
たとえば「福岡の企業を“選ばれるブランド”に育てるホームページ戦略」など、ジャリアが実際に用いているディスクリプションのように、単なる説明で終わらせず「なぜその情報を届けているのか」が伝わる表現にすることで、他社との差別化と、ブランディングの深化が可能になります。
また、構造化データの活用も同様です。FAQやレビュー、著者情報のマークアップを通じて、ブランドとしての姿勢やユーザーとの関係性をGoogleに正しく伝えることで、評価軸としての「文脈整合性」「信頼性」「経験」が強化されていきます。
AIO・LLMO時代におけるSEOとブランドの役割
2025年現在、Googleの検索体験は大きく変わろうとしています。生成AIによる要約表示「AI Overviews(AIO)」の登場や、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)による情報取得の一般化により、従来型のSEOだけでは成果を上げづらい局面が増えてきました。
こうしたAIO・LLMO時代においては、検索結果の「先」に表示されるAIによる要約や回答の“元情報”として取り上げられるかどうかが、ブランドへの流入や認知に直結します。その鍵を握るのが、ブランドとしての一貫性ある発信と、AIにとって“意味のある情報”を提供しているかどうかです。
AIOで拾われるには“意味の一貫性”が不可欠
AIOは、単にページの一部を要約しているのではなく、「質問に対して文脈的に最も適した情報」を抽出しようとしています。そのため、記事単体ではなく、サイト全体としての一貫性が評価の前提条件となります。
私たちジャリアが重要視しているのは、「ブランドの姿勢が全ページに通底しているか」「記事ごとの語り口や視点が統一されているか」といった、“非構造化された文脈”の一貫性です。AIはこのような統一性をもとに、回答の信頼性を判断します。
たとえば、同じ企業のブログ記事であっても、トーンや論点、価値観がバラバラでは、AIにとって「どのような立場の企業か」が不明確になり、回答元として取り上げられにくくなります。つまり、AIが読むのは“文脈の積み重ね”なのです。
LLMOが評価する“ブランドの語られ方”とは
LLMO(大規模言語モデル最適化)においては、検索エンジンよりも“第三者による語られ方”が重要な評価指標になります。SNS、外部メディア、レビューサイトなどで、ブランドがどのように紹介・評価されているかが、AIモデルの“回答候補の選定”に強く影響するからです。
たとえば、「福岡 ホームページ制作 おすすめ」と入力した際に、ジャリアの名前が複数の信頼性あるサイトやSNS投稿で触れられていれば、AIはそれを“文脈上の有力候補”として判断します。つまり、AIOやLLMにおけるブランディングとは、サイト内発信だけでなく“語られ方の戦略”を含む包括的な設計である必要があるのです。
構造的な文脈設計でAIに伝わるブランドを構築する
AIに選ばれるブランドになるには、単なるSEOやコンテンツ更新の延長では不十分です。重要なのは、「ブランドとして何を発信し、どういう一貫性を持ち、どのような第三者の証言があるか」という“構造的文脈”を整えることです。
私たちはそのために、以下のようなステップを推奨しています。
- ブランドドキュメントやトーンガイドラインの作成
- 全コンテンツへの一貫したブランド視点の適用
- 他サイトやSNSでの“語らせ方”を意図した露出戦略
- FAQ・HowTo・レビュー・事例記事など多様な形式での展開
これらを実行することで、AIが情報を要約・再構成する際に、より精度高く「ジャリアらしい回答」が引用されるようになります。AIO・LLMOの進化は脅威ではなく、ブランド戦略を本質的に伝える新たなチャンスでもあるのです。
成果を出す「ブランディング×SEO」の実践ステップ
ここまで述べてきたように、現代のSEOは単なる順位争いやキーワード施策にとどまらず、「ブランドのあり方」「語られ方」「体験設計」が成功の鍵を握っています。そのため、SEOとブランディングを連携させた戦略は、単発的な施策ではなく、段階的かつ持続的に構築されるべきものです。
私たちジャリアでは、“検索行動から始まるブランド体験の設計”を軸に、企業のWEB戦略を再構築するプロセスを推奨しています。ここでは、その具体的な実践ステップを3段階に分けて解説します。
ブランド設計を起点にコンテンツ戦略を再構築する
まず最初に行うべきは、ブランドとして「何を大切にしているか」「誰にどんな価値を届けたいのか」というコアを明確にすることです。これが定まらない限り、どれだけコンテンツを量産しても一貫性のない情報群になってしまい、ユーザーにもGoogleにも伝わりません。
ブランドの軸が定まったら、それを軸にしてトピッククラスターを設計し、ページごとの役割と関係性を明確化します。私たちの現場では、キーワード設計の前に「ブランドメッセージマップ」を作成し、それをもとにSEO施策を紐付けていく工程が定番です。
SEOディレクションに“ブランド視点”を取り入れる方法
SEOの実装フェーズでも、ブランド視点の導入は欠かせません。具体的には、以下のようなポイントで“ブランドを語る設計”を意識することが重要です。
- タイトル・ディスクリプションで伝える理念や価値観
- コンテンツの冒頭に背景・目的・姿勢を語る導入文
- 見出し設計におけるトーンと語り口の一貫性
- 内部リンクによるブランドストーリーの流れ設計
こうした構造によって、検索エンジンは単なる情報でなく“語り手の存在”を認識しやすくなり、ユーザーも記事を読み進める中で自然とブランドに触れていく流れを作ることができます。
制作チーム・経営層・現場での役割と連携設計
ブランディングとSEOを統合した施策を成功させるには、マーケティング部門だけでなく、経営者や現場メンバーも巻き込んだ体制づくりが欠かせません。
私たちは、ブランド戦略をコンテンツ制作の初期段階から共有し、制作チームが“単なる下請け”にならないように設計しています。たとえば、経営者インタビューや社内ワークショップを通じて、ブランドの価値観やトーンを文書化し、ライターやSEO担当にも共有。これにより、誰が見ても「このブランドらしい」と思える一貫性が維持されるのです。
また、定期的なKPI確認やレビュー会議で、「指名検索の増加」「ブランド関連クエリでの表示回数」「ページ滞在時間」などを評価指標に据えることで、SEOとブランディングを一体運用する仕組みが生まれます。
SEOとブランディングは、別物ではなく“同じゴールを異なる角度から支える戦略”です。成果を出すためには、目先の順位だけにとらわれず、ブランドを育てる視点でのSEO戦略こそが今、求められています。
よくある質問(FAQ)
Q1. ブランディングとSEOはそれぞれ何が違うのですか?
ブランディングは、企業や商品が「どう見られたいか」「どのような印象を与えたいか」を設計するための戦略です。一方、SEOは「どうすれば検索エンジンから見つけてもらえるか」を考える施策です。従来はこの2つを別物と捉える傾向がありましたが、現在は“検索行動自体がブランド体験の入り口”であるため、両者は相互に密接に関係しています。ユーザーが検索を通じてブランドに出会う構造を意識することで、ブランディングとSEOは連動した施策になります。
Q2. ブランディングを意識したSEO施策は、どこから始めるべきですか?
第一歩は「ブランドとして何を伝えたいか」を明確にすることです。そのうえで、伝えるべき価値観を反映したキーワードを選定し、トピック構造やページ導線を設計することが重要です。たとえば、“理念やビジョンを語る導入文”や“ブランドトーンが反映されたタイトル・ディスクリプション”など、ページごとの語り口を整えることで、検索エンジンにもユーザーにも一貫性のあるブランドが伝わります。
Q3. AIOで自社の情報が取り上げられるにはどうすればいいですか?
AIO(AI Overviews)で取り上げられるには、ページ単体ではなくサイト全体としての文脈的な一貫性が必要です。ブランド視点に基づいた構造設計、FAQ・レビュー・ナレッジ記事など多角的な情報発信、そして第三者サイトでの言及などが有効です。Googleが「信頼できる情報源」として認識するには、“継続的に価値ある情報を発信している存在”であることが重要です。
Q4. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)はどうやって高められますか?
企業の実体性をコンテンツに反映させることがカギとなります。たとえば、実名での発信、実績のある事例紹介、業界での評価や露出、チームメンバーの紹介などが挙げられます。また、サイト全体の情報構造として、「どのページでも一貫して同じ姿勢が伝わる」ように設計されていることも、E-E-A-T強化に直結します。信頼は“全体で築かれるブランド資産”として構築されるべきです。
Q5. 中小企業でもブランディング×SEOを実現できますか?
はい、むしろ中小企業こそ、ブランディングとSEOを連携させることで差別化が可能になります。限られた予算でも、「誰に、何を、どう届けるか」を明確にしたうえで、SEOコンテンツをブランド視点で丁寧に設計すれば、大手と並ぶ検索評価やCVを得ることも十分可能です。重要なのは、量よりも“設計の質”と“語りの一貫性”です。
まとめ|SEOで成果を出すには“ブランドの一貫性”が不可欠
2025年のSEOは、単に検索順位を上げることではなく、「検索体験全体でどれだけ信頼され、選ばれるブランドになれるか」が問われる時代です。Googleの評価軸が「ユーザーファースト」や「E-E-A-T」「文脈整合性」にシフトし、AIOやLLMOなどAI技術の進化により、情報の“質”だけでなく“背景や発信者の一貫性”まで求められるようになりました。
その中で、企業にとってのSEOとは、“ブランド体験を届ける設計手段”であり、検索行動そのものを通じてユーザーとつながる「第一接点」の場になっています。だからこそ、ブランドの軸がぶれないコンテンツ設計、語り方の統一、トーンの設計、検索導線の設計まで含めて、SEO戦略は「ブランドを軸に据える」ことで本質的に強くなっていくのです。
私たちジャリアでは、「検索から始まるブランド体験」の視点で、クライアント企業のSEOとブランディングを融合させたコンテンツ戦略を設計しています。順位やCTRといった指標の先にある、“指名検索されるブランド”“記憶に残る情報発信”“社内外から評価されるブランド像”をともに築いていくことが、今後のSEO成功の鍵になると確信しています。
短期的な成果を超えて、長く支持されるブランドを育てる視点でSEOに取り組む――それが、今この時代に最も求められている「ユーザーファースト」の実践であり、検索エンジンが評価する“本質”へのアプローチなのです。

弊社では、広告代理店だからこそできるブランディング計画から始まり、伴走型のブランド醸成を行います。中長期的なビジョンを持ち、プロモーション計画とサイトSEOを行いつつ、貴社のブランド発信のPDCAを行っていきます。
ブランディングを通して企業の価値を高めたい、ブランディングとマーケティングの相乗効果で売上アップを図りたいという方は、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
| WRITER / HUM 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBライター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |