インナーブランディングと採用ブランディング|社員を巻き込む施策と成功事例とは?
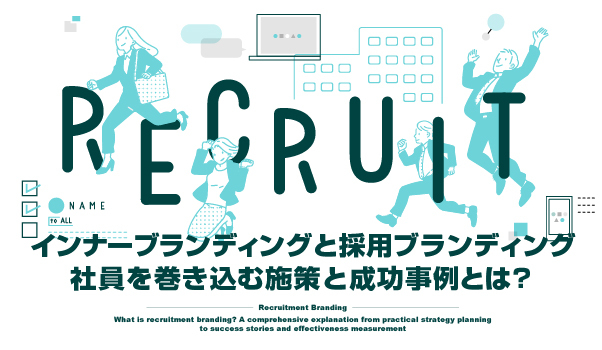
採用活動の成果を左右するのは、広告や求人原稿のクオリティだけではありません。いま、企業の“中の声”つまり社員のリアルな発信や働く姿勢こそが、最も強力な採用ブランディングの源になっています。
「どんな会社か」を語るより、「どんな人が働いているか」を感じてもらう。この“内側からのブランド形成”を支えるのが、インナーブランディングです。
インナーブランディングとは、企業の理念や価値観を社員一人ひとりに浸透させ、組織としての一体感と誇りを育てる取り組みのこと。その目的は単なるモチベーション向上ではなく、「社員が自ら企業のファンとなり、ブランドの語り手になる」状態をつくることにあります。 いまや採用市場では、企業発信よりも“社員発信”が重視される時代。求職者は求人サイトよりもSNSや口コミを参考にし、「そこで働く人」のリアルな声から企業を判断しています。つまり、インナーブランディングは「採用広報の裏側を支える土台」であり、社員の共感と誇りがそのまま採用力へと転化していきます。
本記事では、採用成果を高めるために欠かせないインナーブランディングの考え方と、社員を巻き込むための実践ステップを解説します。
- なぜインナーブランディングが採用に直結するのか
- 社員を巻き込む3つのステップと具体施策
- 実際に成功している企業の事例と効果
- 「社員が語る会社」をつくるための考え方
“外に伝える前に、内を整える”。この原則こそが、これからの採用ブランディングを強くする最大のカギです。
|
目次 「社員の共感」が採用競争を勝ち抜く最大の武器になる理由
社員を巻き込む3つのステップ
インナーブランディング成功企業の事例紹介
まとめ|社員が語る会社こそ最強の採用ブランド |
SNS採用ブランディングの現状
「社員の共感」が採用競争を勝ち抜く最大の武器になる理由
採用ブランディングを考える上で、インナーブランディングは「内側の強さ」をつくる最も重要な基盤です。どれほど魅力的な採用サイトや広告を制作しても、そこに登場する“中の人”、つまり社員自身がその内容に共感していなければ、言葉にリアリティは宿りません。
企業が発信するメッセージの信頼性は、社員の納得感によって支えられています。採用における「ブランド力」とは、単にデザインやコピーの完成度ではなく、“働く人の誇りと共感がどれだけ言葉に滲み出ているか”で決まるのです。
そして、社員が自らの言葉で会社の想いや文化を語れる状態になったとき、その組織は“生きたブランド”へと進化します。
企業文化の「体現者」が語るからこそ響く
求職者が本当に知りたいのは、企業のスペックではなく、「この会社で働く自分を想像できるかどうか」。その判断材料になるのは、公式な採用ページのテキストよりも、社員のリアルな声や日常の光景です。
つまり、インナーブランディングによって理念や価値観がしっかりと浸透している企業ほど、社員一人ひとりが“採用広報の担い手”になります。
たとえば、社員が自発的にSNSで仕事のやりがいやチームの雰囲気を投稿している企業では、その一つひとつの発信が「採用ブランディングの資産」として機能します。そこには“企業に言わされている”のではない、本音から出た言葉の信頼感があります。
この「自然発信」が生まれる背景には、企業理念への共感と、働くことへの誇りがあります。それこそが、どんな広告よりも強い採用メッセージになるのです。
社員エンゲージメントが応募率を高める
近年のデータでは、社員エンゲージメント(会社への共感・愛着・貢献意欲)が高い企業は、採用応募率が平均1.8倍に向上すると言われています。これは、社員の幸福度や熱量が、外部の印象に直接反映されていることを示しています。
求職者は求人票を読むとき、「この会社の人たちは楽しそうか?」「自分もここで成長できるか?」という“感情的な評価”で応募を決めます。だからこそ、社員が誇りを持って働ける組織文化をつくること自体が、最も本質的な採用戦略です。
採用力を高める近道は、広告投資でも求人強化でもなく、社員が「この会社を好きだ」と心から言える状態をつくることにあります。
「内」が整えば、「外」は自然に強くなる
インナーブランディングは、単なる社内広報活動ではなく、“採用広報の起点”です。理念や価値観が社内に深く根づき、社員が自分の言葉で語れるようになると、企業メッセージは自然と統一され、ブランド発信に一貫性が生まれます。
つまり、外に向けてブランドを“つくる”のではなく、内側からブランドを“育てる”こと。この姿勢こそが、採用競争が激化する時代における最大の差別化要素になります。
どんなに大規模な広告よりも、社員が語る一言のほうが強く響く。それは、「社員が語るブランドこそ、最も信頼されるブランド」だからです。
インナーブランディングは採用の裏方ではなく、企業の未来を形づくる中心戦略。“内なる共感”が“外への共感”を呼び、やがてそれが企業の魅力を何倍にも増幅させます。その循環を生み出すことこそが、これからの採用ブランディングの本質です。

社員を巻き込む3つのステップ
インナーブランディングを採用に結びつけるためには、社員を“受け手”ではなく“共創者”として巻き込むことが重要です。経営層だけが理念を語るのではなく、社員一人ひとりが自分ごととして発信できる状態をつくる。
そのためには、理念の共有から発信促進、体験価値の創出まで、段階的に仕組みを整えることがポイントです。
理念の共有と浸透
最初のステップは、「会社が何を大切にしているのか」を社員全員が同じ温度で理解することです。多くの企業がミッションやバリューを掲げていますが、それが“現場の言葉”として語られていないと、理念はただのスローガンに終わってしまいます。
浸透のために効果的なのは、言葉ではなく体験で理念を伝えることです。たとえば、朝礼や全体会議で経営者が理念を語るだけでなく、社員自身が「理念を体現したエピソード」を共有する時間を設ける。そうすることで、理念が“人の行動”として可視化され、自然と文化として根づいていきます。
また、新入社員研修や評価制度にも理念を組み込み、「理念に基づいた行動が評価される仕組み」を整えることも有効です。社員が「会社の考え方を自分の言葉で語れる状態」こそが、採用ブランディングの出発点になります。
社員のSNS・動画発信の促進
理念が浸透したら、次は社員発信の仕組みづくりです。社員の声は、どんなコピーよりも強いメッセージになります。とくにSNSや採用動画での「社員のリアルな発信」は、求職者にとって最も信頼される情報源です。
そのために重要なのは、「発信のハードルを下げる」こと。たとえば、社内で「#わたしの仕事のやりがい」などのハッシュタグキャンペーンを実施したり、短尺動画のテンプレートを用意して誰でも気軽に投稿できるようにする。
また、SNS発信を評価制度や社内表彰に組み込むことで、発信文化を自然に定着させる企業も増えています。
発信は“強制”ではなく、“共感による自発性”で広がるのが理想です。そのためには、「なぜ自分たちが発信するのか」という目的意識を社員と共有することが欠かせません。
社内イベントによる体験価値の創出
最後のステップは、理念と文化を“体験”として実感できる場づくりです。どんなに理念を言葉で説明しても、体感を伴わなければ浸透は難しくなります。だからこそ、社内イベントやチームプロジェクトを通じて、社員が“文化を肌で感じる瞬間”を設計することが重要です。
たとえば、理念に基づいたボランティア活動、周年イベントでの「社員スピーチ」、部署を超えたアイデアコンテストなど。こうした取り組みは、単なる社内交流ではなく、「自分たちの会社を誇れる瞬間」を増やすインナーブランディング施策です。
体験価値の積み重ねは、社員が“語りたくなる文化”を生むきっかけになります。その結果、社員自身が自発的にSNSで投稿したり、採用イベントで自然に会社の魅力を語れるようになるのです。
インナーブランディングは、言葉の共有から行動の共感へ。この3ステップを継続的に回していくことで、「社員が語るブランド」が育ち、採用の競争優位性を確立していきます。

インナーブランディング成功企業の事例紹介
インナーブランディングを採用戦略に取り入れ、成果を上げている企業には共通点があります。それは「理念を浸透させる仕組み」と「社員が自ら発信したくなる環境づくり」を両立していることです。
ここでは、社員を巻き込んだインナーブランディングによって採用力を高めた3つの企業事例を紹介します。
① 「理念共感」を軸にしたストーリーブランディング
とあるIT企業は、急成長中のITベンチャーです。採用競争が激化する中で、「給与や福利厚生ではなく、共感で選ばれる会社」を目指しました。同社が行ったのは、社員全員による“理念再定義ワークショップ”。経営理念を一方的に説明するのではなく、「自分にとってこの理念はどう意味を持つのか」を社員が言語化する対話型の取り組みです。
その結果、社員一人ひとりが理念に“自分の言葉”を持つようになり、自然とSNSや社内イベントで自発的な発信が増加。「採用サイトよりも、社員の投稿を見て応募した」という声が増え、半年で応募数が約2倍に伸びました。
成功要因は、“理念を語らせる仕組み”にあります。理念を押しつけるのではなく、共に再構築することで、社員自身がブランドの語り手となりました。
② 「社員発信」を文化にした動画ブランディング
この企業は地方の製造業で、若手採用に苦戦していました。そこで導入したのが、「社員Vlogプロジェクト」。社員が自分のスマホで1分間の“仕事のリアル”を撮影し、社内SNSで共有する取り組みです。
この動画を編集して採用サイトやTikTokにも展開したところ、閲覧数が大幅に増加。「地方でもこんなに楽しそうに働いている」「人の雰囲気が伝わる」と話題になり、応募数は前年比180%に。動画を見た求職者の内定承諾率も大幅に上昇しました。
企業の強みは、「発信の主役を社員に委ねた」こと。完璧な映像ではなく、リアルな日常を見せることで、企業への信頼と共感を同時に獲得しました。
③ 「社内イベント」を採用ブランドに転化した企業
サービス業を中心とした中堅企業では、毎年行っていた周年イベントを“社員参加型ブランディング施策”に変え、社員が自ら会社の魅力を語るステージを設けました。「会社の好きなところ」「自分が誇りに思う瞬間」を共有するこの取り組みが、社内の一体感を高めるきっかけに。
さらに、その映像をダイジェスト化して採用動画やSNSで発信したところ、「社員の想いが伝わる」「この会社は温かい」というコメントが相次ぎました。結果、応募数が前年比1.5倍、定着率も上昇。社内外両面でブランドが強化されました。
この会社のポイントは、「社内イベントを外へつなげた」こと。社内文化をそのまま採用ブランディングに転用することで、無理のない“等身大の発信”が実現しました。
これらの企業に共通しているのは、「社員が発信したくなる理由」と「発信できる環境」を同時に整えていることです。理念・発信・体験を一貫したサイクルで回すことで、ブランドの“内側”と“外側”が自然に一致していきます。
インナーブランディングの本質は、社員を「発信のツール」として使うことではなく、社員が誇りを持って語れる企業をつくること。この信頼と共感の循環こそが、強い採用ブランドを生み出す最大の原動力なのです。

まとめ|社員が語る会社こそ最強の採用ブランド
採用ブランディングの成功は、外向きの発信力よりも「内側の共感力」によって決まります。どれだけ洗練された採用動画やSNS戦略を打ち出しても、社員がその内容に共感していなければ、言葉の温度は外部に伝わりません。
一方で、インナーブランディングによって理念が浸透し、社員が自分の言葉で会社を語れるようになると、その発信には“リアルな熱量”が宿ります。そしてこの熱量こそ、求職者の心を動かす最も強力な要素です。
社員がSNSや採用イベントで語る一言、動画に映る何気ない笑顔などはすべて、企業の信頼を形づくる“無形のブランド資産”です。つまり、インナーブランディングとは「社員をブランドの一部にする仕組みづくり」なのです。
採用競争が激化する今、企業が本当に取り組むべきは「どう伝えるか」ではなく、「誰が伝えるか」。社員一人ひとりが誇りを持ち、自発的に発信したくなる文化を育てることが、最も持続的な採用力の源泉になります。
“社員が語る会社”は、どんな広告よりも信頼される。それは一夜でつくれるものではなく、理念・体験・共感を積み重ねた企業だけが手にできる、最強の採用ブランドです。
▶︎関連記事
【完全版】採用ブランディングとは?実践戦略の立案から成功事例・効果測定まで徹底解説

| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。