LLMO時代のSEOとは?生成AIとコアアップデートの相互影響を読み解く
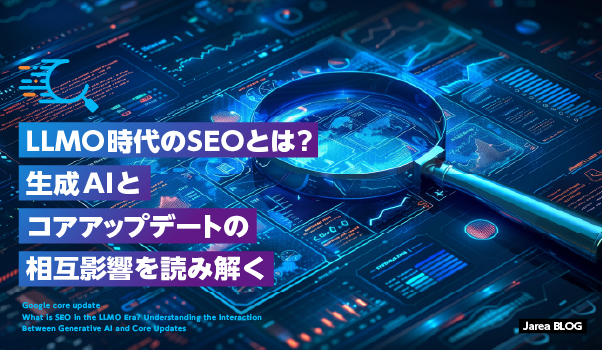
2025年、検索エンジン最適化(SEO)は大きな転換点を迎えています。これまでのように「検索エンジンに好まれる」キーワード対策やリンク構築だけでは、検索上位に位置づけることは難しくなりました。その背景には、Googleが導入を加速させる生成AI技術と、コアアップデートによるアルゴリズムの進化が密接に関係しています。
この新しい時代のSEOでは、ユーザーの検索意図をAIがどう理解し、どう処理するかを前提とした「AIに伝わる設計=LLMO(Large Language Model Optimization)」が不可欠です。本記事では、Googleコアアップデート2025の特徴と生成AIの進化を読み解きながら、今後のSEOで求められる構造・戦略・表現の変化を徹底解説します。
|
目次 |
検索エンジン最適化から「AI最適化」への転換
従来のSEOは、GooglebotがHTMLソースを読み取り、インデックスを構築するという仕組みに最適化していました。しかし、2023年以降の生成AI搭載検索や、MUM・SGEといったマルチモーダル検索の登場により、検索エンジンの中核には“AIが自然文として意味を理解する能力”が組み込まれています。つまり、SEOは「機械への最適化」から、「生成AIへの最適化」へと進化しているのです。
このパラダイムシフトを理解することが、LLMO時代のSEOにおける第一歩となります。
従来SEOと生成AI時代のインデックス構造の違い
従来の検索エンジンは、キーワードの出現頻度やバックリンクの質・数を重視してランキングを決定していました。しかし生成AIの導入以降、Googleは「ナレッジグラフ」や「意味的な関連性」に基づいて文書を理解・評価するようになっています。
特にMUM(Multitask Unified Model)やSGE(Search Generative Experience)のような技術は、単一のページではなくドメイン全体のトピック構造や専門性の一貫性まで評価対象とする点が特徴です。この変化により、見出し構成や内部リンク、文脈整合性といった「構造的理解」が重視されるようになっています。
構造化・文脈・ユーザー行動データの重み付けの変化
生成AIが評価対象とするのは、構造やキーワードだけでなく、ユーザーの行動データ(クリック率、直帰率、滞在時間、クリック深度)を含む「文脈整合性」です。たとえば、検索意図に合致していないページが上位に表示されていても、ユーザーがすぐに離脱すれば、AIはそのページの価値を低く見積もります。
そのため、ユーザー意図に即した構造設計や自然言語としての一貫性あるライティングがより重要になってきています。
GoogleコアアップデートとLLMOの連動ポイント
2025年6月のGoogleコアアップデートでは、生成AIを用いたコンテンツ判定の強化、文脈理解の深化、ナレッジグラフとの整合性の重視が確認されています。これは、AIがインデックスを構築するフェーズで、どれだけ意味のあるまとまりとして理解できるかがランキング要因に含まれてきていることを示唆します。
特に、同一ドメイン内のページ群におけるトピッククラスター戦略の有無や、情報源としての信頼性・一貫性が大きな評価ポイントとなっています。

LLMO時代のSEOに求められる新戦略
生成AIの発展により、検索エンジン最適化(SEO)は従来の“検索アルゴリズムへの対応”という枠を超え、「AIがどう情報を理解し、どう回答を導くか」を視野に入れた新しい戦略設計が必要とされています。特に2025年以降は、Googleのコアアップデートと連動する形で、「Helpful Content System」と「E-E-A-T評価」、さらには「ナレッジグラフとの整合性」までが問われるようになりました。
これは単なるキーワードの埋め込みやリンク施策では通用しない時代が到来したことを意味します。ここでは、LLMO(Large Language Model Optimization)を前提とした新たなSEO戦略の考え方と、実装に向けた再設計の方向性を詳しく解説します。
Helpful Content SystemとAI対応の整合性
Googleが2022年に導入したHelpful Content System(HCS)は、ユーザーの役に立つコンテンツを評価する仕組みであり、2025年のコアアップデート以降は、生成AIやLLM(大規模言語モデル)との整合性も重視されるようになりました。特にHCSは、「誰のためのコンテンツか」「一次情報かどうか」「専門性が伝わるか」といった観点から評価を行い、表面的なSEO対策やAI生成コンテンツだけのサイトに厳しいフィルタリングを行います。
一方、LLMOを意識したコンテンツ設計では、AIが情報を構造的に認識し、意味的に解釈できるかが重要になります。そのため、単なるSEOキーワードの羅列ではなく、文脈整合性・見出し構造・共起語の自然な使用が求められます。たとえば、「Googleコアアップデート2025」というキーワードを含む記事であれば、そのアルゴリズムの背景、影響事例、SEO対応策といったコンテキストを明示することで、AIにとっても“Helpful”な構造になるのです。
SEO担当者としては、E-E-A-TやHCSの基準を満たすことに加えて、AIによる要約や推薦にも耐えうる構造設計を意識する必要があります。これが、検索エンジンと生成AIの両方に評価される新時代のSEOの鍵です。
検索される理由」起点のコンテンツ再設計
従来のSEOでは「どんなキーワードで検索されているか」を起点にしたコンテンツ設計が主流でしたが、LLMO時代においては「なぜそのキーワードが検索されるのか」、すなわち“検索される理由”を起点とした設計が求められます。これは検索ユーザーの意図や背景に深く迫ることを意味し、AIが文脈を解釈する精度が向上した今、より重要性を増しています。
たとえば「SEO 見直し」と検索する人の背景には、「順位が下がって困っている」「最近のGoogleの評価軸が知りたい」「競合が強くなった」など複数の状況が想定されます。このような文脈を的確に捉え、コンテンツに盛り込むことで、AIは“回答に適したページ”と判断しやすくなり、検索結果だけでなくAIチャットツールの参照先としても選ばれやすくなります。
そのためには、FAQ形式の構造化や検索文脈ごとの見出し設定、体験談や事例の挿入など、UXを高める工夫が不可欠です。単に網羅するだけでなく、「このページは今の自分の悩みに答えてくれる」と直感的に思える設計が、LLMOにおける勝ち筋と言えるでしょう。
AIに“伝わる”ページ構造とナレッジグラフ対策
LLMO時代において、AIに「伝わる」構造を持つコンテンツであることが、検索順位やAIリファレンスとしての採用に直結します。そのためには、ナレッジグラフとの親和性を意識した構造設計が欠かせません。
ナレッジグラフとは、Googleが情報同士の関連性を理解するために使うデータ構造であり、人物・企業・用語・場所などがどのようにつながっているかを把握します。たとえば「Googleコアアップデート2025」という概念と、「Helpful Content System」や「E-E-A-T」、「LLMO」といった関連概念を自然文で関連付けて説明することで、AIにとって意味のある“構造的なつながり”が生成されます。
また、hタグ(h2・h3)による階層的な構造、用語の明確な定義、出典の明記なども、AIが理解しやすいコンテンツを構成するための要素です。たとえば「SEOとは?」というセクションで正確かつ簡潔な定義を記載し、その下に具体的な応用や課題、対策を記述するという流れは、生成AIにとっても処理しやすい構造です。
さらに、構造化データ(Schema.org)の活用もLLMO対策には有効です。FAQPageやArticle、HowToなど、文脈に応じた構造化タグを適切に実装することで、検索結果の強調表示だけでなく、AIにとっても理解可能な情報資産となります。

生成AIに強いコンテンツの特徴とは?
生成AI時代において、コンテンツの評価基準は「単にキーワードが含まれている」ことから、「意味の通った文脈の中で、専門性や意図が明確に伝わる」方向へと大きくシフトしています。Googleの評価軸も、生成AIが内容を理解しやすい構造や文体、ナレッジグラフとの連携性といった観点が重視されるようになっており、従来のSEOとは一線を画す対策が求められます。このセクションでは、生成AIと相性の良いコンテンツの特徴を3つの視点から解説します。
エンティティ重視の記述とセマンティックSEO
2025年のコアアップデート以降、Googleは「エンティティ(意味的な概念や固有の情報)」を明確に記述したコンテンツをより高く評価する傾向を強めています。たとえば「福岡のホームページ制作会社」というキーワードであれば、地名・業種・提供サービス・対象顧客といった構造化された情報が文脈に溶け込むように記述されているかどうかが鍵になります。
セマンティックSEO(意味論的SEO)を実現するには、以下の3点がポイントです:
- 主語・述語が明確である自然な日本語での記述
- 「誰に」「何を」「どのように」届けるかが明示された文脈設計
- schema.orgなど構造化マークアップを併用したデータ連携
こうした記述は、人だけでなく生成AIが文脈を理解するためにも不可欠です。ナレッジグラフとの親和性が高まることで、SERP上での表示強化(リッチリザルト)や音声検索での対応力も向上します。
「人が書いたコンテンツらしさ」の担保と表現の工夫
AIによるコンテンツが一般化したことで、Googleは「人間による経験」「独自の視点」「一次情報」に基づく内容をより重要視しています。これがE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)強化の流れにも直結しています。
生成AIに強い=AIらしさを抑えた“人間らしい”表現とは、具体的には次のような工夫です:
- 「私たちのプロジェクトで実践した結果〜」などの体験談を記述
- 事実に基づいた主張と、それに対する理由や背景を丁寧に展開
- 数値や第三者の引用・出典を明記し、論拠の信頼性を担保
特に2025年のアップデート以降は、ユーザーの検索意図に対して「その企業だから語れる情報」かどうかが評価の分かれ目になっています。企業ブログであれば、実績ページや取引実例への内部リンクも信頼性強化に寄与します。

類似AIコンテンツとの差別化ポイント
ChatGPTなどの普及により、「AIで作られた類似コンテンツ」が検索上に氾濫しています。こうした中で、生成AIに強いコンテンツとは、テンプレート化されたものから一歩抜け出し、独自性を打ち出せているかが決定的な差になります。
差別化の観点では、以下の点を意識する必要があります:
- 視点の差別化:業界経験者としての視点、現場の苦労、施策の背景などを丁寧に描写
- 構成の工夫:FAQ構造・ストーリー構造・インタビュー形式など、情報の届け方の多様化
- コンテンツの深度:1見出し1テーマで掘り下げ、400〜800文字以上の解説を基本とする
さらに、内部リンクや補足資料、参考ページの提示により、ユーザーの“次のアクション”まで誘導できる設計が、生成AI・Google双方からの評価を高める鍵となります。
SEOツール・AIツールの最前線|LLMO対応の実用例
生成AIとGoogle検索の進化により、従来型のSEO施策だけでは検索上位を狙うことが難しくなりつつあります。特にLLMO(Large Language Model Optimization)時代においては、「人にもAIにも理解されやすいコンテンツ設計」と、それを支える実用的なツール選定が成果の分かれ目になります。このセクションでは、実際の業務に取り入れやすく、LLMOに対応したSEO&AIツールを紹介し、具体的な活用シーンを通じて最適な組み合わせを解説します。
Clarity・Surfer・Site Explorerなどの活用方法
LLMO対応のSEOにおいては、ユーザーの行動分析・検索意図のマッピング・競合比較といった複数視点の分析が求められます。特に以下のツール群は、実務でのPDCAサイクルを支える中心的存在です。
- 『Microsoft Clarity』(https://clarity.microsoft.com/)無料で使えるヒートマップ&セッション録画ツール。ページ滞在中のマウスの動きや離脱タイミングが視覚的にわかり、UXの改善点が明確になります。
- 『Surfer SEO』(https://surferseo.com/)上位表示されているコンテンツと比較して、自ページの構造やキーワード出現率を最適化。生成AIと連携したコンテンツ調整にも強みを持ちます。
- 『Ahrefs Site Explorer』(https://ahrefs.com/site-explorer)被リンク構造や競合サイトのトラフィック解析に強く、SEOリカバリー時の要因分析にも有効です。
これらのツールは、単体ではなく役割を分けて併用することで、LLMO時代に求められる多角的な分析を実現します。
LLMOに強い生成AI連携ツール(例:NeuronWriter、Frase)
生成AIを活用しながらも、検索エンジンへの適合度を担保するには、LLMOに最適化されたコンテンツ支援ツールの存在が不可欠です。近年注目されている代表的なツールとして、以下が挙げられます。
- 『NeuronWriter』(https://neuronwriter.com/)検索意図の分解、見出し構造の設計、コンテンツスコアの算出など、LLMO対応に必要な最適化項目を自動で提案。ChatGPTとの連携も可能です。
- 『Frase』(https://www.frase.io/)上位コンテンツの要素分析から、構造化されたアウトラインを提案。生成AIとの統合により、クエリ意図に沿った自然な文章生成が可能です。
これらのツールを用いることで、「人が読む文脈」と「AIが理解する構造」の両立を実現でき、2025年以降のGoogle評価に沿ったコンテンツ制作が加速します。
AIとSEOのハイブリッド運用の実務Tips
LLMO時代のSEO施策においては、AIと人間の役割分担が成果の鍵を握ります。以下に、実務で取り入れやすいハイブリッド運用の実践ポイントを紹介します。
- 初期設計は人間がリードする:検索意図・ペルソナ・ビジネス文脈に基づいた戦略設計は人が担当。AIには難しいニュアンスや業界経験が求められる工程です。
- AIは情報整理と補完に活用:見出し構造の下書きや既存情報の要約、競合比較などの「調査・下ごしらえ」をAIに任せることで、作業の効率が向上します。
- 最終チェックは人間が行う:生成されたテキストが検索意図に合っているか、トーンやブランドイメージにマッチしているかの確認と調整は、必ず人間が担うべき工程です。
こうした分業によって、スピードと品質の両立が可能になり、LLMOの基準を満たす高品質コンテンツの量産が現実的になります。

まとめ|これからのSEOは「AI×人間理解力」で進化する
2025年のGoogleコアアップデートとLLMO(Large Language Model Optimization)の時代を迎え、SEOはかつての「検索エンジンのルールに従う技術」から、「AIに正しく理解されるコンテンツ構造」と「人の意図に寄り添う情報設計」を両立するハイブリッドな領域へと進化しました。
これからのSEOでは、単にキーワードを詰め込むのではなく、AIが背後で解析しているナレッジグラフやエンティティ構造を意識した“意味のある文脈”で記述することが求められます。そしてその文脈こそが、「検索する人間の意図」に正しく応えるための鍵であり、企業の持つ一次情報や専門性がそのままE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)として評価される軸となります。
LLMO時代のSEO成功の本質とは、「AIファーストではなく、人間ファースト」を貫きながらも、AIに正しく伝える文法と構造を持ち合わせたコンテンツ運用にあるといえるでしょう。
Googleの評価軸はAIの裏にある“人間の問い”にある
Googleは検索アルゴリズムにおいて、常に「ユーザーの検索意図に最も合致するコンテンツ」を最上位に表示することを目指しています。これは、2022年以降に強化されたHelpful Content System(HCS)においても明らかです。HCSは、「人が見て役に立つコンテンツか」を主軸とした評価システムであり、生成AIによる量産的なコンテンツや、SEO対策だけを目的としたテキストには厳しい評価を下す傾向が顕著に見られます。
つまり、AIで生成された文章であっても「人間の知識・経験・問題意識に基づいて書かれているか」が重要であり、Googleはその背後にある“問い”の質を評価しています。これは、人間の検索行動の本質に近づくという意味であり、企業側もこの姿勢を理解し、表面的なテクニックではなく本質的な課題解決を軸にした情報提供が求められます。
企業がLLMO時代に取り組むべきSEO戦略の方向性
LLMOの潮流が進む今、企業が取り組むべきSEO戦略は次のような方向性に整理できます:
- 「ユーザーが知りたいこと」ではなく「ユーザーがなぜ知りたいか」に焦点を当てる:検索キーワードの背後にある目的や不安・関心を想定したコンテンツ設計が鍵になります。
- ファクトベースの一次情報を中心とした信頼性の高い記述:企業独自の経験、データ、事例、取材などのコンテンツが評価されやすくなります。
- AIに構造的に伝わる設計の徹底:意味のあるhタグの階層構造、定義の明確化、セマンティックな記述、関連コンテンツとの内部リンクなど、AIが論理的に情報を把握しやすくする施策が欠かせません。
- SEOチームとコンテンツチーム、開発チームの横断的な連携体制の構築:AI時代のSEOでは、構造設計、ナレッジ管理、ブランド文脈の理解といった複数の視点が必要となるため、部門横断型のワークフロー設計が成果の分かれ目になります。
- 生成AIツールを活用したコンテンツ改善・実験の内製化:AIによる仮説検証、トーンの調整、記事構造の最適化などを効率的に行える体制を構築することも重要です。
これからのSEOとは、技術と構造の力でAIに正確に伝える「翻訳力」と、人間の問いに応える「理解力」を兼ね備えた新たな専門領域として進化しています。
●検索評価の進化に打ち勝つためのGoogleコアアップデート2025完全ガイド

| WRITER / Yigg 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 WEBコーダー 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。