クチコミ促進機能の進化|AIレビューアンケートで依頼文を自由に編集する方法とは?
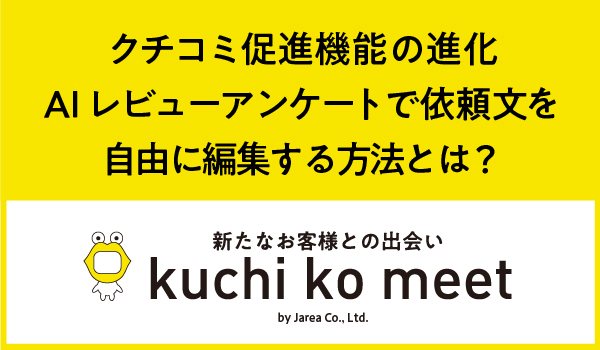
ユーザーからのクチコミは、Googleビジネスプロフィール(GBP)において店舗の信頼性を高め、検索順位や集客効果に大きな影響を与える要素の一つです。しかし、いざ「クチコミを増やしたい」と思っても、ユーザーに自然な流れで投稿してもらうことは簡単ではありません。
そこで注目されているのが、MEO対策ツール「クチコミート」に搭載されたクチコミ促進機能。中でも、レビュー投稿をスムーズに誘導する「AIレビューアンケート」の利便性が向上し、2025年、新たにレビュー依頼文の編集機能が追加されました。
本記事では、この新機能の概要と具体的な設定方法、効果的なレビュー依頼文の書き方、さらに多言語対応の活用ポイントまでを網羅的に解説します。投稿率を高め、ユーザーの声をブランド資産に変えるための一歩として、ぜひご活用ください。
|
目次
多言語レビュー依頼にも対応|インバウンドや外国人対応にも有効
|
クチコミ促進機能とは?
ユーザーの自然な投稿を促すためには、単に「レビューを書いてください」とお願いするだけでは不十分です。多くの店舗運営者が抱える悩みは、「良い体験をしてくれた顧客がいても、レビューにつながらない」こと。これは投稿のハードルが高いのではなく、投稿までの“導線”や“誘導の仕方”に改善の余地があるケースがほとんどです。
こうした課題を解決するために開発されたのが、クチコミートの「クチコミ促進機能」です。アンケートと連動しながら、ユーザーの声を収集し、スムーズにGoogleレビューへとつなげていくこの仕組みは、投稿率の向上だけでなく、投稿内容の質にも好影響を与える設計となっています。
ここでは、クチコミ促進機能の基本的な考え方と、中心となる「AIレビューアンケート」の役割、そして今回アップデートされた“依頼文の設計”が持つ効果について解説します。
Googleビジネスプロフィールにおけるクチコミの影響力
Googleビジネスプロフィールは、いまやユーザーの来店・来院・予約といった行動の起点となる情報源です。そしてその中でも「クチコミ」は、第三者視点での信頼性を担保する重要な指標として、アルゴリズム上でもユーザー心理上でも大きな役割を果たしています。
たとえば、星の数だけでなく、投稿内容の具体性や新しさ、件数の多さが重視されており、MEO(ローカルSEO)施策において最も手ごたえが出やすいのが“クチコミ強化”といっても過言ではありません。
しかし、実際にクチコミを書いてもらうには、顧客の体験を言語化し、投稿へ導く導線設計が必要です。
「AIレビュー生成アンケート」とはどんな機能か
クチコミートの「AIレビューアンケート」は、ユーザーにアンケート形式で体験内容を尋ね、その回答をもとにAIが自動でレビュー文を生成する仕組みです。
たとえば、「料理はいかがでしたか?」「スタッフの対応はいかがでしたか?」など、複数の質問に答えてもらうことで、ユーザーの体験を“言葉”に変換しやすくする=クチコミ投稿への心理的ハードルを下げることができます。
回答完了後には、自動生成されたレビューを確認し、そのままGoogleのクチコミ投稿画面へとスムーズに遷移。ユーザーにとっても「書きにくい」という心理的障壁が減り、店舗側にとっては“伝えたい体験”が反映されたクチコミが蓄積されやすくなります。
なぜ投稿依頼文の設計が成果を左右するのか
アンケート回答後に表示されるレビュー投稿依頼文は、ユーザーに「投稿してみよう」と思ってもらうための“最後のひと押し”となる重要な要素です。
従来はこの部分の文言が固定されていましたが、今回のアップデートによって店舗ごとのトーンや顧客層に合わせて文面を自由に編集できるようになったことで、より柔軟で効果的なレビュー誘導が可能になりました。
たとえば、カジュアルなお店であれば「ぜひ一言、感想をお聞かせください!」というラフな表現、医療系の施設なら「あなたの声が、他の患者様の安心につながります」といった共感ベースの文言など、投稿率が高まる表現を試行錯誤しながら最適化できます。
クチコミ促進機能の真価は、こうした“言葉のチューニング”によって、ユーザーの行動が自然に引き出せる点にあります。

新機能「レビュー依頼文の編集」とは
2025年に新たに追加された「レビュー依頼文の編集機能」は、AIレビューアンケートを利用した後に表示されるレビュー投稿の依頼画面の文章を自由にカスタマイズできる機能です。ユーザーにとってはレビュー投稿へ進む最後のステップであり、ここの文言ひとつで投稿率や内容の質が大きく変わることもあります。
従来のようにテンプレートに頼るのではなく、ブランドや接客スタイル、ターゲットユーザーに合わせて、より“その店らしい言葉”でレビュー依頼ができるようになったことで、クチコミ促進機能は新たな段階へと進化しました。
ここでは、編集できる文言の対象範囲、個店・グループ単位での活用方法、そして複数アンケート運用時の注意点について詳しく解説します。
どの部分の文言が編集できるのか?対象範囲の整理
編集可能なのは、AIレビューアンケートの回答後、Googleクチコミ投稿画面に遷移する直前に表示される「レビュー投稿のお願い」画面における誘導文です。
この部分は、ユーザーがレビュー投稿を迷っているタイミングで表示されるため、心理的に非常に大切なポイント。
文面としては、たとえば、
- 「ご協力ありがとうございました。ぜひ以下よりご感想をご投稿ください」
- 「あなたの声が、他のお客様の参考になります」
- 「投稿は数十秒で完了します。ぜひ一言だけでもご記入ください」
などの表現にカスタマイズできます。店舗の業種や顧客層、ブランドトーンに合わせた言葉選びが可能です。
なお、現時点ではGoogleレビューへの遷移時のみが編集対象であり、MEOツール内部でのレビュー遷移前文面の編集は今後リリース予定となっています。
個店・グループどちらでも設定可能
このレビュー依頼文の編集機能は、個店ごとの設定にも、グループ全体での一括設定にも対応しています。
個店管理画面でもグループ管理画面でも「アンケート一覧」から「AIレビューフォーム設定」を開き、そこで文言を自由に入力することが可能です。
ブランド統一感を重視したい場合にはグループ設定を活用し、エリアや業態によって表現を変えたい場合は個店単位で運用するといった柔軟な管理が可能です。
複数アンケートでも1文面で管理|仕組みの注意点
アンケートが複数存在する場合でも、レビュー依頼文はその店舗単位で1つの共通文面として管理されます。
つまり、「A商品用アンケート」「Bサービス用アンケート」といった複数のフォームがあっても、表示されるレビュー依頼文は同一です。
そのため、アンケートの目的や属性が大きく異なる場合は、事前にどの表現がすべての顧客に違和感なく届くかを考慮したうえで、より汎用性の高い文面設計を心がけることがポイントです。
また、一度でもアンケートが配信・回答されていると文面の変更ができない仕様のため、初期設定時には十分にプレビュー確認を行うことが推奨されます。

多言語レビュー依頼にも対応|インバウンドや外国人対応にも有効
レビュー依頼文の編集機能では、日本語だけでなく複数言語での表示・編集にも対応しています。特に訪日外国人観光客や多国籍ユーザーが利用する宿泊施設・観光業・飲食店にとって、多言語対応はクチコミ促進の成功を左右する要素になりつつあります。
この機能では、日本語で作成したレビュー依頼文をベースに、自動翻訳で他言語に展開される仕組みを採用。また、必要に応じて言語ごとに手動で文言を最適化することも可能です。
以下では、自動翻訳のフローと手動編集の方法、そして導入時に注意すべきポイントについて解説します。
日本語で作成→自動翻訳されるフロー
まず日本語でレビュー依頼文を作成し、「登録する」ボタンを押すと、システムが多言語設定に基づいて自動翻訳を実行します。翻訳結果は数秒程度で処理され、設定画面内の多言語タブにそれぞれの翻訳結果が反映されます。
自動翻訳される言語は、管理画面で事前に設定されている「対応言語」によって変わります。たとえば英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、タイ語、フランス語など、インバウンド需要の高い主要言語に標準対応しているのが特長です。
各言語ごとの手動編集も可能
自動翻訳だけでなく、各言語のタブごとにレビュー依頼文を手動で個別編集することも可能です。
翻訳のニュアンスを調整したい場合や、より親しみやすいトーンで伝えたい場合には、手動編集が有効です。たとえば英語であれば「We’d love to hear your feedback!」、韓国語なら「후기를 남겨주시면 큰 도움이 됩니다」など、文化や言語ごとの表現に合わせてチューニングできます。
編集後は「登録する」ボタンで反映され、実際のアンケート画面にプレビュー表示されるため、完成形を事前に確認しながら調整できる安心設計です。
アンケート回答後は編集不可なので事前チェック必須
注意点として、一度でもそのアンケートが配信され、ユーザーによって回答された場合、その後に依頼文の編集はできなくなります。
そのため、初回設定時には必ずプレビュー画面で表示内容を確認し、全対応言語で違和感のない表現かどうかを慎重にチェックしておく必要があります。
特に多言語対応を行う場合、直訳的な表現ではなく「読み手の文化に即した自然な文言」であるかどうかが、投稿率を左右するポイントになります。事前に社内のネイティブ担当者や翻訳チェックのプロセスを設けておくと、より効果的です。
多言語対応レビュー依頼は、単なる翻訳ではなく「その言語の文脈で心地よく読まれる表現」を設計することが、インバウンド戦略の鍵となります。

投稿率を上げるレビュー依頼文の書き方|実践テンプレ付き
クチコミ投稿を促すには、単に「書いてください」とお願いするだけでは不十分です。ユーザーの心理に寄り添ったメッセージ設計が必要であり、それが投稿率に大きく影響します。
今回追加された「レビュー依頼文編集機能」により、文言を自由に調整できるようになったことで、各業種・業態に応じた最適な依頼文の作成が可能になりました。ここでは、実際の投稿率向上を狙うための文言設計のポイントと、すぐに使えるテンプレートをご紹介します。
「お願い」より「共感」を引き出すワード設計のコツ
ユーザーにレビューを書いてもらうには、「お願いベース」よりも「共感ベース」でのアプローチが効果的です。たとえば「ご協力をお願いします」ではなく、「〇〇さんのお声が、私たちにとって何よりの励みになります」といった文言が、心理的ハードルを下げます。
また、以下のようなポイントを盛り込むと投稿率が高まる傾向にあります。
- 具体的な体験への言及:「〇〇の味はいかがでしたか?」
- お客様の声が活かされていることの明示:「いただいたご意見はサービス改善に活かしております」
- 投稿による影響の強調:「お客様の声が、他の方の参考になります」
テンプレ①:飲食店向け(自然な誘導)
ご来店ありがとうございました!
よろしければ、料理や接客について感じたことを教えていただけると嬉しいです。お客様の声が、私たちのお店づくりの大きな力になります。
カジュアルかつ前向きなトーンを意識し、「書きやすさ」を重視した構成にすることで、日常的な利用客にも響きやすくなります。
テンプレ②:医療・美容向け(安心感+簡潔さ)
本日はご来院(ご来店)ありがとうございました。
今後の施術や対応の参考にさせていただきたいので、もし気になった点や良かった点があれば、ぜひお聞かせください。皆様のご意見が、より良いサービスづくりにつながります。
プライバシーや丁寧さを重視する業種では、礼儀正しい口調と安心感を与える言葉選びが効果的です。
テンプレ③:観光・宿泊施設向け(体験共有の促し)
ご宿泊いただき、誠にありがとうございました。
滞在中に印象に残ったことやおすすめの体験があれば、ぜひシェアしてください。お客様の旅の声が、次に訪れる方の旅のヒントになります。
旅の余韻を活かし「誰かの参考になる」という文脈を加えることで、レビューを書く動機を自然に促す設計となります。
設定方法と管理画面の使い方(操作手順付き)
クチコミートの「レビュー依頼文編集機能」は、非常に簡単な操作で設定・管理ができるよう設計されています。とはいえ、実際に設定を行う担当者が多店舗の運用や外国語対応も視野に入れる場合、「どこで編集すればよいのか」「どのタイミングで保存すればいいのか」「どの言語に対応しているか」といった基本操作をしっかり把握しておくことが重要です。
このセクションでは、アンケート一覧画面からの導線や、編集〜保存〜多言語対応まで、実際の画面操作に沿って手順を紹介していきます。特に初めて使う方や、多言語運用を行いたい店舗担当者の方にとって、迷わず操作できるよう、丁寧にポイントを整理しています。


アンケート一覧画面から「AIレビューフォーム設定」へ
設定の第一歩は、「アンケート一覧」ページから始まります。ダッシュボード上のナビゲーションで「クチコミ促進アンケート」セクションにアクセスすると、過去に作成したアンケートが一覧表示されます。
一覧の中から編集したいアンケートを選択すると、画面右上に表示される「AIレビューフォーム設定」ボタンが、レビュー依頼文の編集機能にアクセスする入り口です。このボタンをクリックすると、言語ごとに編集可能な文面管理画面へと遷移します。
ポイント:AIレビュー機能を活用しているアンケートのみ、「AIレビューフォーム設定」ボタンが表示されます。通常アンケートにはこのボタンは存在しませんので、事前に確認しておきましょう。
文面の編集→保存→プレビューの流れ
編集画面に入ると、各言語ごとに設定タブが並んでいます。初期状態では自動生成されたレビュー依頼文が日本語で表示されます。
ここでの操作の基本ステップは以下の3つです。
-
文面の編集
表示されたテキストエリア内に、希望する文面を自由に入力・修正できます。句読点の整備や語尾の調整なども可能です。
-
保存ボタンで確定
編集が完了したら、画面右下にある「保存」ボタンをクリックします。これで設定内容が確定し、アンケート送信後に表示される文面が更新されます。
-
プレビューで表示確認
保存後、隣接する「プレビュー」ボタンから、実際のユーザーに表示されるレビュー依頼文の見え方を確認できます。モバイル画面を模した表示なので、文量のバランスや視認性をリアルにチェックできます。
補足:レビュー依頼文は、アンケート回答後に自動で表示される形式です。プレビューはその確認手段として非常に便利なので、必ず保存後に一度チェックしておくことを推奨します。

多言語タブの切替・登録の注意点
インバウンドや外国人対応のために、レビュー依頼文は多言語での運用が可能です。日本語での編集を起点に、画面上部にある言語タブを切り替えることで、各国語ごとに文面の確認・修正ができます。
- 🇺🇸 英語
- 🇰🇷 韓国語
- 🇨🇳 簡体字中国語
- 🇹🇼 繁体字中国語
- 🇹🇭 タイ語
言語タブを切り替えると、自動翻訳された文面がそれぞれ表示されます。必要に応じて現地語ネイティブチェック済みの文面に差し替えることもできます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- アンケート回答前に編集を完了させること
一度アンケートが公開されてユーザーの回答が入ると、該当アンケートのレビュー依頼文はロックされ、編集不可になります。 - 翻訳内容の文脈確認を必ず行うこと
自動翻訳には表現のブレや直訳感が残る場合があるため、特に敬語表現や業界特有の用語が含まれる文面は注意深くチェックしましょう。
補足:自動翻訳は初回の下地作りにとても便利ですが、「文法的に正しいか」よりも「ユーザーに親しみやすいか」「レビューを書きたくなるか」という観点で再編集するのが成果への近道です。
このように、「レビュー依頼文の編集機能」は、直感的なUIとシンプルな導線で、初めての担当者でもすぐに使いこなせるようになっています。特にグローバル対応が求められる店舗にとっては、インバウンド対応の一環として、重要な役割を果たすことになります。


まとめ|“依頼の仕方”でクチコミの質も量も変わる
クチコミ数を増やすための施策として、「レビュー依頼文の改善」はもっとも“取り組みやすく、成果が出やすい領域”の一つです。これまで多くの現場では、「レビュー依頼」という行為自体が後回しにされがちでしたが、最近ではMEOやSNS流入の強化、さらには生成AI活用によるUGC評価の重要性が高まったことで、その必要性は再認識されています。
クチコミートでは、ただレビュー依頼文を編集できるだけでなく、「体験の直後」「文脈に合った誘導」「多言語による自然な提示」といった投稿体験そのものを設計できる機能が整っています。本セクションでは、その総まとめとして、クチコミ獲得における“依頼文設計”の本質と、今後のツールの進化についても触れていきます。
自然な投稿体験の設計がクチコミ数の差を生む
レビュー依頼文の効果を最大化するポイントは、「いかに自然な流れで投稿へとつなげるか」にあります。ユーザーはあくまでサービス体験の延長としてレビューを書くのであって、強制的に書かされると感じると、離脱やネガティブ投稿の原因にもなりかねません。
たとえば、以下のような差で投稿率に顕著な違いが出ます。
- ❌「レビューをお願いします」だけの文面
- ✅「本日ご来店いただいた感想を、ぜひお聞かせください」+名前や体験の要素に寄り添った言葉
クチコミートでは、アンケート→レビュー誘導の一連の流れが設計できるため、「文面の最適化」だけでなく「体験全体の設計」によって投稿数を増やすことが可能になります。
ブランドごとの表現に合わせて文章も最適化を
ブランドや店舗のキャラクターに合わせて、レビュー依頼文のトーンや表現を最適化することも非常に重要です。
- ファミリー層が多い店舗 → 優しく・親しみやすい語り口
- 高級志向の美容・医療系 → 丁寧で品のある語調
- 観光系やエンタメ施設 → ワクワク感や感動体験の共有を促す文言
一律のテンプレートではなく、自社ブランドの「雰囲気」や「接客スタイル」に合わせて文面を調整することで、ユーザーの“投稿意欲”を引き出すことができます。これはマーケティングで言うところの「ブランドトーンの統一」であり、MEO対策であってもブランディング視点が求められるという好例です。
今後の進化(MEOツール内レビュー依頼文の編集予定)にも注目
現在はクチコミートの「アンケートフォーム」からレビュー誘導を行う形ですが、今後のアップデートでは、MEO Dashboard(Googleビジネスプロフィール連携画面)上でもレビュー依頼文をカスタマイズできる機能の追加が予定されています。
これにより、次のような新しい体験設計が可能になります。
- SMSやLINE経由でのクチコミ依頼文にブランド文脈を反映
- 店舗ごとにAIパーソナライズされた文面の自動提案
- 多言語・多チャネルでの一貫したレビュー誘導フローの構築
クチコミートは単なるレビュー収集ツールではなく、「投稿体験の設計」を通じてファンを育て、信頼を集める“ブランディングツール”へと進化しています。これからのレビュー施策は、“お願いする”ではなく“共感を引き出す”時代。ぜひツールの拡張にも注目しながら、投稿体験を自社らしく設計していきましょう。

口コミはもはや「評価」ではなく、ブランドと顧客をつなぐ大切な接点であり、企業の成長を左右する重要な資産です。株式会社ジャリアでは、GoogleビジネスプロフィールやSNS上の口コミを戦略的に活用するためのツール「クチコミート」を提供しています。
多地点での順位管理、競合比較、構造化データの最適化までをワンタグで連携し、クチコミ施策を“集客につながるブランディング”へと進化させる支援を行っています。口コミをただの評価に終わらせず、自社の価値を伝える力に変えたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。