クチコミ促進の次なる一手|食べログ連携で広がるMEO分析の可能性
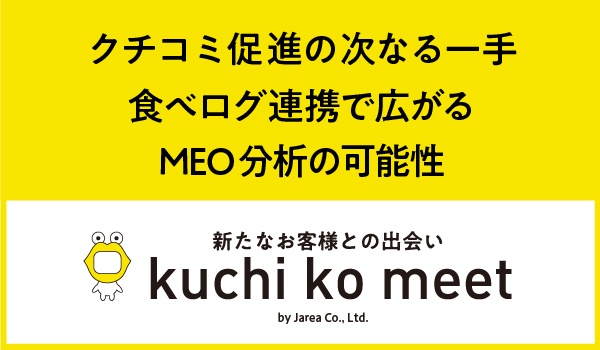
多くの飲食店がGoogleビジネスプロフィール(GBP)によるMEO対策に取り組む中で、見落とされがちなのが「食べログ」の存在です。検索結果にはGoogleのクチコミだけでなく、食べログの評価やレビューも同時に表示され、ユーザーの来店判断に大きな影響を与えています。しかし、これまで多くの店舗ではGoogleと食べログを別々に管理し、分析の手間や精度に課題を抱えていました。
そこで今回、クチコミ一括管理ツール「クチコミート」が新たに食べログ連携に対応。Googleと食べログのクチコミデータを一つのダッシュボードで比較・分析できるようになり、飲食店にとってMEO対策の幅が一気に広がります。この記事では、連携機能の具体的な内容と導入メリット、そして設定方法までを網羅的に解説。飲食店の広報・運営担当者が今すぐ活用できる実践的な情報をお届けします。
|
目次
|
食べログ連携機能とは?
飲食業界におけるMEO対策は、もはやGoogleビジネスプロフィール(GBP)だけでは不十分です。来店前の意思決定において、ユーザーはGoogle以外にも「食べログ」などのグルメ系レビューサイトを必ずと言っていいほどチェックしています。とくに都市部では、食べログの評価点が来店に直結する傾向も強く、無視できない存在です。
こうした中、クチコミートでは新たに「食べログ連携機能」をリリース。Googleと並列で、食べログの評価傾向やレビュー内容をダッシュボード上で可視化できるようになりました。これにより、MEOとブランディングの両面からレビュー戦略を設計することが可能となり、飲食店の集客力を一段階引き上げる施策が現実的になります。
なぜ「Googleだけ」では足りないのか
多くの店舗がGBPに注力する一方で、食べログやホットペッパーグルメなど、他媒体のレビュー管理は後回しにされがちです。しかし実際には、ユーザーがGoogleマップでお店を検索すると、検索結果に他媒体のクチコミや点数が同時に表示されます。
たとえば、Googleで高評価でも食べログでの点数が低ければ、比較される中でネガティブな印象を与える可能性も。情報の“非対称性”がブランド毀損につながるのです。
また、Googleのレビューは新しさや頻度が重視される傾向がありますが、食べログでは文脈や料理ジャンルに対する言及が重視されるなど、評価軸が異なります。このような特性の違いを踏まえたうえで、両媒体を横断的に分析できる環境整備が求められているのです。
「食べログ」のレビューがMEOに与える影響
MEO対策は「地図で上位表示させる」だけではなく、クリック率や実際の来店・予約にまでつながる一連の流れを含めて考える必要があります。この中で食べログのレビューは、以下の2つの面から大きな影響を与えます。
- 検索画面の視認性:Google検索結果のナレッジパネルやローカルパックに、食べログの点数やレビュー件数が併記される場合があります。これにより、ユーザーが食べログにアクセスする可能性が高まります。
- 比較検討の対象:Googleのレビューに加えて、食べログの内容までチェックしてから判断するユーザーが増えています。特に“外食慣れ”した層にとっては、食べログの評価点が「信頼指標」として機能しているケースも少なくありません。
したがって、Googleのみに対応している店舗と、Google+食べログの両方で情報設計されている店舗では、同じ検索順位でも“選ばれ方”がまったく異なります。
クチコミートの連携機能の概要
クチコミートの食べログ連携機能は、Googleビジネスプロフィールと並列で、食べログの最新クチコミや評価推移を自動取得・可視化できるダッシュボード機能です。特に以下の点が大きな特徴です。
■店舗基本情報
- webサイトURL
- SNS連携プロフィール(Facebook、Instagram、Xのみ)
- 営業時間:日~月
- PR文タイトル(新規)
- PR文詳細(新規)
- 営業時間:祝日、祝前日、祝後日(新規)
- 属性:支払い情報(新規)
■クチコミ管理
- クチコミの取得
- クチコミの返信
■飲食店メニュー
- メニューの追加、削除
これにより、媒体ごとの評価傾向の違いや、投稿ユーザーのトーンの変化など、これまで感覚に頼っていた部分を数値とテキストで客観的に把握できます。とくに、「食べログでは高評価なのにGoogleでは低評価」といったギャップの原因分析にも役立ち、次の施策設計に生かせる実用性の高い機能です。

新機能でできること|5つのチェックポイント
クチコミートの「食べログ連携機能」は、ただレビューを横断的に見られるだけではありません。飲食店の広報・MEO担当者が、実際の運用に活かせるように設計された5つの分析&活用機能を搭載しています。
ここでは、それぞれのポイントを解説していきます。
① 食べログ店舗IDの登録で自動連携
まず最初に行うのは、クチコミート管理画面に「食べログ店舗ID」を登録するだけ。これにより、毎日最新のレビュー情報が自動取得され、ダッシュボードに反映されるようになります。
取得されるデータは、評価点・投稿件数・投稿内容などで、手動でのスクレイピングや転記は不要です。複数店舗を管理するチェーン店などでは、各店のIDを一括で登録することで、全拠点のレビュー傾向を統合的に把握できる仕組みになっています。
今後のアップデートでは、ジャンルや価格帯などの店舗属性をもとにしたレビュー比較も予定されており、分析の幅がさらに広がる見込みです。


② ハイライトワードで感情傾向を可視化
クチコミート独自の強みである「ハイライトワード分析」は、レビュー投稿内で頻出するキーワードを自動抽出し、ポジティブ/ネガティブの傾向別に分類する機能です。
これが食べログ連携でも対応可能となり、「美味しい」「コスパ」「接客が丁寧」「待ち時間が長い」など、来店者が何に言及しているのかが一目で把握できます。
この機能により、レビューの件数や点数だけでは掴めなかった「ユーザーの体験価値」が明確になり、接客指導やメニュー改善といった現場レベルの改善に活かせるインサイトが得られます。
感情分析エンジンは今後さらに精度向上が予定されており、「主観を排した改善提案」が可能になる強力な武器となるでしょう。
③ 前月・5ヶ月推移データの比較が可能に
ダッシュボードでは、レビュー件数と評価点の月別推移をグラフ化して表示。これにより、「今月は件数が増えたが評価点が下がった」「改善施策後にポジティブワードが増えた」など、時系列での変化を視覚的に捉えることができます。
特に便利なのが、直近5ヶ月分のデータを横並びで比較できるスナップショット形式。これにより、クレーム発生後の回復状況や、キャンペーン後のレビュー反応などを追跡しやすくなり、社内報告や改善サイクル(PDCA)の可視化に非常に役立ちます。
Googleと食べログのデータを“横断的かつ時系列”で確認できることで、これまで以上に立体的なMEO戦略の立案が可能になります。
④ ダウンロードで社内共有や報告書にも活用
クチコミートのダッシュボードで表示されるレビュー分析データは、CSVファイルとしてワンクリックでダウンロード可能。この機能により、店舗会議用の資料作成や月次報告書への添付、エリアマネージャーや本部への共有もスムーズに行えます。
特に本部・FC本部などが全国の店舗のレビュー戦略を統括する際、「全店横断で共通するネガティブ傾向」や「エリア別に異なるポジティブ評価」を抽出して施策に落とし込むことが可能です。
分析結果をベースに「現場の課題」を見える化できる点が、クチコミートならではの利点です。
今後は、グラフ付きPDFレポートの自動生成にも対応予定で、マーケティング資料としての活用性がさらに高まります。
⑤ 「良い/ふつう/良くない」の分類対応
取得されたレビューは、クチコミート上で独自に「良い」「ふつう」「良くない」の3段階に分類表示されます。これはAIによる自然言語処理(NLP)によって、評価点や表現内容をもとに分類されたもので、感情の振れ幅を定量化するための補助的な指標です。
この分類により、「☆3.5だけど内容はポジティブ」「☆4.0だけどトーンは厳しい」といった“数字と文脈のズレ”を補正して把握できるのが特長です。
MEOにおける改善の優先順位を決めるうえでも、「数は多いが内容が薄い良いクチコミ」よりも、「数は少ないが改善点が明確なふつうクチコミ」に注目するなど、より戦略的なレビュー運用が可能となります。

飲食店にとってのメリットとは?
クチコミートの「食べログ連携機能」は、単にレビューを一覧表示するツールではありません。ユーザーのリアルな声を戦略的なインサイトとして活用できるように設計されています。特に、店舗単位での改善から、グループ本部による戦略立案まで、幅広い飲食事業者にとって有益な視点を提供します。
レビューを「点」から「傾向」に変える分析軸
従来のレビュー閲覧は、個別のコメントや☆評価を「点」として確認するのが一般的でした。しかし、個別の声をそのまま受け止めても、店舗運営の本質的な改善にはつながりにくいものです。
クチコミートでは、「ハイライトワード」と「感情傾向」の可視化により、複数のレビューを束ねて“傾向”として分析することが可能になります。
たとえば、「コスパが良い」「味付けがちょうどいい」というポジティブ傾向が多いエリアでは、その強みをより訴求するプロモーションが有効です。一方で、「接客が冷たい」「待ち時間が長い」といったネガティブ傾向が目立つ場合は、人的配置やオペレーション改善の優先度が明確になります。
このように、レビューを“感覚”ではなく“根拠ある施策の起点”として活かせるのが、クチコミート導入の大きな利点です。
多店舗管理での活用|グループ本部の戦略設計に
飲食チェーンやフランチャイズ事業を展開する企業にとって、多店舗のレビュー傾向を一括で分析できる環境は非常に重要です。
クチコミートでは、店舗ごとのレビュー件数・評価推移・ハイライトワードの傾向を一元管理できるため、グループ全体の運営戦略に直結する「見える化」が実現します。
たとえば、「地域ごとにレビューの質が異なる理由」を読み解くことで、エリア別のマーケティング戦略や指導方針の最適化が可能になります。また、新規出店エリアの選定にも、既存店のレビュー傾向を活かした需要予測が応用できるでしょう。
さらに、定量的なデータはFC加盟店へのレポートや指導にも使いやすく、“納得感のある本部施策”の設計につながります。食べログという第三者評価を用いた信頼性の高い分析は、現場との対話をスムーズにする材料としても機能します。
設定方法と連携の手順
クチコミートの「食べログ連携機能」は、簡単3ステップで設定可能です。初回設定後はレビューが自動取得されるため、毎回の手動確認や登録作業は不要。ここでは、具体的な登録方法から、連携トラブル時の対処法までをわかりやすく解説します。
食べログIDの登録方法
最初のステップは、食べログ上での各店舗のURLを確認することから始まります。クチコミートの管理画面内にある「店舗設定」画面にて、以下の手順で連携が可能です。
- 店舗ごとに該当する食べログページのURLをコピー
- クチコミート管理画面の「店舗編集」メニューへ
- 「食べログ連携ID」欄に、該当ページの店舗ID(URL末尾の英数字)を貼り付け
- 保存ボタンをクリック
この手順を完了することで、当該店舗のレビュー情報が、クチコミート内に定期的に自動連携されるようになります。
初回登録後の自動取得フロー
食べログIDを登録した時点で、クチコミート側が自動的にレビューを取得・解析します。取得データは下記のような形式で自動反映されます。
- 最新レビュー5件
- ハイライトワード抽出(例:「味が濃い」「コスパ良し」など)
- 星評価(3分類:良い/ふつう/良くない)
- 感情傾向の可視化グラフ
- 過去5ヶ月の推移データ
これにより、毎月のレビュー状況が“手間なく”見える化され、改善や報告資料にすぐ活かすことができます。
また、連携設定済みの店舗は、以降も自動でデータを取得・更新し続けるため、常に最新情報が反映されたダッシュボードを保つことができます。
連携がうまくいかない場合のチェックポイント
まれに、連携が正しく動作しないケースも存在します。主な原因とチェックポイントを以下にまとめました。
- 誤ったURLを登録している
→「https://tabelog.com/〜」の正規の店舗ページURLであることを確認。 - URLから抽出されたIDが無効
→ 店舗ページが一時的に非公開・削除されていないかチェック。 - ネットワーク・ブラウザ不具合
→ 異なるブラウザで再試行 or 時間をおいて再設定。 - 旧仕様のURLで登録している
→ リダイレクトURLではなく、現在使用されているURLを再登録。
上記を確認しても解決しない場合は、管理画面右上の「サポート」メニューよりお問い合わせいただけます。クチコミートのサポートチームが直接調査・対応いたします。
クチコミ管理
①食べログのタブを追加
②星評価に星半分を追加。総合評価の少数点以下が0.5以上0.0未満の場合星半分となる。点数なしの場合は「-」
例:総合評価3.4の場合星3つ、総合評価3.9の場合星が3つと半分が表示される。
③日付については日にちのみ記載。時間は表示はなし。
④媒体の項目に食べログを追加

クチコミ返信画面
①食べログの総合評価と、お客様が来店時の利用詳細について「昼」「夜」「テイクアウト」「デリバリー」「その他」の中からアイコンで表示
②項目単位での評価点数を表示。未回答の項目は「-」表示。
※①の総合評価店は②の各項目の平均点ではありません。
③食べログ管理画面上の「クチコミ返信ガイド」へ遷移するボタンを表示

クチコミ返信後の仕様
・クチコミのステータスに「チェック中」「要修正」を追加
・食べログではクチコミ返信文を登録した際に、ページに公開するか食べログ側で審査が入る。
・そのためダッシュボード上でクチコミ返信文を登録した際に、クチコミのステータスは「チェック中」となる。
・審査完了時のステータスは以下のどちらかになる
①「 承認済・公開中」(ダッシュボード上ではGBPなどと同様の「済」)
②「要修正」
・要修正になった場合、修正理由が記載されるので内容にそった文章に変更後、再度申請する。
・申請後のステータスは再度「チェック中」となる
・ワークフローが必要なアカウントで文章を修正した場合、再度ワークフロー申請が必要となる。

まとめ|Google+食べログで“真の声”を掴む
ユーザーの行動は、「検索→比較→来店」という一連の流れの中で、複数のクチコミ媒体を自然に横断しています。Googleビジネスプロフィールだけでなく、食べログのレビューも日々の来店判断に直結している今、両方の声を拾い上げ、戦略に活かすことが飲食店にとって欠かせないアクションとなっています。
Googleと食べログ、それぞれが持つ「口コミの質」と「評価の傾向」は異なる軸を持っており、その違いを一元的に可視化できること自体が大きな価値です。MEO施策は、いま“多元的レビュー分析”の時代に入っています。
二大媒体の統合で、MEO戦略が進化する
これまでのMEOは、Googleマップ上の評価やクチコミ件数の増加にフォーカスされてきましたが、それだけでは見えてこない「本当の評価」や「業態ごとの改善点」が存在します。
たとえば、
Googleでは「接客やアクセス面」の評価が多く、
食べログでは「料理の味や提供スピード」に関する感想が目立つ。
こうした媒体特性を把握した上で、両方の情報を組み合わせると、「どのチャネルで、どんな印象を持たれているか」が立体的に見えてきます。これは、単なる点の評価を“ブランド全体の印象値”へと引き上げるための重要な視点です。
クチコミートのダッシュボード上では、Googleと食べログのレビューを並列に分析できるため、「Googleでは良いが食べログでは普通」などのギャップを即座に把握でき、改善施策の優先順位付けにも活用できます。
クチコミは、単なる評価ではなくブランドとの接点であり、マーケティングと現場改善の両輪を動かす原動力です。Googleと食べログの両面から“真の声”を捉えることで、飲食店のMEOは次のフェーズへと突入しています。

口コミはもはや「評価」ではなく、ブランドと顧客をつなぐ大切な接点であり、企業の成長を左右する重要な資産です。株式会社ジャリアでは、GoogleビジネスプロフィールやSNS上の口コミを戦略的に活用するためのツール「クチコミート」を提供しています。
多地点での順位管理、競合比較、構造化データの最適化までをワンタグで連携し、クチコミ施策を“集客につながるブランディング”へと進化させる支援を行っています。口コミをただの評価に終わらせず、自社の価値を伝える力に変えたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。