【完全版】採用ブランディングとは?実践戦略の立案から成功事例・効果測定まで徹底解説
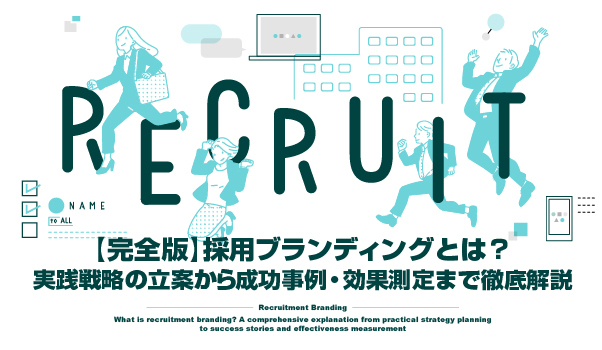
近年、日本の採用市場は“売り手市場の常態化”という言葉で表されるように、企業側が人材を確保すること自体が難しくなっています。人口減少・転職意欲の高まり・働き方の多様化が同時に進行し、優秀な人材ほど複数の企業を比較しながら「自分に合う会社」を主体的に選ぶようになりました。
特にZ世代・ミレニアル世代の求職者は、給与や待遇だけでなく、
「この会社で働く自分を誇れるか」
「社会的に意義のある仕事か」
「価値観やカルチャーが自分と合うか」
といった感情的価値を重視します。そのため、単なる求人広告や採用ページの情報発信だけでは、彼らの心に響かない時代になっています。
つまり、企業に求められているのは「採用活動=短期的な募集行為」ではなく、「採用ブランディング=長期的な共感形成と信頼構築」への転換なのです。
|
目次
|
なぜ「採用広報」ではなく「採用ブランディング」なのか
「採用広報」という言葉はよく使われますが、これは“伝える”ことに主きを置いた活動です。一方「採用ブランディング」は、“伝える”だけでなく、「どう認識され、どう記憶されるか」までをデザインする行為です。
たとえば同じ「動画」を使った採用施策でも、
- 採用広報:企業説明をわかりやすく伝える
- 採用ブランディング:企業の想い・文化・社員のリアルな姿を通して“共感”を生み出す
という目的の違いがあります。「採用広報」は手段、「採用ブランディング」は戦略。後者は採用活動全体の“軸”を定め、“誰に、何を、どう伝えるか”を一貫させる指針なのです。
採用市場が成熟するほど、単なる情報発信では差別化が難しくなり、「どんなブランドとして認識されるか」が、応募の数と質を左右します。
その意味で、「採用ブランディング」はもはや一部の大企業だけの戦略ではなく、すべての企業が取り組むべき“経営課題”といえるでしょう。
本記事では、「採用ブランディングとは何か?」という定義から始まり、実践的な戦略立案・媒体別の施策・成功事例・効果測定までを、解説します。
- 自社が「どのように見られているか」が明確になる
- 採用戦略の軸となるメッセージを設計できる
- 採用サイトや動画など、具体的な施策の方向性がわかる
- 自社の強みを活かしたブランディング戦略を描ける
そして最終的には、単なる“採用成功”にとどまらず、「企業のファンを増やす」という長期的な価値創出へとつながるはずです。
採用ブランディングの定義と目的
まずは、採用ブランディングの定義と目的についての理解を深めていきましょう。ここでは「そもそも採用ブランディングとは何か」「なぜ今それが重要視されているのか」を明確にし、企業がこの取り組みを行う意義を整理していきます。
【H3】「採用ブランディング」と「コーポレートブランディング」の違い
「採用ブランディング」という言葉を聞くと、多くの方が「企業のイメージをよくすること」と捉えがちです。しかし、ここで重要なのは“誰に対してのブランドなのか”という視点です。
- コーポレートブランディング:顧客・株主・社会に向けて「企業そのものの価値」を高める取り組み
- 採用ブランディング:求職者・社員に向けて「働くブランド価値」を高める取り組み
つまり、両者は目的もアプローチも異なります。コーポレートブランディングが「製品やサービスを通じて信頼を得る活動」だとすれば、採用ブランディングは「働く姿を通じて共感を得る活動」です。
たとえば、ある企業が「お客様の暮らしを支える」という企業ミッションを掲げていたとします。コーポレートブランディングの文脈では、そのミッションを製品・サービス・広告を通して社会に伝えます。
一方で採用ブランディングの文脈では、社員がその理念をどのように体現し、どんな価値観で働いているのかを見せることで、求職者の共感を得ていくのです。
この2つは独立した活動のように見えて、実は密接に結びついています。顧客から信頼される企業は、求職者からも“誇りを持って働ける会社”として認識されやすく、逆に社員が魅力的に働く姿を発信している企業は、社会的信頼の向上にもつながります。
採用ブランディングとは、“内と外の信頼をつなぐブリッジ”のような役割があるとも言えます。
つまり、「社内文化 × 社外認知」の交差点に位置する活動であり、企業の成長を“人”の観点から支える戦略的アプローチなのです。
企業が直面する採用課題とその根本原因
採用ブランディングの必要性を理解するためには、まず企業が現在抱えている課題を正しく把握する必要があります。今、多くの企業が共通して直面しているのは、次の3つの構造的な問題です。
採用競争の激化
大手・人気企業への応募集中、求人媒体の多様化、スカウト市場の拡大などにより、母集団形成が年々難しくなっています。かつては「求人を出せば応募が来る」時代でしたが、今は企業側が“選ばれる側”に立っています。
求職者が企業を比較・検討することが当たり前となり、ブランド力が採用成功のカギを握るようになりました。
情報過多による“比較疲れ”
SNS・口コミサイト・社員レビューなど、企業情報があふれる現代では、求職者は多くの情報にさらされています。その結果、どの会社も似た印象に見えてしまい、差別化が難しくなっているのが現状です。
「給与や福利厚生」だけで選ばれる時代は終わり、「自分に合う文化」や「共感できる価値観」が選択基準になりつつあります。
定着率・エンゲージメントの低下
採用段階で企業の“リアル”が伝わっていないことにより、入社後にミスマッチを感じるケースが増えています。「思っていた会社と違った」という理由で離職する若手も多く、採用コストが無駄になるだけでなく、社内士気の低下にもつながります。
これらの根本にあるのが、「企業の価値をどのように伝え、どのように感じ取らせるか」というブランディング視点の欠如です。
求人広告や採用説明会といった“短期的な採用施策”ではなく、企業が長期的に「この会社で働きたい」と思ってもらえる“ブランドとしての信頼構築”が求められています。
“人を集める”採用から、“人が集まる”採用へ。この発想の転換こそが、採用ブランディングが今まさに必要とされている理由なのです。
ブランディングがもたらす採用効果とは?
採用ブランディングを戦略的に実践すると、単なる採用活動を超えた多面的な効果が生まれます。ここでは、代表的な3つの成果を具体的に見ていきましょう。
① 応募母数の拡大
企業の認知度が高まることで、自然検索やSNS、口コミ経由の応募が増加します。「なんとなく気になった会社」から「この会社で働きたい会社」へと意識が変わり、応募の入口が広がることで採用の選択肢も増えていきます。特に若年層においては、広告よりも“共感できるストーリー”が応募動機につながりやすい傾向があります。
② 応募者の質の向上
ブランドメッセージが明確になると、自社の価値観に共感した人材が集まりやすくなります。「自分の考え方と会社の方向性が合っている」と感じた応募者は、選考過程でもより前向きに関わってくれます。結果的に、面接通過率や内定承諾率が上がり、採用のミスマッチが減少します。この“質の向上”は、採用コストの削減にも直結します。
③ 入社後の定着率・エンゲージメント向上
採用段階で企業文化や価値観を丁寧に伝えることで、入社後のギャップが小さくなります。「自分はこの会社の一員でありたい」という意識が強まり、結果的に離職率の低下やエンゲージメント向上につながります。実際、ブランディングに注力している企業では、従業員の定着率が平均で10〜20%改善したというデータもあります。
離職率が問題となる中で、定着率が上がることはそれ自体がブランディング効果を生み出します。働く人が「この会社で働いて良かった」と自然に語ることが、最も強い採用メッセージになるからです。
採用ブランディングは、企業と人をつなぐ“信頼構築の仕組み”です。単なる採用手法ではなく、「人を通じて企業価値を高める経営戦略」としての役割を担います。
そしてこの考え方を持つ企業こそが、激しい採用市場の中でも“選ばれ続ける企業”になっていくのです。

採用ブランディングの戦略立案の5ステップ
採用ブランディングを成功に導くためには、「なんとなく良い印象を与える」ではなく、戦略的に全体設計を行うことが欠かせません。感覚的なPR活動に頼るのではなく、課題発見から実行・改善までを体系的に設計するプロセスが必要です。
ここでは、採用ブランディングを進める上での基本ステップを5つに分けて整理していきます。
① 採用課題の明確化
まず最初に行うべきは、自社の現状を正しく把握することです。「応募が集まらない」「内定辞退が多い」「入社後の定着率が低い」など、採用に関する課題は企業によってさまざまです。
重要なのは、“感覚ではなくデータで課題を定義する”こと。過去の採用活動を定量的に振り返り、どのフェーズで離脱が多いのか、どの媒体からの応募が多いのかなどを分析することで、次の一手が見えてきます。
現状を整理する際の主な観点は以下の通りです。
- 過去の採用データ(応募数・内定率・離職率・承諾率)
- 競合他社との比較(採用サイト・SNS発信・口コミ・採用動画)
- 求職者アンケートや面接後フィードバック(「応募理由」「辞退理由」など)
たとえば、応募数が多いのに承諾率が低い場合は「ブランドメッセージに共感してもらえていない」、逆に応募数が少ない場合は「そもそも認知が足りていない」など、問題の本質が見えてきます。
課題を“言語化”できれば、採用ブランディングの方向性は自然と定まります。現状分析こそが、戦略立案のすべての出発点です。
② 採用ターゲットのペルソナ設計
次に行うのが、採用したい人材像の明確化です。ここで間違ってはいけないのは、ペルソナとは「理想のスキルセット」ではなく、「価値観と行動心理」までを描くものだということです。
たとえば、Z世代の新卒をターゲットにするなら、「何にモチベーションを感じ、どんな働き方を望んでいるのか」「企業選びの際にどんな情報を重視しているのか」まで具体的に掘り下げていく必要があります。
ペルソナを設計する際は、以下の3視点で整理すると明確になります。
- デモグラフィック(年齢・学歴・居住地・職種)
- サイコグラフィック(価値観・関心・キャリア観)
- ビヘイビア(情報収集行動・SNS利用傾向・応募経路)
この分析により、
- どんなメッセージを伝えるべきか
- どんな媒体で発信すべきか
- どんなデザイン・トーンが響くか
が一気に明確になります。
たとえば、20代前半層なら「リアルで温かみのある社員インタビュー」が効果的ですが、30代の中途層なら「事業成長性やキャリア形成の明確さ」を重視する傾向があります。
“誰に語りかけるのか”を定義することは、“どんな言葉で語るか”を決めること。ペルソナ設計は、すべての施策の一貫性をつくる起点となります。
③ コアメッセージ(EVP)の策定
採用ブランディングの中心にあるのが、「EVP(Employee Value Proposition/従業員価値提案)」です。これは、「なぜあなたの会社で働く価値があるのか」を端的に示すメッセージのこと。
EVPが明確な企業は、どの発信内容にも“芯”が通っています。逆にEVPが曖昧だと、採用動画・求人・SNS投稿などがバラバラになり、印象が散漫になってしまいます。
EVPを策定する際は、次の3つの価値の重なりを意識しましょう。
- 企業が伝えたい価値(Vision・Mission・Culture)
- 従業員が感じる価値(働くやりがい・成長実感)
- 求職者が求める価値(安心・挑戦・社会貢献)
この3つが重なる部分こそが、採用ブランドの「核」となります。単なるキャッチコピーではなく、社内外が共通認識として共有できる“旗印”のような存在です。
たとえば、「挑戦する人が主役の会社」「個性を尊重し合う文化」など、短い一文でも理念を感じられる言葉を軸に据えると、ブランドとしての一貫性が生まれます。
EVPは“外に伝えるための言葉”ではなく、“内から湧き出る言葉”。経営陣・社員・採用担当が同じ方向を向けるメッセージこそが、強いブランドを育てます。
④ タッチポイントとチャネルの選定
採用ブランディングの成功は、メッセージを「どこで」「どう伝えるか」によって大きく左右されます。ターゲットが触れるチャネルを特定し、最適なコンテンツを配置することが欠かせません。
代表的なタッチポイントには以下のようなものがあります。
- 採用サイト(一次接触のメイン拠点)
- SNS(Instagram、TikTok、Xなど)
- 採用動画・会社紹介動画
- 求人媒体やオウンドメディア
- 会社説明会・インターンシップイベント
たとえば、Z世代向けには「SNSでのショート動画」や「社員の1日密着型ストーリー」が効果的。一方、中途層には「事業の社会的意義」や「キャリアパス」を中心に据えた採用サイト構成が響きます。
大切なのは、「全チャネルで一貫したメッセージを発信すること」。どの媒体でもトーンやビジュアル、言葉の選び方に統一感を持たせることで、ブランド体験の質が高まります。
また、各チャネルの効果を定期的に検証し、アクセスデータ・応募率・エンゲージメント率をもとに改善していくことも忘れてはいけません。“作って終わり”ではなく、“動かしながら磨く”視点が重要です。
⑤ 実行計画と運用体制の設計
最後に行うべきは、戦略を“継続的に機能させる仕組みづくり”です。採用ブランディングは一度発信して終わるものではなく、運用を通じて徐々に成熟していくプロジェクトです。
運用体制を整える際の主なポイントは以下の通りです。
- 社内での責任者・推進メンバーを明確にする
- 年間スケジュールやKPIを設定する
- SNS運用・動画更新などを定期ルーティン化する
- 外部パートナーと連携し、専門領域を補完する
特に中小企業では「採用担当がすべてを担う」ケースが多く、リソース不足が課題になりがちです。そのため、内製(社内理解)×外注(専門性)を組み合わせた“ハイブリッド体制”を構築することが現実的です。
また、運用フェーズでは「社内報告とナレッジ共有」も重要なポイント。成功した施策・失敗した施策を定期的に社内で共有し、組織として知見を蓄積していくことで、ブランディングが“属人的な活動”から“組織の資産”へと変わります。
採用ブランディングの成功は、「設計の質」と「運用の継続力」で決まります。この5ステップを着実に実践することで、単なる採用施策ではなく、企業の魅力を社会に伝える“長期的なブランド戦略”としての採用ブランディングが実現します。

採用ブランディングの成功に必要な社内体制とマインドセット
採用ブランディングの戦略や施策をどれだけ緻密に設計しても、社内に浸透していなければ成果は長続きしません。ブランディングの本質は「組織の文化」そのものであり、それを支えるのは社内体制と社員一人ひとりの意識です。
採用ブランディングを定着・継続させるために必要な社内の仕組みとマインドの整え方についても理解を深めておきましょう。
採用ブランディングは「人事だけの仕事」ではない
多くの企業では、採用活動=人事部門の仕事と捉えられがちです。しかし、採用ブランディングは「組織全体でつくるもの」。なぜなら、候補者が魅力を感じる瞬間の多くは、現場社員との接点や、会社の雰囲気そのものにあるからです。
人事部が設計した戦略を現場が実践し、経営層がそれを支える。この三位一体の構造が整って初めて、採用ブランディングは機能します。
「採用広報を外に発信すること」だけでなく、「社員一人ひとりが自社の代表である」という意識を持つこと。これが、採用ブランディングを“組織文化”として根づかせる第一歩になります。
経営層・現場社員を巻き込む3つのステップ
採用ブランディングを社内全体で進めるには、経営層の理解と社員の協力が欠かせません。いくら人事や広報が戦略を立てても、経営が本気で取り組まなければ“会社の方針”として浸透せず、また社員が自発的に動かなければ“文化”として根づきません。
採用ブランディングとは、単に「採用をよく見せる活動」ではなく、企業の存在意義や価値観を、内外に一貫して伝えていく取り組みです。
そのためには、トップから現場までが同じ方向を向く必要があります。ここでは、その実現に向けて有効な3つのステップを紹介します。
① 経営層が「採用を経営テーマ」として発信する
採用ブランディングを成功させるためには、まず経営層が「採用は企業の成長戦略の一部である」と明確に示すことが欠かせません。採用を“人事任せ”にしている企業と、“経営の中核”に置いている企業では、成果に大きな差が生まれます。
経営層の発信には、次のような効果があります。
- 社員が「採用は全員の仕事である」と認識できる
- 候補者が企業の本気度を感じる
- 経営のビジョンと採用メッセージが一致し、ブレない
たとえば、トップ自らが採用動画や採用サイトで語ることで、求職者はその会社の“方向性”や“価値観”を直感的に理解できます。単なる数値的な目標ではなく、「どんな人と、どんな未来をつくりたいのか」という想いを発信することが重要です。
また、経営層の発信は社内にも強い影響を与えます。「社長が採用にここまで熱意を持っているなら、自分も関わってみよう」と社員が感じることで、採用活動が“人事部の仕事”から“全社のミッション”へと変化します。経営トップが率先して採用に関心を示すことこそ、ブランディング成功の起点なのです。
② 社員が“発信者”になる場をつくる
次に必要なのが、「社員が自ら会社の魅力を語る文化」をつくることです。求職者にとって最も信頼できる情報源は、企業の広告ではなく、実際に働いている社員の声です。
社員が登壇する採用イベント、社内でのインタビュー動画、SNSでの日常発信など、社員が“主役”として登場する場を意識的に設けましょう。「人事が話す会社」から「社員が語る会社」へと変わることで、ブランドの温度が一気に上がります。
また、社員発信のメリットは社外だけでなく社内にもあります。自分の仕事や会社の魅力を言葉にすることで、社員自身が自社の理念や文化を再認識できるのです。
「発信する=自社理解が深まる」というサイクルが生まれれば、それ自体がインナーブランディングとして機能します。
ただし、社員発信を促す際に注意すべきなのは、「無理やりやらせない」こと。重要なのは、社員が安心して発信できる環境づくりです。発信のルールやトーンをまとめたSNSガイドラインを整備し、成功事例を共有することで、社員が自信を持って“会社の顔”になれる仕組みを作りましょう。
③ 社内で成果を共有する
採用ブランディングの効果を社内で可視化し、成果を“数字”と“ストーリー”の両方で共有することも欠かせません。ブランディングは目に見えにくい活動だからこそ、「やって意味がある」と実感できる瞬間をつくることが重要です。
たとえば、
- 応募数・フォロワー数・サイトアクセス数の変化を定期的に報告する
- 社員発信がどのくらい反響を得たかを可視化する
- 採用につながった成功事例を全社ミーティングで共有する
といった取り組みを行うだけでも、社内の意識は大きく変わります。
また、成果共有の場では「数字」だけでなく、「応募者の声」や「社員が感じた変化」などの“ストーリー”を紹介することが効果的です。「自分たちの取り組みが、誰かの共感を生んでいる」と実感できると、社員のモチベーションが自然に高まります。
この積み重ねによって、採用ブランディングは“人事施策”から“全社員でつくる文化”へと変化していきます。成果の共有は、社員を“巻き込む”だけでなく、“育てる”行為でもあるのです。
採用ブランディングを継続的に機能させるには、経営層の旗振りと社員の自発的な関与、その双方が欠かせません。トップのメッセージが理念を方向づけ、社員の声がリアリティをもたらす。
この二つが噛み合ったとき、採用ブランディングは単なる戦略を超え、企業文化そのものを動かす力になります。
社員を“発信者”に変えるインナーブランディングの重要性
採用ブランディングとインナーブランディング(社内ブランディング)は密接に関係しています。外に見せるブランドは、内側の文化が整っていなければ持続しません。
インナーブランディングの目的は、社員が自社の理念や価値観を理解し、「自分ごと化」すること。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- 社員が自社の価値観を語れるようにするワークショップ
- ミッション・ビジョンに基づく社内表彰制度
- 社員同士の“ありがとう”を可視化する社内ツールの活用
- 社内報や動画でのストーリー共有
社員が自社のブランドを“他人事”ではなく“自分の物語”として捉えられるようになると、発信の質が変わります。結果として、採用ブランディングが「自然発生的に続く文化」へと成長していくのです。
社内文化を可視化する仕組みづくり
採用ブランディングは、目に見えない“文化”をどう可視化するかが鍵です。そのためには、情報を「見える化」し、共有できる仕組みを整える必要があります。
たとえば、
- 社内ポータルで採用施策や社員ストーリーを共有する
- チーム単位で発信テーマを決めてSNSで発表する
- 新入社員が感じた“会社の魅力”を毎年アーカイブ化する
こうした仕組みを通して、企業の文化や人の想いを蓄積していくと、ブランドが“組織の資産”として積み上がっていきます。
採用ブランディングの最終的なゴールは、「社員一人ひとりがブランドの担い手になる」こと。それが実現すれば、採用・広報・経営が自然と連動し、企業全体が“共感を生み出す組織”へと進化していきます。

【媒体別】採用ブランディング施策
採用ブランディングを実際に形にしていく段階では、どの媒体(チャネル)をどう活用するかが鍵になります。ここでは、代表的な5つの媒体を取り上げ、それぞれの役割と効果的な活用方法を解説していきます。
採用サイト(コーポレートサイトとの関係性)
採用ブランディングの中心的な役割を担うのが「採用サイト」です。コーポレートサイトが“企業の顔”だとすれば、採用サイトは“企業の人格”を伝える場といえます。
求職者が最も長く滞在し、最も多くの情報を得るのが採用サイトです。単なる求人情報の羅列ではなく、「企業の価値観」「社員の姿」「働く環境」を伝える構成が求められます。
効果的な採用サイトにするためのポイントは以下の通りです。
- トップページで「自社らしさ」を一目で伝えるデザイン
- 社員インタビューやストーリーでリアリティを演出
- ミッション・ビジョン・カルチャーをビジュアルで表現
- 求職者が次のアクションを起こしやすい導線設計
また、採用サイトはSEO(検索対策)やSNS連携の基盤にもなるため、情報発信の“ハブ”として戦略的に設計することが重要です。
採用動画(ストーリーテリングと感情訴求)
近年、動画は採用ブランディングの中でも特に影響力の大きい媒体として注目されています。言葉では伝わりにくい「空気感」や「人の魅力」を、映像と音で直感的に伝えられるのが大きな強みです。
採用動画には大きく3つのタイプがあります。
- 企業紹介動画:会社の理念やビジョンをわかりやすく伝える
- 社員インタビュー動画:働く人のリアルな姿を通して共感を生む
- 1DAY密着・ドキュメンタリー動画:日常業務や文化を体験的に見せる
動画制作の際は、「感情を動かす構成」を意識しましょう。最初の5秒で興味を引き、ストーリーの中盤で共感を得て、最後に「自分もここで働きたい」と思わせるような展開が理想です。
また、TikTokやYouTubeショートなどの短尺動画も効果的。Z世代への訴求には、テンポとリアル感が鍵となります。
SNS運用(Instagram/TikTok/Xの特性比較)
SNSは“日常の延長線上で企業を感じてもらう”ための最適なツールです。各プラットフォームの特徴を理解し、目的に合わせた発信を行うことが重要です。
|
プラットフォーム |
特徴 |
向いている発信内容 |
|
|
視覚的な世界観・統一感が重要 |
社員紹介、カルチャー紹介、リール動画 |
|
TikTok |
エンタメ性と共感のスピード感 |
若年層向けショートストーリー、社風のリアルな発信 |
|
X(旧Twitter) |
情報拡散力が高い |
募集告知、採用イベント、日常のつぶやき発信 |
SNS運用では“投稿頻度”よりも“継続性”が大切です。定期的に情報を発信することで、企業の存在を自然に印象づけることができます。
また、コメントへの返信や社員のリポストなどを通して、双方向のコミュニケーションを意識しましょう。これが「共感」と「信頼」の形成につながります。
採用ピッチ資料・会社説明会資料の最適化
採用ピッチ資料は、企業と求職者が“初めて対話する瞬間”を支えるツールです。会社説明会や面談で使用するスライドのクオリティ次第で、企業イメージは大きく変わります。
構成の基本は次の流れです。
- 会社の理念・存在意義
- 事業内容と成長性
- 社員・チームの紹介
- 働く環境・制度
- 求める人物像
ビジュアル面では、フォント・色使い・写真選定に統一感を持たせることで、ブランドの一貫性が生まれます。「資料=デザイン」ではなく、「資料=ストーリーテリングツール」として設計することが大切です。
リアルイベント・社内見学・オープンカンパニー施策
オンライン施策が主流となった今でも、リアルでの接点は強力な印象を残します。特に学生や若手層にとって、「実際の社員に会う」「オフィスを見学する」体験は、企業理解を深める貴重な機会です。
効果的なリアル施策のポイントは以下の通りです。
- 現場社員が登壇するカジュアルトーク形式
- オフィスツアーで“働くリアル”を体感させる
- SNSでイベントの様子を発信し、二次的な認知拡大につなげる
リアルとオンラインを掛け合わせる「ハイブリッド採用イベント」も増えています。
オンラインで興味を持たせ、リアルで信頼を得るという流れを意識すると効果的です。
成功事例から学ぶ採用ブランディング
実際に採用ブランディングを行って成果を上げている企業には、いくつかの共通点があります。ここでは、大手企業・中小企業・業種別の3つの観点から、成功のポイントを整理していきます。
大手企業の戦略型ブランディング事例
大手企業では、採用ブランディングを「経営戦略の一部」として位置づけているケースが多く見られます。特に注目すべきは、企業理念や社会的意義を軸にした“共感訴求型”のブランディングです。
例えば、グローバル展開を行うメーカーでは、「世界中の人々の生活を豊かにする」という企業ミッションを採用コンセプトに落とし込み、社員一人ひとりがその理念を語る動画を制作していました。
この結果、応募者の7割以上が「企業理念に共感した」と回答し、採用広報が“企業文化の可視化”へと進化しました。
また、IT業界の会社は、採用動画や採用サイトのトーンを統一し、「ブランド体験としての採用活動」を実現。SNS運用でもコンテンツを分散させず、採用から入社後のオンボーディングまで一貫してブランドストーリーを展開しています。
重要なポイントは、理念・ミッションを起点に採用体験をデザインしているかどうか、です。
単なる告知活動ではなく、「ブランドと共感の設計図」として採用を捉えている点が共通しています。
中小企業の創意工夫による成功事例
一方、中小企業では予算や人員が限られる中で、“自社の強みを活かした等身大の発信”が成功の鍵となります。
たとえば、地方の製造業の会社では、社員が自らスマートフォンで日常の仕事風景を撮影し、Instagramで発信。「派手ではないけれど、まじめにモノづくりに向き合う姿」が若手層に共感を呼び、結果的に応募数が前年比150%まで増加しました。
また、ベンチャー企業は、経営者が自社の採用理念をnoteやYouTubeで発信し、求職者に直接語りかける形で認知を拡大。社長の言葉が“ブランドメッセージそのもの”として機能し、採用だけでなく取引先からの信頼も向上しました。
小さな企業ほど「リアルさ」「人の温度感」が最大の武器になる。等身大の発信が、企業文化を最も自然に伝える採用ブランディングの原動力になります。
業種別(IT・製造・医療・サービス)のアプローチ比較
業種によっても採用ブランディングの方向性は異なります。自社の特性に合った戦略を立てることで、より効果的にターゲット層に訴求することができます。
- IT業界:スピード感と挑戦を前面に出し、動画やSNSでカルチャーを発信
- 製造業:職人の技術や品質へのこだわりを「誇り」として見せる
- 医療・福祉業界:社会的使命・やりがいをストーリーで伝える
- サービス業界:接客・チームワーク・人の魅力を中心に据える
それぞれに共通するのは、「人を通して伝える」ことです。どの業界でも、“社員が自社を語る”瞬間こそが最も信頼を生み出します。
成功している企業は、業種を問わず「伝える内容」よりも「どう共感を生むか」を重視しています。この意識こそが、採用ブランディングを“仕組み”として根づかせる第一歩です。
採用ブランディングと企業価値の関係性
採用ブランディングは「人を採用するための活動」として捉えられることが多いですが、実際にはもっと広い影響を持つ“経営ブランディングの起点”でもあります。ここでは、採用を超えて企業価値そのものを高めるための視点から、その関係性をお伝えしていきます。
採用ブランディングは「企業ブランディングの入り口」である
採用活動は、求職者だけでなく社会全体に向けて「自社の在り方」を発信する場でもあります。たとえば、採用サイトや動画、SNS投稿を通じて「社員がどう働き、何を大切にしているか」を発信することは、求職者だけでなく取引先・顧客・地域社会にも届いています。
つまり、採用ブランディングは単なる採用戦略ではなく、企業ブランディングの入り口なのです。
採用の文脈で語られるメッセージが、そのまま企業文化や理念の体現として機能する。これは、外部に対してだけでなく、社内にも「自分たちはこういう価値を提供している」という再認識をもたらします。
実際、多くの企業が採用ブランディングをきっかけに、自社のブランドメッセージを再定義しています。“採用のために始めた発信”が、“企業そのものを磨く活動”へと発展していくというのが採用ブランディングの本質的な価値です。
採用から始まる“ファンベース経営”とは
採用ブランディングを通じて企業の魅力を発信し続けると、そこに共感する人が少しずつ増えていきます。その人たちは、まだ応募者や社員でなくても、ブランドの“ファン”になっていきます。
この「共感の輪」を広げていくことこそが、ファンベース経営の第一歩となります。
ファンベース経営とは、顧客や社員など、企業に共感し支援してくれる“ファン”を中心に組織を成長させる考え方。採用ブランディングは、このファンを生み出す起点として機能します。
たとえば、ある企業では、採用SNSで発信していた社員紹介動画が話題になり、結果的に顧客からの信頼や問い合わせが増えたというケースもあります。
「どんな人が働いているか」を見せることで、“どんな会社か”が伝わる。採用ブランディングは、ファンベース経営の“入口”であり、企業成長の循環をつくる活動なのです。
社員エンゲージメントと企業成長の相関関係
採用ブランディングの取り組みを進めていくと、最も変化が現れるのは“社内”です。社員が自社の理念やビジョンに改めて触れる機会が増え、自分の仕事の意味を再確認できるようになります。
この「自分の仕事が会社のブランドに貢献している」という実感が、社員エンゲージメントの向上につながります。
そして、社員エンゲージメントの高い企業ほど、
- 離職率が低く、定着率が高い
- 生産性・顧客満足度が高い
- 結果的に収益性が安定している
という調査結果も多く報告されています。
つまり、採用ブランディングは外部に向けた広報活動に見えて、実は社内文化を強くする経営施策でもあるのです。「働く人が誇りを持てる会社」は、自然と外からも魅力的に見える。その好循環が、長期的なブランド価値を支える基盤となります。
ブランド資産としての「人の声」活用方法
企業の“信頼”を築く上で、最も強い影響力を持つのは広告ではなく、“人の声”です。採用ブランディングでも、社員や元社員、求職者などのリアルな発信がブランド資産として機能します。
たとえば、
- 社員がSNSで日常の仕事を紹介する
- 内定者が会社の印象をポジティブに語る
- 顧客が「この会社の人は信頼できる」と投稿する
こうした“自発的な声”は、企業がどんなメッセージを出すよりも強力なブランディング効果を生みます。
重要なのは、企業がこの発信を「コントロール」するのではなく、「応援しやすい環境を整える」こと。たとえば、社員が安心してSNSで発信できるガイドラインを設ける、社内コミュニケーションツールで共有を促すなど、自然発生的な発信を支える仕組みづくりが大切です。
“人の声”をブランド資産として活かすことで、企業はより立体的な存在になります。採用ブランディングの成功は、広告ではなく「人の温度」で伝わる信頼に支えられているのです。

採用ブランディングの効果測定と継続改善
採用ブランディングは「つくって終わり」ではなく、成果を見える化し、改善を重ねることで育っていくものです。ここでは、効果を測定するための具体的な指標と、継続的にブランドを磨いていくための考え方を解説します。
KPI設定(応募数/内定承諾率/定着率)
採用ブランディングの成果を定量的に把握するには、KPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。代表的な指標として、次の3つを中心にモニタリングしていきます。
応募数:認知拡大や採用サイト・SNS施策の効果を測る指標
内定承諾率:ブランドメッセージの共感度や選考体験の質を測る指標
定着率:採用後のカルチャーフィット・入社後満足度を測る指標
これらを単体で見るのではなく、「どの施策がどの数値に影響しているか」を分析することが重要です。たとえば、応募数が増えても承諾率が低ければ、メッセージや体験にズレがある可能性があります。
逆に、応募数は少なくても定着率が高い場合は、“質の高い採用”が実現できているということです。
数値の良し悪しだけに一喜一憂するのではなく、「数字の裏側にある人の感情」を読み取る視点を持つと、改善の方向性が見えやすくなります。
効果測定ツールとデータ分析
効果測定を行う際は、定量データと定性データの両方を組み合わせることが大切です。
定量データとしては、Googleアナリティクスなどを活用し、採用サイトのアクセス数や流入経路、滞在時間などを把握します。また、求人媒体やSNSのエンゲージメントデータを分析することで、どのチャネルが効果的かを定期的に検証できます。
一方で、数字だけでは見えない“求職者の印象”や“体験の満足度”も重要な判断材料です。面接後アンケートや内定者ヒアリングを通して、「なぜ応募したのか」「なぜ入社を決めたのか」「他社と比べてどんな印象だったか」といった定性的なデータを収集することで、ブランド体験のリアルな反応を掴むことができます。
ブランディングは感情に根ざす活動だからこそ、データを“人の声とセットで”読み解くことが成功の鍵です。
PDCAの回し方と継続的改善のポイント
採用ブランディングを継続的に成長させるには、「発信して終わり」ではなく、改善を前提とした運用体制を整えることが必要です。基本は、以下のようなPDCAサイクルで回していきます。
Plan(計画) :目的・KPI・メッセージを設定する
Do(実行) :媒体ごとに最適な形で発信・実施する
Check(検証) :アクセスデータや応募傾向を分析する
Action(改善) :結果をもとに内容や表現をブラッシュアップする
改善のポイントは、“すべてを変えようとしないこと”です。うまくいった部分は継続し、課題のある部分だけを修正することで、ブランドの一貫性を保ちながら成長させることができます。
また、年単位での指標(例:エンゲージメントスコア、SNSフォロワー数、サイト滞在時間など)を追うことで、短期的な数値だけでは見えない「ブランディングの成熟度」を可視化することも可能です。
採用ブランディングは“走りながら育てるもの”。改善を繰り返すことで、求職者だけでなく、社内のメンバーにも誇れるブランドへと進化していきます。
まとめ|成功の鍵は「戦略×クリエイティブ×実行力」
ここまで、採用ブランディングの定義から戦略立案、媒体別施策、成功事例、効果測定までを一通り解説してきました。最後に、採用ブランディングを継続的に成功へ導くための3つのポイントを整理しておきましょう。
採用ブランディングとは、単なる「採用活動の見せ方」ではなく、企業が社会や求職者に対して「どんな存在でありたいか」を形にする経営戦略です。短期的な採用成功だけを目的とせず、長期的な視点で“共感と信頼”を積み重ねていくことが大切です。
そのためには、
- 現状の課題を把握し、採用戦略の軸を定める
- 自社らしいメッセージ(EVP)を明確化する
- 採用サイト・動画・SNSなどの媒体を一貫性のあるトーンで運用する
- データ分析と改善を繰り返し、ブランドを継続的に育てる
といった「戦略的な設計」と「実行の持続力」が欠かせません。
採用ブランディングを社内だけで完結させようとすると、戦略設計・デザイン・動画制作・運用分析など、多岐にわたる領域をカバーする必要があります。このすべてを自社で行うのは現実的には難しく、多くの企業が「アイデアはあるのに形にできない」という課題を抱えています。
採用ブランディングは、見た目を整える活動ではありません。それは、「企業が何を信じ、どんな未来を描こうとしているのか」を社会に伝える行為です。
戦略 × クリエイティブ × 実行力。この3つの軸がそろったとき、採用は“告知”ではなく“共感”へと変わります。そしてその共感が、企業の未来を支える「人」を惹きつける最大の力となるのです。
▶︎関連記事
【新卒・中途別】ターゲットに響く採用メッセージの作り方
【中小企業向け】予算とリソースがなくてもできる採用ブランディング
【動画活用】応募率が劇的に上がる採用動画の企画・制作ガイド
SNS採用ブランディング|InstagramとTikTokの最新活用術
採用ピッチ資料・会社説明会スライドの構成とデザインの極意とは?
採用サイトのSEO戦略|求職者に見つけてもらうための施策
採用ブランディングの「費用対効果」を最大化する予算配分と相場
インナーブランディングと採用ブランディング|社員を巻き込む施策と成功事例とは?

| WRITER / demio 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部 クリエイティブディレクター 株式会社ジャリア福岡本社 WEBマーケティング部は、ジャリア社内のSEO、インバウンドマーケティング、MAなどやクライアントのWEB広告運用、SNS広告運用などやWEB制作を担当するチーム。WEBデザイナー、コーダー、ライターの人員で構成されています。広告のことやマーケティング、ブランディング、クリエイティブの分野で社内を横断して活動しているチームです。 |
※本記事は、株式会社ジャリアのWebマーケティング部による編集方針に基づいて執筆しています。運営ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。